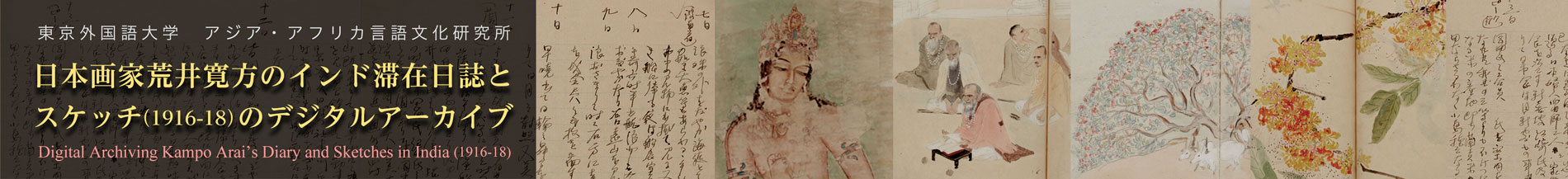- 《現地語の表記について》
本サイトでは、人名、地名、その他の固有名詞については、原則として現地語に基づくカタカナ表記を用いた。ただし、ラビンドラナート・タゴール(これは母語のベンガル語ではロビンドロナト・タクルとなる)など、すでに日本語でも親しまれている表記についてはそれを尊重した。また、日記翻刻などの記述については、固有名詞などは、適宜、修正を加えて、注を付すなどして補ったが、それ以外は当時の原文を尊重した。 - 《脚注について》
故・麗澤大学名誉教授の我妻和男氏による「荒井寛方-人と作品」中の印度日誌注釈を元に加筆および修正を行った。本文および注釈の(*)は翻刻者による加筆。
d19161113大正五(一九一六)年十一月十三日出発
十一月十三日午後七時の東京駅発車にて渡印の途に就けり。余を送るもの百数十人。親友大野静方兄、池田秋方兄1の二人、わざわざ神戸まで送らる。東京にては横山大観氏、横浜にては下村観山氏の送るあり。
汽車は急行車とて琵琶湖付近にて日の出を見、初旅の初感ここに始まる。同車内に原博氏(*原文は原博だが、原煕氏、農学者と思われる)あり。京都にて別れる。
d19161114十一月十四日
神戸には九時前に降着。尾張通り五丁目柴田館に宿をとり、すぐに大野君の長兄長谷川如是閑氏宅を訪問す。主人不在。三人休むこと一時間余り。昼飯の馳走にあずかって大阪に至る。
朝日において長谷川氏に会し、夕食を倶楽部に長谷川、大場の両君の五人にてなし、神戸の宿に帰る。
d19161115十一月十五日
京都に至りて近宗氏を岡崎の図書館に訪ね、四条、円山、清水を廻り、縄手の小川亭方(*肥後藩御用達の旅館で勤王志士たちが利用)
に寄り、宿を冨士館に重興を得て、囃子座の遊びに夜を明かすべし。

大正5(1916)年11月13日
〜11月16日(途中)
(1/85)
d19161116十一月十六日
電車の便をとりて、途中東福寺通天橋(*つうてんきょう)の紅葉を探り、大阪に至り、住友家に村山旬吾君を訪ね、そのほか上野、樋口氏を訪問なし、神戸に帰る。
この日堅山君も来神。その夜、友人の蓑林三雄君が余のために送別の会をなす。草野芦江、村山旬吾君もその座にありて興をとる。午後十時半の上りの汽車にて大野、池田の両兄帰り去る。嗚呼。
d19161117十一月十七日
さらにこの日、出航予定延期となること一日。時に降雨しきりなり。日本郵船の戸沢船長来る。夕刻高田鶴仙氏来たり、南風君の三人にて相生町の三輪牛肉店に十二時という時間まで興をむさぼり、女郎の送らざるところさらに得意の体。女郎のやらで帰るを得ず、ついに宿にて動けず。
この夜、小早川秋聲氏に会す。
d19161118十一月十八日
早朝高田鶴仙氏來る。そのほか二、三人の訪問者あり。
d19161119十一月十九日
大阪の西照庵主人來る。戸沢氏来たり宝屋に長崎料理を食す。
南風兄の友人財満、桑満氏の申すところに従い、桑満氏宅の昼食の招きに応ず。
d19161120十一月二十日出港
午前八時、いよいよ神戸出航。瀬戸内海の風光を愛で、伊予の辺りにて日は西山に傾く。
d19161121十一月二十一日
門司に上陸。ただちに停車場に至り博多見物のため乗車せんとす。時に知人岩田順一氏に出会い、それより乗車。途中の風望また見るべきものあり。この辺り柿の木の紅葉盛んにして、養牧の牛馬あり。すべての風望、風俗など関東に同じうせしところなし。車中に片岡仁左衛門などあり。
二時間余りにして博多に着く。末広というに鰻を食し、車を雇い市中見物に出かく。まず城跡を見て西公園に至る。この風光絶佳の地、小丘みな青松遠山をもって廻らし、博多湾を目の下に見て、湾を廻らす松樹まったく青く、その間に福岡、博多市街横たわり、まれに見る風望なり。
夕刻の急行車にて帰途につく。ただちに岩田氏を訪問す。その夜同氏の案内を得て門司第一という料理店に至り、女郎などの取り巻きに夜の更くるを忘れ、岩田氏宅に一夜。その前にうどん屋に入りて滑稽なこともあり。
d19161122十一月二十二日日本の地を去る
午前十時に帰船。いよいよ十二時出航。外海の初航海の第一日となる。
この日ことのほか天気晴朗。門司を出て六つれが(六連?)島を見、熊本県の西端を遠く見る。この日ようやく西の海に入らんとする夕日の色、絶佳をきわむ。時に船首にて音楽聞こゆ。水夫の旅情をなぐさむるとて、バイオリンを奏す。その音夕陽に和し、旅情の初感また妙なり。

11月16日(続き)
〜11月22日
(2/85)
d19161123十一月二十三日
早暁起き出でて海を望めば、ようやく日の出。初日はことに壮美をきわむ。午後は〇〇の遊び(*イラストあり)に時間を忘れる。この日きわめて浪静か。玄海の難所平日のごとし。
d19161124十一月二十四日
早暁出でて海を望めば浪やや増し、暖気ことに加わり、着衣一枚となる。堅山君のごときは早や床に入る。生などにても心気少しも快ならず。夜は船長をはじめ七、八名の者とカルタの遊びに十時となる。床に就く。
d19161125十一月二十五日
朝起き出でて見れば日ははや高く、早暁降雨ありし雲いまだ去らず。東に日の光に会いて虹を出す光景美し。
午後また運動、遊戯をなす。夜またカルタなどをなす。時にこの日午前より「ガス」すなわち靄(もや)ありて、四方を望み見るあたわず。夜に入りてますます深く、時に他船の近く汽笛するあり。初めての吾々にも、あまり気持よきものにあらず。
d19161126十一月二十六日
この日初めて支那の山を見る。実に愉快、また快を覚えたり。終日陸地を右に見て夜に入る。
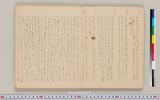
11月23日
〜11月27日(途中)
(3/85)
d19161127十一月二十七日香港
早暁出でてみれば、船ははや香港入口に来たりて、四方の風望いかにも支那式なると感を得る。ようやくにして港内に進む。この地は英国の要塞の地とて砲台多々あり。近きところには鉄条網など肉眼にても見るを得る。湾内に進むにしたがい小舟や人家も多く、支那国にいるごときの様ありて、ひとしお感を深くなす。
香港に着しただちに上陸す。不案内の吾々に対し船長、事務長よく案内の労をとれり。最初郵船会社に至り、それより山上高く「ケイブルカー」に乗り港内を見おろし、しばらくにして山を下り、支那料理の◯◯◯(*原稿欠)と言うにて昼飯をなす。一行の者みな支那語に通ぜず、そのおかしさかぎりなし。ようやくにして三、四品注文するを得て食す。その味は美。時に日本人なども多くこの家に来たり食する者あり。
食終りて電車に乗り西行す。よきほどにて下車、市街の有様を見物す。見るものことごとく目新しく、吾々には喜びかぎりなく、ことに雑沓をきわむる市中の有様は筆にてはつくし難く、そのまた不潔さもかぎりなく、家々にはよく透かし彫りの剪紙(*原文欠)をなし、看板などはもっとも意匠に進み、種々なる形や色をもってなす。売店にてはもっとも肉類を多く売買す。その不快なることまたあれども、一面より見れば面白くも感ず。市中雑感は後日画によりてなすべきのみ。
夕刻いったん船に帰り夕食をなす。再び船長、事務長の案内にて夜景を見るべく市中に至る。まず籠に乗り二、三丁を行く。試みなれば人力車に乗り換えをなすときに、籠かきの悪者が賃銭を再び求めんとす。ここにおいて吾々との間に悶着を生ずるときに、印度人の巡査来たりて我々の理をかい、ただちに籠かきのひとりを殴る。彼らは蜘蛛の子を散らせしごとく去れり。痛快々々。人力車にて進むこと六、七丁余りにして雑踏の街に至る。下車、日本町に入りて一泊す。
d19161128十一月二十八日
午後三時出航。港口のころに夕陽まさに入らんとす。その光景また美し。このとき浪著しく動くことはなはだし。
d19161129十一月二十九日
依然として浪高く、動揺に動揺をもってす。終日雲は黒く、風は速し。時に飛魚の飛ぶあり。
d19161130十一月三十日
早朝デッキに出でて日輪を拝す。浪また高し。
d19161201十二月一日
この日またまた北の風強く、浪きわめて高し。動揺すること前日に増し、南風君のごときは床にいる。生はこの大浪に少しも困ることなきは幸いなり。
d19161202十二月二日
前日のごとく風浪なお高くなりしも、午後よりようやく減じはじむ。
d19161203十二月三日
おいおい浪風少なく、この日船を四艘見る。午後七時ごろシンガポール(新嘉坡)の入口灯台のところに達す。十時ごろには同市の近くまで進む。時にサーチライトをもって海面を照らす。翌日のシンガポールを思い眠りに入る。
d19161204十二月四日新嘉坡(シンガポール)
早朝シンガポール港に入る。初めての熱国の朝。第一に目に入りしものは山。赤土の山に樹木生い繁り、洋式及び印度雑式の家屋その山上にあり。港内船舶また多し。陸地を見れば黒人が赤の腰巻をなし、様々の有様。ただただ感きわまりてただちに上陸。
船長及び事務長の案内で、沼田氏も同道にて見物に出かく。電車によりて日本人の旅館のあるところに至る。沼田氏の知家関田館にて茶を飲み、同船乗客の石橋、金子氏の宿たる青柳楼を訪ね、小時にしてそこを去り和蘭陀(オランダ)ホテルの大和商会に行く。店員の案内を得て和蘭陀ホテルに昼飯をなし、自動車に乗りて市中、市外を走らす。見るものことごとく快。ヤシの密林に入れば土人の家その間に点々として、その光景は言語につくし難し。快また快を覚ゆ。この時間四時間にわたる。
日暮れに帰船なし、荷揚げのやかましき夜を明かす。
d19161205十二月五日
この日沼田氏及び仕長司の案内を受けて、前日のヤシの密林に行き写生などをなす。正午過ぎ市に帰り、和蘭陀ホテルに昼飯をなし、沼田氏に別れ、しばらくして台湾銀行に行き支店長江崎氏に夕食の招待を受け、ここに大槻氏の案内にて自動車によりて前日のヤシ林を周遊なし、夕刻江崎氏の家を訪ねて夕食のご馳走を受く。食する者は江崎氏夫婦、堅山君、山崎氏、大槻氏と余なり。
久しぶりにて日本食をなす。
会談時を移し十一時ごろ帰船なす。江崎氏及び外の二氏も船まで送り来たる。この二日間の感は言語に絶するの思い、愉快をきわむ。
d19161206十二月六日
朝六時出航。マラッカ海峡を過ぐ。左右に小島点々として赤土の上に樹木繁り、熱国の島は前年今村君2の画かれし「熱国の巻」を思い出せり。

11月27日(続き)
〜12月6日
(4/85)
d19161207十二月七日波南(ペナン)着3
浪ことのほか穏やか。海峡とて陸地両岸に見え、飛魚点々として飛び、時にサメのごとき大魚などもあらわる。
午後四時波南に着く。小船を見る。小船はことに面白く、波南に上陸。市中の見物に出かけてみる。これまた面白く痛快を覚ゆ。時に降雨の様子に急ぎ船に帰る。夜は船長室において食をなす。日本軍艦明石、新高あり。
d19161208十二月八日
午前六時半出航。浪少しありて気色あまり快を覚えず。午後よりはやや穏やかになり、右は遠山を見る。山また形のよきは支那に見るごとき感あり。
d19161209十二月九日
浪おさまりて、時どき右方に遠山及び島を見る。船員のために絹本に揮毫をなし、尺五、尺八の二枚を画す。夜はトランプなどに時間を忘る。
d19161210十二月十日
早暁に出て日輪の昇るを拝す。その光景美。西を見れば月いまだありて、日月の対照また美なり。午後より筆を持ち尺八絹本一枚を画す。
d19161211十二月十一日蘭貢(ラングーン)着
午前三時、すでに蘭貢に着く。日の出ずるを待ちて港内に入り、旅行券の改め、かつは税関の調べなどに二、三時間を要す。同船の客沼田氏、新嘉坡(シンガポール)三井の中山氏上陸。吾は午後より上陸。船長、事務長、機関長の四人にて岡田氏の店に至れば沼田氏もあり。岡田氏こそ沼田氏の友人、すなわち同氏の懇意なりし。
午前に三井の小川氏より夕食の招待にあずかり、午後の四時を約しあり。その時間まで見物の時間あり。岡田氏、沼田氏の案内によりて、自動車二台をもって一行で市中の見物。公園に至り下車、園中に至る。池あり、小丘あり。この園の様はわが東京の芝浦のごとく、浜離宮公園に同じうして大かつ美。しばらくにしてここを出で、郊外の様子も見たしと帰途道を郊外に進めて一周。時間四時に近きをもって三井支店に至り小川氏に面会す。中山氏すでにありて、この日市中にて求めしという行者の用いるごとき木目漆器の碗などを見せ、一時間余りにして自動車をもって社宅へと向かう。
早や夕刻とて市中、市外の光景もまた美し。日没ごろ小川氏の社宅の家に至る。妻君の出迎えありて社宅に入る。会談二、三時間、この間に月出ず。この家少しく小高きところとて市中を眼下に見てまた快を覚ゆ。しばらくにして食堂に入り、再び露台に至り会談に時をうつし、帰途につく。帰船十一時となる。
d19161212十二月十二日
この日岡田氏の知人インド人ジャマル氏方に茶の招待にあずかり、堅山君、船長、事務長の四人にて午後三時より行くことになる。午前中は共進会に至り見る。ビルマの産物多くあり。一度船に帰り昼食をなし、時間の来るのを待ちて岡田氏も同行とて同氏の店に至る。ジャマル氏すでに出迎えにここにあり。ここより自動車二台にてジャマル氏方に至る。家はさほどに大ならず。しかれども小さき麗なる家にて、ことに前年日本に来遊ありし由にてすこぶる日本趣味にて、装飾物に日本品多く、和田三造氏(*明治、大正、昭和に活躍した洋画家でインド、ビルマで東洋美術を研究した)この地に永くありしとて同氏の油画多くあり。
しばらくにしてここを辞し、帰途シイタコパコダに参拝す。その快感なる、まったく世界の奇跡と言うべし。夕刻とて十分間ぐらいにて去るのやむなきにいたる。再び来るを思い、岡田氏の住宅に至る。一行のために夕食の招待にあずかる。日本婦人、西田師、二人の家医、年長の方など座十人にて夕食をなす。すべて日本食をもってす。新嘉坡(シンガポール)の江崎氏及び小川氏方にても日本食の供応を受く。異国に来たりて日本食は目新しきものと、ことさらに感ず。堅山君と僕とは岡田氏宅に一泊す。

12月7日
〜12月13日(途中)
(5/85)
d19161213十二月十三日ピーク行
岡田氏と店員〇〇(*原文欠)氏を案内者となし、午前六時半発の汽車に乗る。室は二等なれども、わが国の三等よりも不潔にして不快を覚ゆ。
すでに郊外の田畑に出ず。初めて有名なる米の産地、すなわち蘭貢(ラングーン)米の産立地を見る。茫々として美山なく、見渡すかぎり田地ならざるはなく、小鳥種々なるも飛び寄らず。田舎の風物また快を覚ゆ。久しくして水牛のいるを見る。遠くパゴダのあるを見る。樹木の熱国的なる、ビルマ人の風俗や家屋、みな快ならざるはなし。
二時間半にしてピーク駅に着す。町を見物すべく出ず。駅外に牛車の待つあり。面白く思い写生をなすとき、自分の周囲は人垣をつくる。町を進み行けば小川あり。流れに小舟多くある。これまた写生をなす。この辺りに市場あり。しばらくにして帰り、停車場にて昼食をなす。
時にビルマ人のこの町の者、吾々をして自分の家に寄ることをすすめる。この者は先般の案内者にて、すなわち岡田氏方に世話になりしことあり。大方そのためならん、親切になす。言にしたがい同氏の家に至る。ビルマ人の家庭の有り様を見る。家は中等の下、しかれども小金はある人の由。再び馬車にてパゴダに向かう。途中同氏の姉君の家にも寄る。すぐに辞しパゴダに至り参拝す。ここにて小なる花瓶と木彫の仏像とを得る。再びビルマ人の家に至り茶の供応を受く。
時に汽車の中にて余の目の中にゴミの入りしもの、しきりと傷む。親切なるビルマ人、とやかくと心配す。時に妻女の写生を求む。余インク筆をもって写生をなし記念として贈る。同氏の案内をもって仏陀の像を見るべく馬車を進める。一時間ほどにして達す。その大なる、なるほど世界第一なるものと感ず。その辺りすべて古く、樹木ことに仏に縁あるものと思う。久しく見るところの仏画中におけるは、なるほどなるやと。古びたる池あり、竹あり、ヤシ樹あり。ここより十町ほど西に至れば塔あり。塔中に六十二仏像あり。作は上作ならず。すべてビルマ仏像はその作のほどのものなり。
四時の発車にて帰途に就く。その時まで例のビルマ人、親切を尽くす。七時半蘭貢(ラングーン)着。婦人医師によりて眼中のゴミを取り、岡田氏宅に至りて夕食をなし、しばらくにして辞し、店員二人によりてジャンクに乗る。月下に舟を浮かべて気持よし。しかるところ目的の錫蘭(セイロン)丸にあらずして他船なり。時に流れ早くして流中に船を探す。また面白きものにもあらず、ついに一時間を要して船を見出す。
d19161214十二月十四日
午前十時ごろ沼田氏、岡田氏来船す。堅山君と僕はシイタコパゴダを見るべく同氏らに別れ、仕長司の案内にてパゴダに行く。午後三時ごろ岡田氏の店に至る。沼田氏も居りて一時間ほど会談なし船に帰る。出航午後四時半、ついに蘭貢(ラングーン)を去る。
ビルマの風俗は、男子は一見女子のごとく見え、服装、頭などすべて女子に近く、また遊惰の民。女子の服装は、わが国古代すなわち天平時代そのままと言うべし。パゴダにありて仏に礼拝する様、瓶を頭にし肩より天衣様の薄絹を掛け、頭の形、生花を挿して色彩は白の表着に赤青緑などの下巻き、足にはぞうりを履き悠々として歩く様、まったく天平時代をいま現実に見るの感あり。
d19161215十五日
海上浪静かにして緬甸(ビルマ)の遠山見え、午後よりは筆を持ちて絹紙を染む。
d19161216十六日
浪いよいよ静かなり。この日も午後より筆をとる。明十七日こそ多年の望みようやく達するの日となりぬべし。思いこそ深く、今夜の夢こそ楽しけれ。
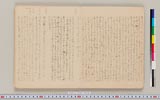
12月13日(続き)
〜12月17日(途中)
(6/85)
d19161217十二月十七日印度(インド)入国
三時というにはや眼をさまし、夜明けには陸地見ゆるとの昨日の話にてや、再び床の中にて夢の人となりぬ。久しくして眼また覚めぬ。起きてみれば日の出前、堅山君4も起きて出ず。ややありて日の出。今日こそ初めて印度の日輪を拝することの忘るべからざる極みにてこそあれ。浪は静かにて油のごとし。右手の水平線に黄土の丘見ゆ、見ゆ、見ゆ。「印度、印度」と思わず口ずさむ。
次第に陸地近づくころは樹木、家屋、牛、舟、人と順々として見ゆ。すなわちすでに川に至りたるなりき。この川はガンジス河の支流にしてフグリー河(*原稿は欠)5と言う。川幅広く、湖水のごとく対岸遠く見ゆ。午前中は前日書き残しの絹紙に揮毫し終わりて荷づくりをなす。
船は進むにしたがい川幅せまく、午後四時半カルカッタ(甲谷陀)に着く。日も間もなく暮れる。ほどなく三井の使いとして、吾々二人を出迎えのため山口茂君来る。同氏に従い船と別れる。馬車によりて三井社宅に入る。支店長の千田氏6、この夜同窓会ありとて不在。ほどなく床に入る。これ印度の一日にこそ。
d19161218十二月十八日
朝早く起き出でて庭園を歩す。園広く樹木茂り、家屋また広し。はなはだ気持よし。九時に朝食終わりぬ。千田氏にも面会なし、堅山君の世話になることどもも頼み、ほどなく千田氏とともに会社に至る。
ほどもなくタゴール氏方よりアンドリウス氏7、余の迎えに来る。見れば顔には長髯あり、一見見まがうべくも覚えたり。氏の余に対する慈悲の心、親のごとき感ありぬ。タゴール氏令息8も來たるあり、自動車によりてタゴール氏宅に行きぬ。出迎える者ゴゴネンドロナト・タゴール氏9、オボニンドロナト・タゴール氏10、第三弟〇〇〇(*原稿欠)氏11、令息妻女、そのほか二、三の方々、余の宝と決めしところを案内す。昼飯をタゴール氏令息、同妻女12、アンドリウス氏老人、タゴール氏の妹君13と共に会食し、深感を思う。
日暮れるときに三井より夕食の招待に会す約束をなし、行くことになる。この日タゴール氏方は皆みな他出。案内者の日本人コック田嶋氏も留守のこととて、その者を待たず三井へ電話をかける。要領を得ずおぼつかないながら、馬車に乗りて三井に向かう。馭者君、三井のあるところを知らず、人に尋ね尋ねて一時間の後ようやく至る。ご馳走にあい、この夜三井に宿る。
d19161219十二月十九日
朝九時半、山口氏と馬車によりて会社に至り正金銀行に行く。支店長○○(*原稿欠)氏に面会。金銭上のことを頼み錫蘭(セイロン)丸に行きぬ。後より山口氏も來たり、荷物取り運びの手続きをなし、再び会社に行きぬ。都合ありて堅山君と二人にてまたまた錫蘭丸に至り、用をすまし一時間ほど町内を歩す。
雑踏の町は夕暮れとて、そのさま筆につくし難し。行けども行けども尽きるを知らず。余の見当が図に当たり、ついに三井の前に出ず。三度三井に行き七時近くまでありぬ。山口氏の世話にて荷物を馬車に乗せ、店員のひとりを付添いとして、道細き町を二台の馬車は走りぬ。三、四十分にしてタゴール氏方に着く。しばらくにしてゴゴネンドロナト・タゴール氏及び令息君来る。食を令息及び妻女十一人にてなす。のち荷の納めをなす。十時床に入る。
d19161220十二月二十日
朝食、例のごとく家族の者となす。のちゴゴネンドロナト・タゴール氏より「来遊あれ」とて来たり、即行く。土産物などを持ちタゴール氏宅に行けば、間のことごとに美術品あり。チベット、ペルシャ、ペルシャ印度、印度仏陀伽耶、種々の美術品、古代絵画によき物あり。しばらくにして帰る。

12月17日(続き)
〜12月21日(途中)
(7/85)
d19161221十二月二十一日ボルプル14
タゴール氏令息に従い、ボルプルに行くべく十二時ごろ家を出ず。ほどなく停車場に至る。余の相乗りの印度人二人あり。言語通ぜず、停車場に余ひとりを置き汽車の中に入る。余は令息を待つべしとのごとく察せられ、そのごとくに待つこと半時間。その心細きこと。ほどなく来たるタゴール氏の令息、これにてやっとひと息つきぬ。半時の後、汽車は走り行く。
田舎の風物は初めてのこととて面白く、タゴール氏令息が停車場にて求めし雑誌を余に見せてくれしも、外の景色見たさにろくろく本を見るを得ず。進むに連れて愉快なること、四時間前後を要しボルプルに至る。
このとき日まったく暮れる。砂漠のごとき広きところ、日没の光景また快なり。牛車によりて村道、すなわち砂の道を揺られゆられてボルプル学校15に至る。点々として家あり。村の若者遊び歩き、煙草をふかすあり、楽器を持ちて遊ぶありて面白し。校内二階に上りて食事をなし、床に入る。
d19161222十二月二十二日
早朝起き出でて見れば、樹木の無数にあり。チャテンマンツリー、あるいはテイク、あるいはバイアンツリー16、様々の樹茂り、その中に学校校舎などあり。すなわち密林学校なり。
この地はタゴール氏の祖々父氏の深き縁(えにし)の物語あり。その当時、この辺り一つの人家もなく広き広き砂原なり。ただ大樹の一株あり。そこに賊ありて旅人を殺害なし、樹の下に埋むとなん。タゴール氏の祖々父氏この下に就床するときに賊來たる。タゴール氏の祖々父氏すなわち説きさとす。賊改心し、もって約をなす。すなわちこの辺りの土人はその子孫なりと。もってタゴール氏の高徳大ならずや。いま学校には生徒二百人を数うと。嗚呼。
この日村人多数つどいて市をなす。芝居あり、様々の娯楽ありて、村々喜々として午後十二時を告ぐ。煙火などもあり。村人は水牛及び牛車に乗りて来たる、ことに面白ききわみにこそ。生も終日写生に務む。この日象に乗りて来たる者を見る。この感また深し。
d19161223十二月二十三日
学校は運動会あり、様々のギャラリーあり、夜は学生の芝居などもありて面白し。「ベニスの剣」などもあり。
d19161224十二月二十四日
早朝より牛車によりて令息、余、コックの田嶋君にて、去ること一里のところの別荘のある村に行きぬ。この地は水池多く、水田もまた多くありて樹木茂り、豊かなる村のごとし。見るもの快。写生などをなして帰る。

12月21日(続き)
〜12月25日(途中)
(8/85)
d19161225十二月二十五日
コックの田嶋君と同道にて近きところの村に向かう。土民の風俗面白く、まったく黒色の人種多く、村にはヒンズーの寺などあり。家の造りも奇。行くほどに小川あり、これを渡りて進む。この辺り風景よし。久しくして右に道をとり、ただ田園の中を横切り村に出ず。
竹林あり、沼あり、菩提樹の大樹あり、数多の樹木茂り愉快を覚ゆ。
久しくにして停車場に至る。時に発車までは三時間を待つという。駅長また種々愚かなる質問をなし、誠にうるさく、ついに歩して帰ることになる。時計を見れば十二時を告ぐ。朝パンに茶を食せしのみ。歩み続け、誠に日中は日射し強く、三里ほどあるところを飲まず食わず炎天下を歩むは少々心細き思いなりしが、行きがかり上あゆまざるを得ず、ついに出発す。所どころ沼あり、その廻りには必ず樹木生ず。その良きにいささか心をなぐさめ、勇を起こして進む。進むほどに村あり。鶏卵を求むれども一個としてなく、身体ようやく疲れはじむ。咽喉は渇し、行くこと久し。
この時すでに道の方向を誤りいたるは後にして知れり。進むほどにいよいよ不明を、村人に尋ね尋ねて前進す。この時午後三時。すでに三時間を要すれども、一向に目的の学校のあるところ少しも知れず、大閉口を感ず。時に砂糖キビ畑ありて、持ち主また畑にあり。田嶋君行きて求む。ただちに二本を得てただちに食す。ここに至りて土人と同じと。はじめ新嘉坡(シンガポール)にて、土人の生のキビを木のまま齧りしを野蛮人なりと笑いしが、いまは天よりの救いの賜物、非常に結構なるものと思いしは、深き深き味のあるところ。
そこを立ち出でて村に入り、また出でて次の村に入る。そこにて村人の案内を得て初めて広き本道、すなわちボルプルに行く道に出ず。これにて一安心。しかれども見渡せしところにては、学校のあるところはさらに見えず。進むこと一里余り、実に疲れ疲れて声また出でず、足は痛んで前に出ず。印度内地の旅行の第一歩、このぐらいのことで閉口いたしてはならぬと勇を出して進む。
時に小川の辺りに出ず。よくよく見れば今朝渡りしところ。嗚呼なんのことかな。考うるに吾々の取りし道は右に右にと取りしため、反対の方向になり8の字形に進みしなり。ここに安心と疲れの一時に出でし思い、このときこそ勇を出すべき時とさらに勇を起こして歩み、午後五時半というにようやく帰り着きぬ。
吾が室に入りしときは疲れさらに十倍し、床の上に横たわりて休むことしばし。のち紅茶、卵などを食して久しく休む。ここに初めて人心地なす。九時ごろ起き出でて夕食をなす。十時床に入る。この日の行程二十五マイル、終日靴にて歩みしは初めて。
d19161226十二月二十六日
朝起き出でてみれば足の疲れさほどにもなく、田嶋君来たりてボルプルの町に行くとのことに、余も行くべく思い、同行す。
町は二マイルほどのところ、行きてみれば田舎にはかなりの町。まったく印度式の家屋にて、初めて見る印度在来の町。非常に面白く写生などをなす。今日は昨日にひき換え、労せずして多く得るところありと。しかし昨日ありて今日あるを知る。決して昨日のことは無駄にてなきを。
d19161227十二月二十七日
午後六時の発車にてボルプルを立つ。三時間余り17にてカルカッタ着。急行とて一時間ほどは早く着きぬ。車中話することも出来ず、ほかの人より話しかけられてもかなわず、はなはだ閉口のもの。痛切に語学の必要を感じたり。
d19161228十二月二十八日
午後より三井の会社に至る。中山氏に会す。社宅に堅山君を訪ね、夕刻に千田、中山、堅山三君と共に自動車によりてタゴール氏宅を訪問なす。
この日ひとり歩して会社まで行き、社宅まで馬車をやとい、初めて独歩をなす。
d19161229十二月二十九日
午後三時ごろより教授をなす。オボニンドロナト・タゴール氏も居れり。タゴール氏令息、令夫人及び三人の男子、都合六人なりし。
d19161230十二月三十日
午後よりボシュ氏18、コール氏19、子供ひとり、令夫人の四人に教授をなす。
d19161231十二月三十一日日曜
日曜日にて休み。日本へ出すべく端書六、七十通を認めて出す。夕刻、梵研究のため留学中の岡教遂氏20来る。しばらくして小林氏訪ね来たり、一日の朝食、雑煮のご馳走をなすと約して帰る。

12月25日(続き)
〜大正6(1917)年1月1日(途中)
(9/85)
d19170101大正六(一九一七)年一月元旦
早暁起き出でて屋上にのぼりて日の出を拝す。やや久しくして小林氏の使い、自動車をもって迎えに来る。すぐに乗り小林氏に会す。時に日本人ひとりあり。大阪の人にして○○(*原稿欠)氏という。三人にて食事をなす。○○(*原稿欠)氏も会す。
ほどなく皆みな馬車を連ねて領事館に至る。すなわち年賀御影礼拝のため十一時を期して一堂に会す。順をもって拝賀す。来会する者十四、五人。帰路三井社宅に至り、しばらく談話す。のち堅山君と博物館21に至り仏像彫刻を見る。非常なる感を得て別れ帰る。
時に「弱法師」の屏風届きおり、すでに立て廻せり。痛快自から覚ゆ。タゴール氏令息、令夫人及びオボニンドロナト氏も来たり、非常に讃嘆す。ことにオボニンドロナト氏の指摘、さすが大家と感ず。オボニンドロナト氏の話二、三時間にわたる。
d19170102一月二日
午後より授業をなす。屏風参観の者多く来る。夕刻オボニンドロナト氏も来る。のち余ひとりにて運動に出かく。町端れまで歩す。
d19170103一月三日
午後より授業を修む。前日よりさらにひとり増し、五人となる。夜分に田嶋コックと運動に出かく。土人町を歩く。実に面白く非常に目新しきところを発見せしと喜ぶ。
d19170104一月四日
午後より授業をなす。さらにひとり来る。この日ゴゴネンドロナト・タゴール氏ベナレスより帰り、屏風を見て非常に喜ぶことかぎりなく、たびたび見に来る。
夕刻、オボニンドロナト・タゴール氏及びご兄弟の方にてヒンズーの寺院に古美術の展覧を見に行く。彫刻にもかなり面白きものあり。織物などにもまたかなりのものありし。絵画に至りてはさほどのものはなき様なりき。電気の消えしため見るに堪えず、残念とこそ思えり。
d19170105一月五日
午後より例の如く授業をなす。四時ごろより岡教遂氏を訪ねる。会談二、三時間にして辞す。帰る途中、三井の社員に会す。
d19170106一月六日
日課は例のごとし。四時ごろより運動に出づ。古風な裏町を諸所廻り歩き、夕刻帰る。留守中に堅山君、三井の社員二、三人と来たると。実に残念至極。

大正6(1917)年1月1日(続き)
〜1月7日(途中)
(10/85)
d19170107一月七日
午前八時半ごろよりオボニンドロナト・タゴール氏及び尊兄の三人にてガンジス河に至り、汽船にてガンジス河を上る。約一時間を要し、両岸樹木茂り、シウバ及びカリ22などの古寺多くありて面白く、写生などをなし、船中にてタゴール氏の肖像を写生す。タゴール氏また余を写生す。いずれも余の写生本の中にあり。感を得て帰る。
午後三時、博物館に行く。タゴール氏の令息と自動車によりて、令息の案内するところなり。堅山君もすでにありて写生をなす。一時間余りにて閉館となり、二人で三井社宅に行く。
八時より領事館に至る。来会者五、六十名。三井、日本郵船、正金銀行、日本綿花その他の人びとにて若き人多く、すぐに食席に座し、両陛下の万歳を三唱し、領事館の万歳なども祝し、来会者諸君の健在も祝せり。ビールを飲み、刺身を食し、寿司を食べ、そのほか数品あり。
ここに書記長吉田信友氏より挨拶あり、日本郵船の小川氏が来会者代表として答辞をなし、席順により姓名及び渡印の年月日を述べることになり、一巡す。しんがりに正金銀行の○○(*原稿欠)氏俗歌を歌いだす。ここにおいて書記長立ちて「諸君に是非かくし芸を一巡することを申し出ず」と言う。しかしてまずもって自分より歌いだす。次は小川氏、次は日蓮宗の岡氏という順にて、思い思いの自慢の歌をだす面白さ。順を経て余も歌う。堅山君も歌う。余は例の「丸くなれ」を出した。堅山君は「追分」を出すという有様。一巡に二時間を要す。
しかして多くのうち三人の選歌者を上げられる。林誰がし、いまひとり誰がし、いまひとりは余なりしは驚きを覚ゆ。しかしてこの三人はいま一度歌うの義務ありて、ついに余も歌うことになり「槍はさびても」を出した。再び高評を博した光栄さよ。自分ながらもおかしくもあり痛快でもあった。
ビールに酔うたる人びと、十時半というにすでに帰路につく。この日さらに愉快なりしは、堅山君と社宅へ戻る際に古道具店にてインド絵画を見て、一枚八ルピーをもって得るところの小画、かなりのものとて殊に楽しみあり。しかして今日こそ朝夕晩の記念とこそ存するものかな。
d19170109一月九日
午後、例のごとく授業をなす。夕刻より市内へ写生に行く。
d19170110一月十日
日課をなす。タゴール氏より小さき箱を頂戴す。夕刻より市内へ写生に行く。
d19170111一月十一日
日課をなす。ゴゴネンドロナト氏より筆を頂戴す。すなわちインド古代様式の竹ペン。午後堅山君を訪ね、石崎光瑤23君に会す。千田氏宅において小会あり。余興に歌うところとなれり。自動車によりて宿に帰りしは十一時半。
d19170112一月十二日
午前、堅山君と約し博物館に行く。写生をなす。堅山、石崎二君も来る。余は日課あるをもって早く帰り、日課を修む。夕刻、二君訪ね来る。
d19170113一月十三日
日課を修む。夕刻より千田氏方に堅山君と伺い、明日の写生行のため宿泊す。
d19170114一月十四日
午前四時半というに早や起き出で、六時の発車に乗るべくありしに、馬車の来たらぬにせっかくの早起きの効もなく、七時発の他方面行きの汽車に乗り、ネーハティという約一時間を要するところで下車。堅山、石崎の両君とボーイひとりの四人連れ。ボーイを停車場に居らせて三人にて終日写生をなす。ガンジス河に小舟を渡して往復す。きわめて快を覚えける。
夕刻帰りて、三井社宅にて夕食をなし帰宅す。
d19170115一月十五日
日課を修す。
d19170116一月十六日
日課を修す。午後九時より三井物産における「天嘉の曲芸」に招かれ、タゴール氏三名及び令夫人三名と共に行く。帰宅一時となる。
d19170117一月十七日
日課休み。三井物産に行き、千田氏に会し用談をなす。
d19170118一月十八日
日課をなす。
d19170119一月十九日
日課をなす。印度の角力(すもう)を見る。チャンピオンというガマという力士、もっともその大なる者。
d19170120一月二十日
日課をなす。
d19170121一月二十一日日曜
午前十時より博物館に仏像の写生に行く。堅山君も来る。四時閉館。二人にてそれより動物園24にいたる。夕刻三井社宅に行き、時に芸人天歌(*天嘉?)の来たるなり。そのほか二人、日本郵船の小川氏も来たり会す。社員の余興もっとも振いたり。余も終わりに歌うこととなれり。この夜ここに一泊す。

大正6(1917)年1月7日(続き)
〜1月21日
(11/85)
d19170122一月二十二日
午前中、博物館にチャンドラ氏を訪ね古画を見る。よき画あり。正午居宅に帰り日課をなす。
夜、下村観山氏書写の屏風を出し、このために日本座敷を造りたるに初めて立て廻す。一族の令夫人、令嬢ら多数来たりて屏風の前に座をなし、ラビンドラナート・タゴール氏25作の歌を一同の者によって歌うを見ること久し。一種の感を覚えけり。
d19170123一月二十三日
日課をなす。午後コブラ使い来たり笛を吹きコブラを出す。時にゴゴネンドロナト氏、余の本に女の写生をなす。かたわらにオボニンドロナト氏もあり、同氏は生の写生をなす。余またゴゴネンドロナト氏を写生す。
夜はボルプルより来たりたる学生の多数の歌うあり。これタゴール氏の宗教、すなわち梵教26なるものの記念日のため來たりたるなり。
d19170124一月二十四日
早暁より音楽の耳に入りて、夢うつつのうちにいつしか眼はさめにき。常より早く床を起き出でて茶を飲みにき。はやすでに朝の式は始まり、令息ロティンドロナト氏8の案内にて式場に入り写生などをなす。式はタゴール氏の長兄27宰師となり、ベタ経典28及び宗の歌などこもごもあり。一、二時間にして式終わる。
午後二時半、一族の者五、六十人一堂に会し(堂は細長きところ)古代式の食事をなす。長たる者にはタゴール氏の令兄○○〇(*原稿欠)氏を初めとし、右にタゴール氏令息、次に生、次にゴゴネンドロナト氏令息というような順。左はゴゴネンドロナト氏。料理は芭蕉の葉の上の中央に米、廻りに種々、そのまた廻りに素焼きの器。日本の古代カワラケ式のものに種々なるものを入れてあり。奇観というべきか。余も右手をもって食す。印度食はすべて右手をもって食するなり。指をもって食する味、善しと覚えたり。上席に置かれたるはまったくタゴール家の厚遇、ひと方ならざるを知る。
食終わりて別堂においてゴゴネンドロナト氏、オボニンドロナト氏そのほか五、六人にて談ず。時どきヒンズーにて音楽をよくする人を召して音楽をなさしむ29。楽器はタンブラと言いて古代式のもの。その歌などまた一種のものありて感ずるところあり。生もまたついに謡曲「羽衣」の一節を謡う。ゴゴネンドロナト氏曰く「ベイダに似たり」と。音楽師にも歌わしむ。わが国仏教の経文読経のごとし。まったく印度古代の音歌の式、わが仏教の読経にまで存すと感多し。
四時半ごろよりはタゴール氏の式に参加する人びと多数来る。五時半ごろにはまったく堂に充満す。その数二千人に近しと。式は朝のごとく二時間にして修む。

1月22日
〜1月24日
(12/85)
d19170125一月二十五日
日課を修む。ゴゴネンドロナト氏、オボニンドロナト氏など来たりて談ず。オボニンドロナト氏の談ひとつの盛りにて、ひとり談ずること二時間。快なること痛快と言うべき。
d19170126一月二十六日
日課例のごとし。夕刻より堂内においてインド古代よりの美術の講義あり。
d19170127一月二十七日プリ―30及びコナーラク行31
午前正金銀行に行きしところ、この日は休み。三井にいたり千田氏宅にて食し、天気のことを話す。旅行用の物品などを買う。
午後八時発の汽車にボシュ氏同道にて乗る。折から月は五、六日目の中天に輝き、四方の景色おぼろに見えにき。そのうち眼をつむりて(*原稿は「眼をむさぶりて」)時過ぎ、眼さめて見ればはや夜明け方、乗り換え停車場のクルタロードにてありき。驚き急ぎ下車。停車場にて茶を飲み、プリー行きに乗る。
d19170128一月二十八日
四方の風景また快を覚ゆ。ことにプリー近くになりていっそう増しにき。赤き花を咲かせたる樹木ことのほかよろし。牛車または女子の風俗など赤、黄ありて、まったくベンゴール州とは相違の感あり。
ほどなくプリ着。車でタゴール氏別邸に入る。ここにはボシュ氏、令弟シュレンドロナト氏32もあり。ひとまず休息をなす。夕刻海辺に歩き、小さき寺などを見る。珍というほどのもの。
d19170129一月二十九日
早暁起き出でて日の出を拝す。その色彩、実に美をきわむ。海岸を南に六、七丁行くほどに、多数の人びと海に入りて日の出を拝す様、また目新しきところにて感を覚ゆ。ボシュ氏の衆人にとりつかれたる様もおかしかりき。
小なる寺じつに多く、いちいち非常に面白く、町も古代の様式の家のみにて、その快いうべからず。小寺には必ず絵画あるいは模様などあり、ことにその画を描く人びとの家屋また多し。その家にはことごとに絵画ありて面白きことまた非常なる感。玩具などにも面白きもの数種あり。いちいち買い求め楽しみとす。
いよいよ有名なるプリーの寺の入口に至る。入口には石柱あり。高さ三丈余り、一個の石にて作りたる古代アイコウのものたる由。門には彫刻非常に多く、女体の像のごとき作も可なり。
町を所どころ見てひとまず帰宿。昼食をなし、午後四時ごろ再び出かけて町を見る。夜に入りて帰宿。闘牛を見た。
d19170130一月三十日
早暁より仕事をなし、プリーの写生に出かけ、正午ごろ帰宿。夕刻また出かける。
d19170131一月三十一日
午前中宿にいる。午後海岸に行く。
d19170201二月一日
午前中町に出かけ、「コナーラク」に行く用意の物品を買い求め、写生もなす。この日出発の都合悪く、牛車の都合にて、二日朝出発のこととなる。
d19170202二月二日
午前八時出発。ボシュ氏、夫人及び子供五人、女中、シュレンドロナト氏、生の一行。馬車三車に乗りて出発す。砂中を行くこととて、その遅さというものは非常なもの。暑さは暑し、閉口のきわみ。午後よりは雲多く出て、ついには雷雨となりぬ。砂漠のごとき所ひとしおの感。
すでにして日まったく暮れぬ。この辺り鹿多く狐も多し。余もこれを見る。ヒョウもいる由。日暮れて一時間ほど行きて民家の一室に宿をとる。すべて土間。周囲も土にて造りたる粗雑なるもの。ついに眠る。
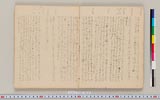
1月25日
〜2月2日
(13/85)
d19170203二月三日
早朝四時に起き出でて牛車の用意などに一時間を要し、出発なす。一時間過ぎには夜はまったく明ける。日の出の光景また美し。右手を見れば虹の立つ。
八時、ついにコナーラク寺に着く。小寺に宿をとり朝食をなし、写生にとりかかる。寺は石造りの彫刻をせざるところはほとんどなく、しかも大寺院なり。周囲の小寺はことごとく崩れ、本寺もよほど崩れる。何年月のちにはこれも崩れるものかなと、嗚呼。この結構なる寺院すでに命尽きにき。美術家の見るべきもののための存在の姿、というような愚感を覚えたり。
寺堂のよほど高きところまで昇ることを得る。まことに美なること、風光また能し。しかし恐ろしさの増し来たりて背に汗をなす。しかれどもせっかくこの難儀を重ねたるを思い、勇を起こして高き所にありて写生三時間。時に強雨あり、ここに雨去るを待つ。
いったん宿に帰り茶を喫し、再び写生をなす。間もなく日暮れ、宿に入り、午後九時に床に入る。室は廻りは土塀にて、出入り口三カ所あり。いずれも戸なく雨は入口より吹き込み、話に聞く猛獣などの出で来ぬかと思案されたり。心中多少気味悪くも思いたり。
d19170204二月四日
時どき降雨。ために暑さなく、写生にはもってこいの日。思うままに写生をなすことを得る。この夜もこの家に宿す。
d19170205二月五日
朝のうち降雨あり。写生をなす。午後四時ごろ帰る用意をなし、急ぎ帰途につく。途中、前に宿りし民家にふたたび宿す。
コナーラク寺は〇〇〇(*原稿欠)と言いてすべて石造りの大建築、アショカ朝ごろのものにて仏教寺なり。今を去るおおよそ一千年前、太洋(*太陽?)を尊像となす。彫刻ことのほか結構をきわむ。
音楽の堂あり。堂はことごとく女神の楽を奏するあり。本堂には男女の交接の像をもってことごとく彫刻せり。実に一驚をなせりというべし。しかも作品については肉体美を遺憾なく発揮し、思いのままの形像を作る。当時の仏教の隆盛、美術家の喜び、思ふべきかな。
二百年前、彼の英国の砲艦をもって砲撃するところとなり、その大半を破れり。遺憾というべし。今日はまったく廃寺となれり。
d19170206二月六日
早暁に起き四方の景色を見る。近くに流れあり。砂漠のごときところ、小岳所々にあり。日の出の光景、美をきわむ。ガリ、すなわち牛車に乗りて帰途につく。午後五時宿に着く(コナーラク)。
d19170207二月七日
午前十時半の汽車にてカルカッタに。帰途四方の風景を見る。夜十一時ごろ床に就く。
d19170208二月八日
午前五時カルカッタ着。午後日課を修む。
d19170209二月九日
午前、三井社宅に行く。堅山君を訪ね、石崎君にも会って三時間談話をなす。辞して帰る。正金銀行にて四百ルピーを引き下げ、三井物産に行く。山口君に会って三百ルピーを堅山君に貸すべく頼む。
d19170210二月十日ボルプル行
日課をなす。午後九時の発車にてタゴール氏令息とボルプルに行く。〇〇〇(*原稿欠)氏も同行する。
d19170211二月十一日
午前三時、ボルプルに着く。馬車にておよそ半道のところ、大いなる家に入る。これマハラジャの家に来たりき。この夜ここに宿り、朝余ひとり町近くのバンガローに行く。午後までタゴール氏を待つ。同道して共進会を見、町を見る。この夜はバンガローに宿る。

2月3日
〜2月11日
(14/85)
d19170212二月十二日
午前十時ごろタゴール氏来たりて同道し、町を見る。写生などをなす。町は古ベンガルの首府にてありき。今は見る影もなき廃墟となりぬ。西にガンジス河を廻らし細長き町にてありき。
この夜共進会に芝居を見に行く。外国人の多数見物する。ラジヤの招待するところとて種々ラジヤ自らもてなす。小生らも特別席にて見る。活動写真、手品、印度芝居、これは下等なるもの。踊り種々。一時半ごろ帰去。
d19170213二月十三日
午前八時半の汽車にて帰る。カルカッタへの途中、赤き花の盛りをなせる樹木多々ありて美麗なりき。
d19170214二月十四日
日課をなし、夕刻三井社宅に堅山君を訪ね、石崎君も在宅。九時過ぎまで話をする。堅山君は神経衰弱の気分にて、きわめて勇気なく、気の毒の感あり。
d19170215二月十五日
日課をなす。堅山君来ると言うによりて待つ。しかるに遂に見えず。
d19170216二月十六日
日課をなす。
d19170217二月十七日
午後堅山、石崎両君来たりて間もなく帰る。この日の夜出発というために、小生も七時半より日本郵船の大谷氏より晩餐に招待せられしが、その途中で堅山君のところへ行き、ハウラ停車場まで送る。この時も堅山君の意気消沈の様、気の毒に限りなし。旅行前は勇気盛んなるものなるに。
小生は直ちに自動車によりて三井の社員二名に送られて、大谷氏宅に至る。来客には三井の千田氏、日本綿花の〇〇(*原稿欠)氏、古川の方二氏、婦人も四名あり。盛んに食いて十二時半というに送られて帰る。
d19170218二月十八日
午前ゴゴネンドロナト、オボニンドロナト、ロティンドロナト・タゴール氏と共に自動車によりて西洋人の家に至る。この人ことのほか美術愛好家にて、種々美術品あり。オボニンドロナト・タゴール氏の絵画も多々あり。一、二時間にして帰宅。ただちに自動車によりて植物園に至る。アショカ樹花いまが盛りにて、まことに美なるもの。終日写生なす。
d19170219二月十九日
日課をなす。
d19170220二月二十日
日課をなす。
d19170221二月二十一日
日課をなす。午後六時より正金銀行の藤木鎮太郎氏に晩餐の招待を受け、古川の二君も同行。キタボー(*?)の瀬良氏方には日本式の座敷ありて、二た月ぶりにて牛鍋のご馳走。すこぶる愉快にてありし。ついに宿泊す。
d19170222二月二十二日
日課をなす。ボシュ氏、アショカの花を持ち來る。美事なる花、非常に喜び写生をなす。
d19170223二月二十三日
日課をなす。ボシュ氏再びアショカの花を持ち來る。ボシュ氏は余の室にて小なる板に画を揮毫す。タゴールの三氏、時に来ること毎日。絹本揮毫の下画を作る。夕刻雨降る。
d19170224二月二十四日
日課をなす。ボシュ氏また花を持ち來る。終日雲多く、夕刻雷雨。少時にて雨晴れる。
d19170225二月二十五日日曜
終日室内にて絵画などをなす。夜に入りて雷雨あり。買物に田嶋君を連れて出かく。帰途雨に会す。人力車などに乗り帰宅十一時。
d19170226二月二十六日
ボシュ氏、コール氏来る。西洋人ミス○○〇(*原稿欠)もタゴール氏宅にしばしの間仮寓。
d19170227二月二十七日
日課をなす。

2月12日
〜2月27日
(15/85)
d19170228二月二十八日
日課をなす。
d19170301三月一日
日課をなす。夕刻ゴゴネンドロナト・タゴール氏と自動車にて外人の家を訪ね、美術品を見る。
d19170302三月二日
日課をなす。絹本の揮毫を励む。
d19170303三月三日
日課休む。
d19170304三月四日日曜
早朝より植物園に行くべく家を出ず。ガンジス河橋際に至りてみれば、乗るべき場所不明。聞くにも聞けず、言語の不自由はほとんど閉口のいたり。やむを得ず電車によりてシブプールの終点まで至る。それより馬車を雇い園内に至る。
園にアショカ樹多々あり。今や花の盛りにて美しきこと言語に絶す。写生をなすによりて園内を見るうちにも、アショカ樹多々あり。持ち来たりし食をなし、所どころを見るときに、のど常になく渇く。水を望むこと非常なり。とある休息所に入りて休む。ここにすでに一団の人びとありて、水を飲み果実を食す。一団中の少年の主人公と思しき、生を見て余にも一瓶及び甘味一つを付与せんとす。すなわち助ける神ありと一礼。これを飲みほし生きたる心地する。
ややありて一団帰り去る。彼の少年去るにおよんでも、また生に話したりする可愛らしさ。年齢十二、三。また感なきをや。
生も久しくしてここを出でて写生などをなす。時に後ろより「ジャパンニス、こんにちは」という声を聞きて見れば、ボルプル学校の彼の合いの子の○○〇(*原稿欠)君でありし。四時半汽船に乗りて帰る。
d19170305三月五日
午前中揮毫をなす。午後五時よりベンガル知事を招待。展覧会をもって迎う。同知事は英本国に帰任のため告別の意を表するため。生の写せし「弱法師」の屏風を中央に、タゴール氏以下の人びとの小品画多く、そのほか新古印度の美術品多くありて、知事を迎うる用意充分せり。
正五時に知事来る。そのほか諸外国人多く来たれり。屏風と向かい合わせに知事椅子に座る。タゴール氏、友人、外国人など歓送の趣意を述べ、次いで絵画を贈り後に巡覧す。知事答辞を述べ、しかして茶となる。生もタゴール氏の紹介するところとなり握手をなす。言語の通ぜざるをいかにせん。辞書をもって常に談ずといえば笑い話だが。タゴール氏の息女二人が二節ほど歌う。しばらくにして帰る。
この日暑し。夜はオボニンドロナト・タゴール氏を中心に音楽に時を過ごす。夜遅くアンドリウス氏来る。一泊をなす。ボシュ氏、シュレンドロナト氏も一泊。
d19170306三月六日
早朝より揮毫。日課を休む。夕刻雷雨ある。
d19170307三月七日
揮毫をなす。午後日課をなす。夕刻アンドリウス氏、オーストリアに出発。
d19170308三月八日
揮毫。この日印度においてヒンズー教徒は「クリシナの赤い祭り」33とて、赤き粉及び赤い水を人びとに頭から振りかくるなり。珍とする、奇というべし。
d19170309三月九日
日課をなす。この日も赤い祭り。この日は召使いの者、赤き粉を振りかけ、音楽をもって日を過ごす。岡教遂氏来たりて談ずること三時間。夕刻二人にてガンジスに行く。
d19170310三月十日
日課をなす。
d19170311三月十一日日曜
博物館に行き写生をなす。閉館後、電車に乗りてカリガートの先の電車の終点まで行く。
d19170312三月十二日
朝より揮毫、午後出来(しゅったい)。この日オボニンドロナト・タゴール氏より、扇子と印度の古物でタゴール氏がラマ法王より貰いしという、赤き糸でチベット人が首に巻く人面の飾り様のものを五個頂戴す。

2月28日
〜3月12日
(16/85)
d19170313三月十三日
揮毫画ロティンドロナト氏に呈す。喜びてビジットラ34堂内に陳列す。
この日ラビンドラナート・タゴール氏25の帰国の日。カルカッタ着午後一時という。家族の人びとと共に出迎えのために行く。一時過ぎ船は着しぬ。船ようやく近づかんとす。遠目にてもタゴール翁の姿はそれと見ゆ。ムクル氏35のごときはしきりとハンケチを振る。出迎えの人びと、学校の生徒ら多くありし。
船はすでに着く。立ちて動かざるタゴール翁は初めて口を開きぬ。曰く「ピアソンは日本にある」だけのことは生にも分明した。すべての態度衆にまさりて、その様高く見えたり。ほかの人びとは、故国に帰りたる嬉しさと下船の騒ぎに自己を失うもの多し。嗚呼、立派なるかなタゴール翁の風采。かつて日本にて見し時と少しも変りなく、上陸後ただちに人びとに取り囲まれて礼をなす。生もまた礼をもってす。「荒井さん、荒井さん」などと特に生の名を言う。感深きものありし。
しかして自動車によりてタゴール氏宅に入る。家族の人びと総出にて迎う。タゴール氏また生に「荒井さん、話は出来るようになりましたか」と英語をもってす。談笑終日、夜も十時ごろまで談ぜられき。
一時ごろ食堂に入る。吾々もそのうちにありて、印度の食事にて多くの人びとと食す。先にムクル氏のために諸氏の遊戯的式をなし、おかしみのもの、ムクル氏なすところを知らざる有様、少し気の毒の感ありき
d19170314三月十四日
午前中堅山君来る。午後よりは多くの人びと来るとのことにて、花などを多く生けて待つ。夕刻より人びと来たり茶会をなす。後にタゴール氏の詩吟するところとなる。その声の美なる、その形の美なる、何においても人より高く出でたる翁の、人びとの感に入り、聞きいる光景は、かつて見る絵画中のもの。写生をなす。オボニンドロナト・タゴール氏も余の写生本に写生をなす。十一時というに夕食をなす。
d19170315三月十五日
午前中、下村観山氏の巻物の陳列あり。午後より堅山君を訪ね、夕方七時よりの日本郵船大谷氏の招待に堅山君、田嶋君と同道。会する者は仁川丸の船長、機関長そのほか六、七人。愉快に談笑をなす。
d19170316三月十六日ボルプル行
タゴール氏ボルプルに行かれることとて、小生もその同伴者のうちに入れり。午後堅山君来る。生は出発前とて長く話も出来ずはなはだ遺憾。二十日夕方の出航にて日本に帰る予定というに、堅山君神経弱くして血色悪く勇気なし。気の毒の感もいたしたり。
午後六時過ぎボルプルに向かう。タゴール氏親子三人、余、そのほか二人にて午後十一時半着。学校の生徒タイマツをもって出迎う。タゴール翁はその中になりて半里以上の道を歩む。学校近傍にはタイマツ多く、特に新道などをつくる。学校前の入口のところにおいて古代の式をなす。その光景また美、ベイダーの賛美などあり。この偉大なる翁を目のあたり迎うる子弟の心組み、翁の感慨を察し、余も感きわまりて涙を覚ゆ。
d19170317三月十七日
午前中シャラ樹の写生をなす。昼食は大食堂において学生、教員をもって充満し、中央がタゴール翁の座するところとなる。生は翁の左側に座して食するの光栄を得たり。古代の式をもってす。昼食は教員の妻女の作るところ。
午後は翁のところにて茶をなし、写生を少しなす。しかして夜となる。樹下にてタゴール翁が旅行談をなす。教員、学生の喜んで聞く様は、往時仏陀の衆生にさとす様もかくやと思いし。ここはカルカッタより暑く、初め来たりしときは一番寒きときなりと。
d19170318三月十八日日曜
午前中写生をなす。夕刻より半里ほどのところへシャラ樹林を見に行く。熱国の夕べ、砂漠のごときところ、夕日の光景は絶美の様をなす。
d19170319三月十九日
午前中写生をなす。日中は非常に暑く、外出はなはだ困難。午後十二時ごろの汽車にて帰る。

3月13日
〜3月20日(途中)
(17/85)
d19170320三月二十日
午前六時ごろ着く。ただちにロティンドロナト・タゴール氏と自動車によりて、バブガンジのシュレンドロナト・タゴール氏の家に岡倉氏来たるとて訪ねる。しかるところまったく着かず。帰路堅山君を訪ねる。しかるに堅山君は木駄ポール(*?)に送別会ありてそのまま宿泊すと。使いを出して呼ぶ。二、三時間待ちて来る。
午後同君と植物園に自動車にて行く。暑く暑く暑く、風は熱して顔を洗う。同君と別れて帰宅。さらに岡倉氏の迎船の着く所に行く。待てどもついに来たらず。
d19170321三月二十一日
午後三時、岡倉氏36錫蘭(*セイロン)丸にて来たる。ロティンドロナト・タゴール氏及びアンドリウス氏と共に出迎う。
この日堅山君帰国の日とて五時ごろ訪ね、途中にて行き合い、自動車に同乗、木駄ポールのドックに乗船を見送る。一度三井社宅へ帰り、諸君と夕食をなし再び船に行く。出航十時、ついに別れる。この日、入る人と出ずる人とにて妙なる感にてありき。
d19170322三月二十二日
午前、岡倉氏を正金銀行に案内す。西巻氏にも会す。午後日課を励む。
d19170323三月二十三日
早朝、タゴール翁ボルプルより来る。日課をなす。
d19170324三月二十四日
日課をなす。チベットに四年間の研究をなし、この度日本に帰られる青木文教師37訪ね来る。二、三時間談ず。タゴール翁に紹介をなす。
d19170325三月二十五日日曜
午前中、錫蘭丸の船長津田氏及び事務長種子島(*原稿「嶋」)氏来る。タゴール翁に紹介を得ざるうち、タゴール翁はボルプルに行く。二氏と共に木駄ポールに行き昼食をなす。岡倉氏も共に来る。
d19170326三月二十六日
日課をなす。午後より青木氏を三井社宅に訪ね、チベットの写真及び絵画などを見る。七時半、日本綿花の青木嘉三郎氏の晩の招待でバブガンジの社宅に行き、十二時ごろ帰宅。
d19170327三月二十七日
日課を休む。急に暑くなり、この日九十九度から百度という。
d19170328三月二十八日
日課をなす。午前、青木文教師再び来る。この日も暑し。
d19170329三月二十九日
日課をなす。
d19170330三月三十日
単衣もの、襦袢を洗濯に出す。台湾銀行の江崎氏及び三井社員三人にて来る。ゴゴネンドロナト氏にも紹介す。この日錫蘭丸の出航に岡倉氏もこの船にて帰国することになり、午後五時より同道す。夕食を木駄ポールの〇〇君の家にてなす。会する者ムクラジ氏及び店員三名、都合六人支那そばに腹をふくらす。
船に至りみれば、いまだ乗船客見えず。船上涼風ありて心地よし。ややありて乗客及び見送りの人びと来る。江崎氏もこの船にて帰るとのこと、青木文教師も同じ。送る人は在甲谷陀(カルカッタ)の人びとを網羅す。十二時ごろまで談じかつ呑む。ついに別れて帰る。
この晩、領事館の書記藤垣長作氏に面会す。氏は余の同県隣郡の芳賀郡中川村の人。生の生地とは六、七里のところ。異郷にありて同郷の人に会す、また懐かしきもの。正金銀行の植栗氏にも会す。この人は上州の人。帰途自動車にて同君の宅まで行く。
d19170331三月三十一日
日課をなす。
d19170401四月一日日曜
午前中、日本綿花の青木氏夫婦及び社員ひとり来たり、ゴゴネンドロナト氏に紹介す。青木氏写真機を持ち来たり、余を画室にて撮影す。またゴゴネンドロナト・タゴール氏及び青木氏夫婦同座にて撮影す。
午後マハラジャ・タゴール氏の別荘に笠原氏を訪ね、庭を見る。
d19170402四月二日
日課をなす。午後雷光あり。雲美なり。
d19170403四月三日
日課をなす。
d19170404四月四日
日課をなす。
d19170405四月五日
日課をなす。
d19170406四月六日
日課をなす。「寿学画集」郵便にて届く。
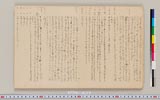
3月20日(続き)
〜4月6日
(18/85)
d19170407四月七日
日課をなす。
d19170408四月八日日曜
日課をなす。
d19170409四月九日
日課をなす。午後三時ごろより外出。岡教遂師を訪ね、談三時間。時に強い雷雨、雹(ヒョウ)など降る。
d19170410四月十日
日課をなす。
d19170411四月十一日
日課をなす。午後五時ごろよりタゴール氏の男四人と活動写真を見に行く。
d19170412四月十二日
日課をなす。夕刻雷雨あり、すこぶる暑し。
d19170413四月十三日
日課をなす。
d19170414四月十四日
日課をなす。この日は印度の旧正月元旦にして、タゴール氏宅においては朝、宗廟の中に多くの人びと来たり読経をなし、のち茶菓を食す。門前には多くの乞食集まりて物を乞う。
d19170415四月十五日日曜
休み。夕刻ボシュ氏来たり、タゴール信氏38と自動車によりて市中を廻る。クリシナの花々39盛りにて、その赤色ことに美麗なり。
ボシュ氏の揮毫の一室で、木板へ描きしもの、アジャンターの写生もありて、それを見る。日本にては門松というところを、芭蕉を入口の両側に立て、上に注連(しめ)というところをマンゴウツリーの葉の間に、小なる赤白などの花を下ぐ。
d19170416四月十六日
休み。
d19170417四月十七日
休み。絹本に「聴法の図」の揮毫に取りかかる。
d19170418四月十八日
揮毫。
d19170419四月十九日
小荷物三個来着。田嶋君の本及び生の本など、高島(*原稿は嶋)屋の高津氏より送り来たれる画集本一冊などありて、楽しむことの出来るもの。
d19170420四月二十日
揮毫を休む。このところ身体の具合よくないため。午後、日本橋西河岸の大倉洋紙店の店員梅津重雄氏、ムカジ氏と共に来る。同氏は視察として岡倉一雄君と同じ錫蘭(セイロン)丸にて熱国方面に来たり、蘭貢(ラングーン)にて岡倉氏と別れ、岡倉氏と入れちがいにて来たる。
夜十時ごろ、タゴール翁がボルプルより来る。
d19170421四月二十一日
日課をなす。
d19170422四月二十二日日曜
日課をなす。ムクル君、生のために印度服すなわちベンガルの着物を持ち来たる。ただちにこれを着す。夕刻この様で大正丸の大石君を訪ねる。多くの人びと生を見る。しかして船に至ってみれば大石君は外出。やむを得ず帰宅。
d19170423四月二十三日
ムクル君同道でガンジス河に至り見る。このとき二十六ルピーほど入りし財布及び手帳を失す。しかしてムクル君の友人の家に至り、のち帰宅。日課をなす。初めて着たる印度服、人をオド(脅)さで物をオト(落)した。
d19170424四月二十四日
日課をなす。
d19170425四月二十五日
日課をなす。この日は少しく暑い。
d19170426四月二十六日
日課をなす。タゴール翁、余に「ジャワに行きませぬか」と言う。40

4月7日
〜4月27日(途中)
(19/85)
d19170427四月二十七日
日課をなす。ボシュ氏並びにシュレンドロナト氏来たりて談ず。スペリト(*当時はやっていた交霊術占い(table-turning))の話となり、テイブルを持ち来たり、四、五人の人びとテイブルの上に手を連ねいること久し。すでにしてスペリト来たり種々話す。初めテイブルを動かす。よりてそのうちのひとり、まず話をする。スペリトこれに答う。英スペリングをもって訳す。最初フジイという。すなわち生の生地「氏家(うじいえ)」なり。美術家と言い、ついに余の父たることになる。それより種々問うところあり。余、在印の善悪を問う。可とす。二年間滞在を可とす。種々談ず。妙なもの、心理作用のしからしむるところと思う。この後日本より手紙はいつ来るやを尋ぬるに、四度テエブル(*テーブル)を動かすなど、妙なり妙なり。
d19170428四月二十八日
日課をなす。午後五時より大石君を木駄ポールの船大正丸に訪ねたるに、船は早や早朝出航。よりて帰途に岡君のもとに遊ぶ。この日英郎及び国江の写真来る。
d19170429四月二十九日日曜
日課を休み揮毫をなす。この日少し熱気ありて気持悪し。
d19170430四月三十日
日課をなす。タゴール翁ボルプルに帰らる。
d19170501五月一日
日課をなす。午前、岡教遂師来る。
d19170502五月二日
日課をなす。ボシュ君夕刻来たり、無憂樹の大輪を余に呈す。
d19170503五月三日
日課をなす。朝より雨降り風ありて樹木の葉ひるがえして、その美しさひとしおなりし。時にオボニンドロナト氏、同氏の邸宅に余を呼び、庭の樹木を見せしむ。
d19170504五月四日
日課をなす。雨終日降り、夜に入りていっそう風強く、また寒さを覚えたり。
d19170505五月五日
雨止みたれどもいまだまったく雲去らず、天を覆いて少しく寒し。午後、日出でず。夕刻ロティンドロナト氏夫婦と同乗し、自動車によりてバルガンジ付近の花を見る。無数の赤きクリシナ、チョラの花咲きて美し。黄、紫、薄紅などの花も咲きおれり。
d19170506五月六日日曜
日課休み。ボシュ・シュレンドロナト氏、ボルプルに行く汽車に乗り後れしとて来る。ムクル君を連れ来たり、久しき間談笑し、後去る。この日満月、夜運動に出かく。
d19170507五月七日
日課休む。午後より外出。三井物産に至り、山口君そのほか三人に会し、日本郵船に行く。大谷氏にも会し、正金銀行の藤木氏にも会す。のちに岡教遂師を訪ね同氏と領事館に至る。しかるところ吉田、茂垣の二氏不在。やむを得ずその辺りを歩き、種々の花を見る。
この辺りは道の両側霊樹をもって並木となす。赤き花、黄なる花、あるいは紫、薄紅など種々あり。夕刻岡氏の住居に至り、ウイスキーそのほか夕食の御馳走になる。十時帰宅す。
d19170508五月八日
日課をなす。買物のため田嶋君を引き連れて出かく。Ms. Lahuaダージリンに行く。
d19170509五月九日
午後より大雷雨となり、二、三時間にして後晴れる。大なる家にただひとり。時に隣家の音楽聞ゆ。

4月27日(続き)
〜5月10日(途中)
(20/85)
d19170510五月十日
早朝ロティンドロナト・タゴール氏、ボルプルより帰る。しかしてダージリン行きは明十一日の午後との話。しかして田嶋君は先発として出発、荷物を持ち行く。この日は読書などに一日を送る。揮毫の画、ロティンドロナト氏に呈す。
夕刻屋上に昇り四方の景色を眺むるところ、西にあたりて黒雲すごく、見る間に東方に向かって飛び来ること急なり。寸時にして強風襲い来るさま恐ろしく、屋上にあるを許さず。すぐに下りて室に至る。しかるところゴゴネンドロナト・タゴール氏余を招く。同家に行き、まさに来たらんとする雨を庭前に見んとす。いなや、たちまち強風雨来たる。室内にありて談余、暫時にして雨去る。しかして光景一変、黒雲をついて日の射すところ、たちまち雲上には大いなる虹あらわれ、しかも二重にして、その美なる色は言語に絶す。
庭の樹木はあくまで緑。高き家屋の正面のみ日光を受け、空は薄黒の色を呈し、青をもあらわし、様ざまな色となり、大いなる虹はあくまでもはっきりとして、初めて見たる印度自然界の色、美とも何とも言いがたし。オボニンドロナト・タゴール氏、余を高き屋上に伴い昇る。四方の展望、山に登りしがごとし。四方ことごとくその趣きを異にし、刻々その色を変じ、実に恍惚たるとはこのときを言うものなるべし。
すでにして虹は去り、夕陽また西山に入る。夕色の雲あくまで様ざまの変化を試み美しさを装う。まったくこの日ほど天然美色の光景に接したることは少なしと、明くる日になりても頭のうちに往来す。
晩十時ごろ、タゴール翁ボルプルより来られる。ボシュ・シュレンドロナト氏も余の隣室に寝る。

5月10日(続き)
〜5月11日(途中)
(21/85)
d19170511五月十一日大雪山、ヒマラヤ山、ダージリン41行
午後四時、いよいよヒマラヤ山、ダージリンに行くこととなる。
ロティンドロナト氏種々多用のため、出発の際に小生を誘うを忘れ、生もまた時間の何時なるかを知らざるため、かくのごとき失策をなす。出発後余の家にタゴール翁来たり、「貴君はダージリンに行かぬのか。すでにロティンドロナトは行きたるに」と。ここにおいてタゴール翁、馬車を命じて余をして行かしむ。途中モーターに乗り換え、急ぎ停車場に至る。幸いにして発車間ぎわとて、まだ一行の人びと室の内外にあり。ロティンドロナト氏も停車場に至り、余のあらぬに心づき、モーターを迎えに宅まで出すなどの騒ぎ。
すでにして列車は動き始めぬ。久しく甲谷陀(カルカッタ)の煙の中、室内にのみ居しこととて、郊外の空気を吸い四方の風光を見たる、本生の感ありき。
四時間ほどにしてガンジスの淵に至る。一、二年前に橋を架くという。長き長き橋。向こう岸のイッショデ(Isurdi)停車場にて夕食をなし、別の汽車に乗り換える。この辺りに多くの地所を有すとロティンドロナト氏の言う。ここより一夜眠りて早朝起きて見れば、大雪山は雲を突いて、しかもよく見ゆ。暫時にしてシリグリ駅42に着く。ここより小なる汽車に乗り換える。今までの人員、客を三分にして、三車おのおの間をとりて進む。途中樹木のだんだんと変化をなし、森林帯となりて、見る間に汽車はジグザグ(*イラストあり)のごとき様にて進む。
山麓は沙羅双樹をもってその大半を占む。実をなしてその色ことに美し。進むほどに展望またよし。この辺りは夜は猛獣の往来する所という。この辺りまったく人種一変、いわゆる蒙古人種にして、すなわちダージリンに古くより住む者多し。
汽車はいよいよ高く昇るにしたがい展望ことによし。汽車は途中たびたび水を飲み、停車場も八ケ所。人家はこれも古代風のもの多く、昇るにしたがって多し。この建築の様は、わが国古代そのままと言ってもよし。屋根は竹を割りて編みたる様のものに千木(ちぎ)をもって押しとなし、多く横板をもって周囲をかこみ、あるいは土を色どるに白とし、下部を赤にて彩色す。人種もいよいよ様ざまとなり、ボタン43、ネパール、チベット、印度、そのほか様ざまの種となす。服装もまたことごとく変化をなし、女は頭より縄をもってみな後ろに下げ荷物を背負う。
樹木もまた杉多く、松も少しはあり。わが国のとは少しく異なる紅葉に似たる木もある。まったく印度に在るの感ありき。温度も日中六十度という。甲谷陀(カルカッタ)にありては百度前後というに、非常なる相違。夜に入りてはストーブに火を焚くなど、かくしてこの夜は感を深くして眠りに就く。

5月11日(続き)
〜5月12日(途中)
(22/85)
d19170512五月十二日
早朝起き出でて見れば白雲多く昇りて、カンチンジャンガ44の峰見えず、ようやくその麓を見るのみ。しかれども様ざまの形をあらわす雲は、あくまで美感を深くせしめぬ。
朝食後、四人にて町に行く。土人の商店及びバザーなどを見る。帰途ミスラージの家を訪ね、帰宅す。午後時どき雨を降らし、すこぶる寒し。夕刻再び外出し、途中雨に会す。雨中を歩き見ること一時間余りにして帰る。しかしてその第一日を送る。
d19170513五月十三日
早暁起き出でて見れども、なお大雪山は見えず。しかれども雲はあくまで美にして飽くを知らず。しかれども霧ただちに起こりて一寸先は見えずという有り様、変化きわまりなし。
午後よりは雨降りて外出もならず。夕刻となりて一時晴れる。四人にて外出、四方の風光を見る。山間の夕まぐれ、その色ことによし。歩くこと一里余りにて帰る。
d19170514五月十四日
早暁起き出でて見れば、見んと欲せし大雪山、見えたり見えたり。高き高き峰は、なお雲の上に高く現れたり。見る間に雲は立ち昇り、まったくその姿を白衣をもって覆いたり。しかして朝食をなし、田嶋君をしたがえて町に出て靴などを買う。諸所を見歩くこと二時間余りにして帰宅。
d19170515五月十五日
早暁起き出でて見れば、カンチンジャガまったくその姿を現し、続いて連山ことごとく見ゆること三十分余り。茶を喫してのち、山と雲との画を小なる掛け物に揮毫なす。
午後五時ごろより運動に出て写生などをなす。
d19170516五月十六日
早朝より運動に出ず。天気ことによし。午後五時より再び運動に出ず。歩くこと二時間。霧一面に白く、少し先は見えず。まったく雲中を歩する二時間となりき。
d19170517五月十七日
早朝より運動に出ず。大雪山は雲下にして、全山ことごとく見ゆ。一時間余りにして帰る。夜田嶋君は何がなし、カルカッタに帰ると主人公に言う。しかして余止むるところとなり、ついに止まる。

5月12日(続き)
〜5月18日(途中)
(23/85)
d19170518五月十八日
午前二時半というに起き出ず。虎ケ岳に行き朝日のカンチェンジュンガを見ることでありしが、人馬の来ることの遅きためついに中止となり、近所の岡に至り朝日を見る。
カンチェンジュンガは朝日を受けて赤金色を呈し、影は紫色をなし、すこぶる美。快絶いわんかたなし。雲は横にたなびきて、古代天平時代の美術家のものせられしごとき様な形をなし、朝日のまさに出でんとするときの光景、美を尽くせりということにてありし。
この朝はタゴール氏妻女、その弟君及びアロックナート・タゴール 氏45にてありし。同君と余は馬に乗りて往復す。余は西洋鞍に乗ること初めてとて、身の中心が誠にとりにくくありしが、何事もなく帰宅なす。午後も五時ごろより再び運動に行く。
d19170519五月十九日
この日ことのほか天気晴朗、春の気候とて気持よし。午後一時ごろより写生に行く。およそ二里ほどのところ、虎ケ岳の麓にて土人町あり。停車場もある。ここより印度原野、河の流れなどを見ることを得る。また首を廻らし反対の方面を見れば、谷深くして見るべきものあり。まったく風俗も面白く、写生五、六図を作す。しかして帰途につく。
すでに夕昏れとて山の色、空の色、すなわち日の入りの光景、色彩の美をきわめ、ダージリンに来たりて初めて見る日色の光景。この日よく半日を歩す。ために靴ずれ(豆)をつくる。足痛を覚ゆ。
久栄のところへ端書を出す。
d19170520五月二十日
朝、奥様の使者と余と外出。ボタン寺に詣ず。夕刻少し歩く。陽の西山に入る頃おい、暮色ことによろし。二日月を見る。
d19170521五月二十一日
天気よし。前日遠くに雪降りて峰白く、ために少しく寒い。午後余ひとり運動に出てボタン寺を写生。それより競馬場を見、丸く廻る道を歩き、四時間余りにして帰る。
d19170522五月二十二日
この日、時どき雷雨あり。夕刻晴れる。運動に出で行く。日入りの頃はことのほか色彩の美をあらわし、ただただ茫然として立ち止まることしばし。
d19170523五月二十三日
天気よし。午後ロティンドロナト氏と古道具屋に行く。ボタン織物一枚買う。オボニンドロナト・タゴール氏及びボシュ氏より絵端書着く。のち雨降る。
d19170524五月二十四日
天気時どき曇る。
d19170525五月二十五日
天気。
d19170526五月二十六日
夕刻運動に出る。ホワイトシャウッタ(*ホワイトシャツか?)を買う。

5月18日(続き)
〜5月26日
(24/85)
d19170527五月二十七日
終日霧深し。時どき雨降る。
d19170528五月二十八日
天気にして前日の雨天に引き換えて気持よし。午後運動に出ず。夕刻タゴール翁のお出であり。しばらくの間ご滞在のことならん。
d19170529五月二十九日
午後よりゴムという次の停車場のあるところまで歩む。時に降雨少しあり。一方は日照り、すなわち山間の気候をよくあらわせり。この町をそこここと歩き見る。岡を廻らして人家あり、ことに面白し。夕刻帰宅。この日タゴール翁は他の家へ住まうこととなりて家にあらず。
d19170530五月三十日
夕刻、小高き岡に昇り夕色を眺む。夕陽は雲に映じ、その光は雪山の表を金色ならしむ。光景はまた絶美なり。天上高く半月すでに輝く。月影を踏んで帰宅。
d19170531五月三十一日
午後運動に出かく。印度絵画二枚買う。あまり良き画にはなく、価(あたい)きわめて低きためこれを求む。夕色また佳。
d19170601六月一日
天気よし。時どき霧来る。一日絵端書などを認む。夕刻外出。例のごとく夕色よし。
d19170602六月二日
一日中霧深し。この日も絵端書などを認む。日本より久栄の手紙及び二、三通来る。英郎及び喜代子、芳枝46などの手紙、ことのほか楽し。
夕刻外出。夜、タゴール翁を訪問す。帰宅後もカードなどを取り、一時となる。
d19170603六月三日日曜
午後より外出。道にてチベット人で先に青木師に使えし者に会す。彼の者いわく「日本領事館にいる」、すなわち領事館の秘書に転じたるを知り、彼に案内させて領事館に至る。吉田氏に会し快談に時をうつす。のち同氏を同道し町に出ず。この山間遠地にわが国人に会す。また楽しきものにこそ。
d19170604六月四日
午後より外出。植物園に至り、のち茶園の道を行き村落などもある。村はことに面白く、写生などをなす。夕刻帰宅。

5月27日
〜6月5日(途中)
(25/85)
d19170605六月五日
巻物の下図に着手。午後吉田氏訪ね来る。のち同道し外出、散歩をなす。帰途吉田氏宅に至り日本酒をご馳走になる。この遠地の高山にてウニ(雲丹)にて日本酒を得るは珍事の珍にて、格別のものなりし。
d19170606六月六日
午前中絵端書をかき、午後より外出。ボテヤバッス方面の下方に行き、歩むこと二時間余りで帰宅。夜はカルタの遊びに時を過ごす。この日、巻物の下図も揮毫。
d19170607六月七日
午前中巻物の下図を揮毫。午後より植物園から茶園を過ぎ、前に行きしところまで行く。夕刻帰宅。机上に書翰あり。これ岡教遂師来るとの書状なり。客のまた増すことにてぞ。雨は夜に入りて強し。
d19170608六月八日
午後外出。吉田氏を訪問し快談に時を転ず。久栄のところに書状出す。
d19170609六月九日
岡教遂師、午後一時着という。よりて停車場まで吉田氏と行く。待つこと二十分余り。時に英役人、余らを「どこへ行くや」と尋ね、吉田氏答えて「岡氏来たるを迎える」と。役人岡氏の宿所などをも聞き手帳に控える。程なく汽車は着きぬ。二度目の汽車にて着きし。
吉田氏宅に至り夕刻まで談ず。帰宅しみれば家には点火もなく、ただひとりも居らぬ。別員の人びと来たるとて出て行きし。
d19170610六月十日日曜
朝、岡氏訪ね来る。のち二人にて外出。一度帰宅。午後より吉田氏のところへ行く。岡君と三人にてバザーに行き、古道具屋を見てチベット古画を買い求む。その年代は不明なれども五百年ぐらいはあるべきものと。名品にあらずともかなりのもの。価(あたい)は六ルピー。まずまず安価というべし。
それより植物園の脇を通り、茶園の中道をそこここと遊び行く。夕刻帰宅。吉田氏宅にて三人車座の胡坐(あぐら)となり、久しぶりのすき焼きに日本酒、おつなウニに舌打ち鳴らし、九時半ごろ帰宅す。
d19170611六月十一日
午後より岡氏来る。二人にてボテヤバッスの寺に至る。住職に会し、その付近を見る。夕刻帰宅。三井の山口氏より電報あり。「伊藤氏ほか一名登山ある、明日停車場まで出て待っていてくれ」とのこと。夜吉田氏宅に至る。土人の花を見る。すべてにおいて日本のものに似ている。
d19170612六月十二日
午後一時着の汽車にて、三井の伊藤氏及び金剛丸の汽船長及び事務長の三人来る。余出迎えに行き、それよりマントべレスホテルに至り、のち案内者となりて所々を引き廻す。夕刻帰宅。雨多し。
d19170613六月十三日
午後より伊藤氏及び船長などをマントべレスホテルに訪ね、それより四人にて古道具屋を見て歩き、夕刻帰館。夕食のご馳走になり、快談に時をうつし、十二時ごろとなる。ホテルの者みな寝に就き、ために諸君と一緒に宿す。
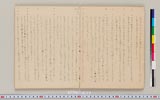
6月5日(続き)
〜6月14日(途中)
(26/85)
d19170614六月十四日
九時半にタゴール翁に会すべく大雨をおかして至る。暫時会談して辞し、また諸氏とも別れる。午後二時発の汽車にて三人とも帰る。停車場まで送る。
帰途吉田氏方に寄り、岡氏の室にて談ず。のち三人にて運動に出る。幸い降雨なし。
d19170615六月十五日
午後より領事館に至り、記念の撮影をなす。吉田氏、岡氏、余の三人。
それより岡氏を同道し、ボンの先のギン村のグンバリー47、すなわち寺に行く。この道は山をよほど下るものにして、いささか帰る時が思われる。道にて巡公に寺を尋ねる。その巡公先生、余らの後をつき来たりて種々話などをなす。時にこの村に日本婦人の外人の妻女としてあるをかねて岡氏の知るところ、ついにその話の出て、巡公の曰く「案内をなす」と言う。
程なくその家の前に至れば、彼女の姿らしきものすでに見ゆ。年ごろ五十ぐらいにして野羊をもて遊びいたり。岡氏声を発して「あなたは、おとよ様になきや」と。ついに話し込み、その家の中に休み、暫時にして寺に行くこととなり、おとよばあも行くと言う。またまた山を登りて行く。この辺りの眺めまた可なり。
廻り廻り土人の妙な村を過ぎて寺に至る。寺僧二、三あり。参拝ののち岡氏は写真、余は写生などをなし帰途につく。道に巡公に別れ、雨また降り来たる。おとよばあは頻りに「家に寄れ」とすすむ。しかれども夕暮れ近く、雨は降る。ついに別れて帰る。行く時とは相違して、どこまでも坂道とて難儀である。
日入りの頃にボテヤバッスの寺付近に来る。時に寺にての音楽はまた一段の感ありき。夜分はパースなどを取る。時にタゴール翁も一、二度その仲間に入るも座興なりし。
d19170616六月十六日
午後運動に出ず。青木師の例の娘に道にて会す(*六月二十六日の項に「青木師の縁あるソナというブテヤの娘」の記述あり)。絵巻にとりかかる。雨なし。夕刻、山少し雲間に見ゆ。
d19170617六月十七日日曜
午後二時、タゴール翁甲谷陀(カルカッタ)に帰る。停車場に送る。時に三井物産の社員ひとり及び尼崎紡績社員というがひとり、同じ汽車にて帰る。これより吉田、岡の二氏とバザーなどを見歩く。夕刻帰宅。
d19170618六月十八日
午前、山見ゆ。山の写生に出かけ、帰宅すれば岡氏来たるあり。午後岡、吉田の二氏と共に、ボテヤバッスの寺に何かの式のあるを見に行く。なんとも奇妙なものにてありし。夕刻帰る。夜、吉田氏宅に至る。ネパールの花というを見る。早咲きのものなりし。
d19170619六月十九日
絵巻物に着手。夕刻岡、吉田氏来る。談、快を覚ゆ。
d19170620六月二十日
絵巻物揮毫。午後岡氏、テニスをなさんと来る。よりて紹介をなす。程なく雨降り来たりて茶となる。対談音楽のことになり、デブ氏(*?)の音楽家なるをもって、ついに種々の音楽をなす。同氏の後に余も日本の歌などを歌い、すこぶる快なりし。
d19170621六月二十一日
揮毫。終日雨降る。夕刻吉田氏宅に至る。例の三人にて長談す。
d19170622六月二十二日
揮毫。午後ちょっと雨止む。外出、商店などを廻り歩きて帰宅。揮毫をなす。夜、領事館の吉田氏を訪ねる。ネパールの花にて日本の鬼アザミのごときものを見る。珍花もっとも多し。久しきにして辞し帰る。

6月14日(続き)
〜6月23日(途中)
(27/85)
d19170623六月二十三日
終日雨。午後五時ごろより領事館に至る。晩をご馳走になるを約し、三十分ほど三人にて外出。この日雨上りて、その夕景、雲の美なる色彩、また一段とよし。
帰館後、ウイスキーに缶詰肉とキノコと野菜を煮たウドンの打ち立てを食う(これはチベット人の小使いの作りしもの)。その美味なること近来の美食。ボタンフキムのウドンという。誠によし。
d19170624六月二十四日日曜
午後天気となる。領事館に出かけ、三人にて外出。バザーなどを見歩き、帰館後再び外出。途中にて別れる。
d19170625六月二十五日
午後より天気となる。明日出発、甲谷陀(カルカッタ)に帰るという。よりて筆を止めて外出、写生に行く。帰途吉田氏宅に寄り、二氏も拙宅に来たりて留守とて帰り来たりしところと言う。ついに話し込み、夕食までご馳走となる。辞し帰る。
d19170626六月二十六日出発、甲谷陀(カルカッタ)に帰る
この日出発。甲谷陀(カルカッタ)に帰らんとて早朝より荷造りなどをなし、午前十時に昼食をなし、生は諸氏より先に家を出て領事館に至り談ず。午後二時発車。そのためその近くの時まで話し、二人の見送りを受けて停車場に至る。(領事館には青木師の縁あるソナというブテヤの娘来たりあり。写生などをなす)。
間もなく発車。途中の風光また可にして、来たる時は雨少なくなりしため、滝などはほとんどなしと言いてもよし。しかるにこの度は至るところ滝、大中小無数にありて見るべきものありき。山麓のシリグリ辺りの近くに来たるときは早や日暮れて、機関車にはタイマツを付けて進む。そのわけはこの辺りは猛獣多く、時には象なども出ることありて、汽車の進行を止むることさえあるとの由。二つには道を照らすためなど。
程なくシリグリ着。ここにて汽車を乗り換える。後より来る汽車に故障ありて、一時間余り遅れて出発。車中にて夕食をなし、程なく眠りにつく。眼をさまし見れば、はや夜は明けにけり。
d19170627六月二十七日
寒いところに一と月半、まったく暑いということを忘れたる身には、シリグリ付近に来たる時はまったく暑く、家の人も印度人はみな素体となりて家の外にあり、盛暑のよう。嗚呼、吾もまたその仲間入りかなと。進行中はさほどになくとも、止まるときは実に暑い。夜明けてはいっそう暑さの増すならんと思ひしにさほどにもなく、雲をもって天をおおい、時どき降雨ありて時には照る。
正午ごろ甲谷陀(カルカッタ)着。家に着きひと息つきぬ。ボシュ氏及びムクル氏も来たりて談ず。ゴゴネンドロナト氏、オボニンドロナト氏の家に至りて談ず。夕刻タゴール翁のところに多くの人びと来る。夜、ガゴネンドラ氏来る。
d19170628六月二十八日
朝、オボニンドロナト氏来る。ダージリンの写生をご覧に入れる。夕刻領事館の茂垣氏を訪ねて同道。カフェイに至り、ウィスキーをもって酔うて帰る。(久栄に書状を出す)。
d19170629六月二十九日
ボシュ氏来たる。唐紙書をなす。
d19170630六月三十日
絵巻物の揮毫に着手。午後、三井物産に千田氏を訪ねる。帰途公園を歩く。
d19170701七月一日日曜
絵巻物を揮毫。夕刻千田氏、大槻氏、山口氏及びボンベイの人というが来たりて談ず。タゴール翁にも紹介す。二日夜に千田氏宅に招待の約をなす。

6月23日(続き)
〜7月1日
(28/85)
d19170702七月二日
揮毫をなす。タゴール氏奥様も絹本に着手。ボシュ氏も来たりて唐紙書をなす。夕刻三井社宅に至り夕食をご馳走になる。大槻氏の写生なども見る。赤花とじた(*?)悪しきものをも見る。
d19170703七月三日
揮毫。大雪山の絵巻の終尾をなす。ロティンドロナト・タゴール氏に呈する巻物。終日雨降る。
この夜はタゴール翁を始めゴゴネンドロナト氏、オボニンドロナト氏そのほか四、五人の人と、生の写生やゴゴネンドロナト氏の写生などを見、また生の巻物なども見、下村(*観山)氏の巻物なども見、種々談話ありて九時ごろとなる。夕食をなし安眠をなす。ゴゴネンドロナト氏よりヒマラヤ山の写生(余の気に入りしもの)を頂戴するところとなる。
d19170704七月四日
ボシュ氏、オシツ氏48来る。オボニンドロナト氏、余のために小品画一葉を贈らる。二日に二枚の画を収得するところとなる。のちオボニンドロナト氏、ボシュ氏、オシツ氏と共に、ムクル氏の父親の死亡を見舞いのため出かける。
今晩一時より二時にかけて月食あるという。午前一時半に起床。屋上に昇りて見れども月見えず。
d19170705七月五日
早朝五時に起床。ガンジス河に至りてみる。この日は非常なる人びとの水浴、日輪を拝す。道は広きなれども人出多く、ために歩行困難を覚える次第。道の側には苦行者あり。頭を地に着け逆立ちとなるあり、あるいは数千の釘の上に横臥するあり、静座するあり。様ざまの行者及び乞食の頭数(あたまかず)を知らず。
ガンジス河には男女の水中に入りて日を拝する。水は非常なる泥水なるに、皆みな口に含みて平然たり。女子の体格を見るには、これもよく見るを得る。薄き白衣を、水に入るとてほとんど素体のごとし。乳は胸高に大きく、腰部は後方に出て、かつまた大。腹部は小なるを良しとなす。肉体美はわが国女子の及ばざるところなり。しかして老幼男女、ただ神を信ずるのみ。その信仰の力の大なるには、いささか驚かざるを得ず。写生十点をなす。
帰宅後、ほどなく岡氏来る。タゴール翁にも会す。このとき多くの人びと来たり、(*下村)観山氏の巻物を人びとに見せ、翁その説明をなす。岡氏もその席にて見る。午後にもボシュ氏及びオシツ氏来る。この日、家の召使い一家の者コレラなりとて避病院に連れて行かれる。はなはだよき気持のせぬもの。
d19170706七月六日
前日の召使いはコレラにあらざる由を聞く。これにていささか安心を得た。ボシュ、オシツの両氏及びムクル氏も来る。
午後五時より約束の領事館茂垣氏に招待を受け、夕食のご馳走になり、ウイスキーの酔いにて皆みな歌うところとなり、歌を尽して帰る。時に十二時、電車皆無。自動車をもって帰宅。

7月2日
〜7月6日
(29/85)
d19170707七月七日
タゴール翁はボルプルに行かれた。オシツ氏来る。奥様、信さんなどに教授をなす。この日は非常に蒸し暑く、近ごろになき苦しさであった。オボニンドロナト氏より絵を一葉頂戴した。面白いものである。
d19170708七月八日日曜
ボシュ氏来る。前日より暑く、夜は度たび目を覚ます。その暑苦しきこと、この日も同じ。午後より雨来る。少しは楽。夕刻雨あがる。またまた蒸し暑いのである。オボニンドロナト氏の子息オロク氏夫婦来たり夕食を共にす。その妻君の美人なる、実に美感を覚えたり。
d19170709七月九日
ボシュ氏、オシツ氏、ムクル氏来る。時どき大雨あり。
d19170710七月十日
ボシュ、オボニンドロナトの両氏来る。時どき雨降る。オボニンドロナト氏より、氏及び弟子君の絵画の本を頂戴す。
d19170711七月十一日
ムクル、ハルダル氏来る。午後よりゴゴネンドロナト氏と自動車によりて商店に至り、マイダンを一廻りなす。その気持のよさ、すべて緑色にして雨雲また可。この日も暑苦しきこと殊のほかと言うべし。
d19170712七月十二日
ムクル、オシツの二氏来る。日課をなす。
d19170713七月十三日
オシツ氏来る。日課をなす。午後三時より信さん、ガバさんの三人にてフットボールを見に行く。マイダンの原に見物の人びと非常に多く、ベンガル人と英人との競争。西日に面して陣取れる我々は非常に暑く、待つこと二時間近くにして始む。一勝一敗、手に汗をにぎるということ。六時ごろ終わり、英三勝に印二勝という点でありし。夜、タゴール翁帰らる。
d19170714七月十四日
オシツ、ムクルの二氏来る。夜九時よりロティンドロナト氏、オロク氏と共に印度人の芝居を見に行く。場内小にして暑きこと非常なるもの。クリシナによる演劇にして女優二、三人あり。一女優のダンス、これも見事にして感を得る。写生数葉を作る。
d19170715七月十五日日曜
午後岡氏を訪ね、同道して三井社宅に大槻氏を訪ねる。時に千田氏も来たりて笠松氏にも会す。談数刻にして帰り、帰途領事館の吉田氏を訪ねる。この日吉田氏はダージリンより帰りたるものにして、暑さに驚いていた。
これより吉田氏夫婦を岡氏の招待するところとて、支那料理屋に行く。万歳商会の駒岡氏夫婦と余の六人。ウイスキーに酔いてよく食す。十時ごろ別れて帰る。
d19170716七月十六日
田嶋君暇をとり、この日タゴール氏宅を出ずる。夕刻ボシュ、ムクル両氏と共にボシュ氏の新宅に行く。
d19170717七月十七日
早朝木村龍寛氏、タゴール翁を訪ねるために来る。余も会す。
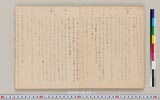
7月7日
〜7月18日(途中)
(30/85)
d19170718七月十八日
午前信氏と自動車によりてボシュ氏宅を訪ねる。午後ボシュ、ムクル氏来る。夕刻よりベンガルの村芝居を催す。多くの人びと来る。妻女も多く来たれり。芝居はブランマーによるものの由。九時半ごろ散会す。
d19170719七月十九日
日本より書状七、八通来る。久栄よりも来る。タゴール翁は旅行された。大正丸船の大石君より奈良漬が届いた。夕刻大石君来る。夕食をなさんと木駄ポールに行き二、三時間にして帰る。
d19170720七月二十日
日課。ムクル氏、オシツ氏来る。時どき降雨あり。
d19170721七月二十一日
日課をなす。
d19170722七月二十二日日曜
午後、三井の笠松氏及び大槻氏来る。岡教遂師も来たりて久しく談ず。笠松、大槻氏帰る。岡氏あとに残り、領事館の吉田氏の家へ行く。うどんのご馳走に時間をおくり、のち帰宅。
d19170723七月二十三日
ボシュ氏、ムクル氏来る。日課をなす。夕刻大正丸の大石氏及び機関長共に来たり、夕食を共になさんと木駄ポール街に行く。九時ごろ帰宅。この日少し熱気ありて気持悪し。
d19170724七月二十四日
夕刻、ボシュ氏とオボニンドロナト氏宅に行く。時にオボニンドロナト・タゴール氏所感を述ぶ。
自分は今までの風にて(画についての)通す。初め洋画を学びしため、七、八分までは洋風にて二、三分だけが印度風である。ボシュ君なぞは印度風であるから、将来大いに成し得てもらいたいと。しかして自分やボシュ君が、今の世において寺の前に立ち、花を手に持ち来たる人びとにその花をあげるのである。印度の美術は堂の奥にあるというところへ導くのであると。今のインドの画は弱いと。心に強味があれば、考えもおのずからよい考えが出来ると解す。
自分はかつてモスリ49という遊場、大雪山の麓を非常に愛する。同時にダージリンはつまらぬと。多くの色が時どき変わり、目の前は山また山でさわがしいと。それに引き換えモスリは一日一色、時になお別色の色を呈す。朝早く小鳥の鳴くはさながら音楽。こちらの峰より向こうの峰に飛びちがう。しかして朝日出ずるにおいて、ようやく止まる。一色の雲山、その中に雪山の壮大なるは実に愛すべきものである。敬すべきものである。静にして大、無色にして色あり。雪山の大きさを初めて知ると。しかしてその後に描きしは、日本へ来たりし時の鳥の画であると。自分は若い時は多くの画を揮毫したが、今は歳老いて元のごとくならずと。印度は他国と相違して暑い国で早く歳をとる。他国ではいまだ盛りの歳であるのにと嘆息をなす。
のち辞して家に帰る。夜分熱気なおあり。

7月18日(続き)
〜7月24日
(31/85)
d19170725七月二十五日
朝ちょっと起き出したがなお熱ありて、ついに床の中に入りて後は苦しむ。午後ロティンドロナト氏やほかの人びと見舞いに來たり、医師を迎える。薬を飲みて伏す。タゴール翁も心配なして見舞いに預かる。
d19170726七月二十六日
熱なお去らず、医師来る。クイナイン(*キニーネのことか?)を飲む。タゴール翁はじめ家内の人びと、オボニンドロナト氏兄弟の人びとも来る。
d19170727七月二十七日
熱よほど低くなる。
d19170728七月二十八日
熱は確と常に復すといえども、この二十七、八日の両夜は眠ることを得ず。起きいてもこの頃の雨期、汗の出ずるに閉口するに、熱の床には汗泉のごとく、その苦しきこと言わん方がなく。
d19170729七月二十九日日曜
熱なしといえども、疲れにて身体苦しきかぎり。
d19170730七月三十日
快方。
d19170731七月三十一日
快方。
d19170801八月一日
快方。この日床を起き出ず。
d19170802八月二日
ますます快方。これまでタゴール翁、毎日のごとく見舞い言いしは、深く感謝す。
d19170803八月三日
ますます快方。大槻君及び三井の社員杉山君、日本へ帰るという。二人訪ね来る。
d19170804八月四日
夜タゴール翁、ほかにおいて演説をなす50。この日の演説はよほど強味のもののごとく、家を出ずる前の決心の様を推することを。自ら言うポリース等の拉致するべくならんと。暫くにして帰り来る。何事もなきもののごとし。
d19170805八月五日日曜
ますます快方。
d19170806八月六日
全快は変わらず。時どき降雨。
d19170807八月七日
大槻氏甲谷陀(カルカッタ)に出発というため、夕刻三井社宅まで訪ねたるに、大槻氏は六日夜すでに出発なしたる由。山口君としばし談話をなし、のち帰宅。
d19170808八月八日
d19170809八月九日
d19170810八月十日
d19170811八月十一日
d19170812八月十二日
タゴール翁、再度の演説を六時よりなすと言う。生も見に行くことになりおりしに、この日の朝気分悪しく寒さを覚ゆ。ついに午後より床に臥す。熱高し。再度の熱にかかりしなり。その苦しきこと、言語に絶するの思い。
タゴール翁、演説無事に済み帰宅。医師を同道、余の室に至る。
d19170813八月十三日
なお苦し。服薬をなす。医師来る。

7月25日
〜8月13日
(32/85)
d19170814八月十四日
d19170815八月十五日
熱ようやく引くといえども、時どき少しの熱出ず。
d19170816八月十六日
薬すべてクイナイン(*キニーネ?)。二度まで皮下にクイナインを注射す。
d19170817八月十七日
快方。
d19170818八月十八日
快方といえども前回より重く、六、七日間、夜まったく眠ることを得ず。
d19170819八月十九日
d19170820八月二十日
起き出ず。
d19170821八月二十一日
起き出ず。
d19170822八月二十二日
起き出ず。
d19170823八月二十三日
朝、温湯にて身体を洗う。気持よし。食堂にて諸氏と常のごとく食す。
d19170824八月二十四日
尺八来る。オボニンドロナト・タゴール氏に進呈す。同氏非常に嬉んだ。この夜、同氏のインド絵画の演説あり。
d19170825八月二十五日
d19170826八月二十六日
d19170827八月二十七日
d19170828八月二十八日ランチー行51
午後ムクル君と馬車にて横浜正金銀行に行き、藤木氏に会し、なおあと百ルピーを引き出す。それより日本郵船に行き、大谷氏に会す。同氏は五、六日後に出発し日本に行くという。帰途吉田氏に会す。三井の◯◯(*原稿欠)氏にも会す。同氏はこの日出発、日本に向かう由。
生も午後九時半というに出発。ホシーツ、ムクル氏停車場まで送り来る。月下を走る汽車は余に美なる光景を与う。同室に二人連れのランチー行きの甲谷陀(カルカッタ)の人あり。ほかにひとり同乗。この者挙動風体、嫌な気のする男。ために眠ることを得ず。その男、三時半ごろ下車す。
d19170829八月二十九日
六時にポロリア(*プルリア?)という停車場に至り、乗り換わるのである。茶を喫し一時間の後に発車なす。この辺りの眺望風俗、殊に面白し。黒人種にして非アーリアンなり。小岳は諸所に見え、すべて緑にして美なることダージリン行以来の感。山すなわちランチーの山近きに見ゆる辺り殊によし。山にかかりては無憂樹そのほかが繁茂し、また見るべきものありき。
午前十一時近きにランチ着。停車場にはシュレンドロナト・タゴール氏の母堂及び息君52出迎え、自動車にておよそ一里ほどのところの家に着きぬ。ジョッテンドラ(ジョティリンドロナト)・タゴール氏53来たるに会す。同氏はロティンドロナト・タゴール氏の令兄にして美術家の由。肖像画によし。同令兄のショテンドラ・タゴール氏にも会す。
余の住居の家は小岳のところにして眺望に富み、ショテンドラ氏の家とジョティリンドロナト氏の家の中間に位置する家にて、余ひとり住む。隣りには◯◯◯(*原文欠)氏とて住む。

8月14日
〜8月29日
(33/85)
d19170830八月三十日
ジョティリンドロナト・タゴール氏、余の肖像を写生す。氏は肖像画に上手なり。しかしてのちマハラジャ54◯◯◯(*原稿欠)の家に行く。同氏余を写真に撮る。同氏は蒙古種による日本人に似たる顔。洋式水彩画を描く。新式水彩の描き方とて、余の前にて一枚の小なる画を描く。最初水を塗り、のち彩色をなす。水の乾かざるうちに描きあぐる方法なり。面白き人なりき。
夕刻は村人稲の生い立ちを祝う三日間の祭りとて、若き男女数かず歌い、かつ踊る。しかして村中を踊り歩き、日中より夜遅くまでなす。この日の夕刻タゴール氏も庭に来たり、盛んなる踊りありき。例のマハラジャも来たりて見る。写生十数枚を作る。村人は非アーリアンにて肉色黒く、唇出て厚し。その踊りはわが国の盆踊りに似たるもの。面白きほどにこそ。
d19170831八月三十一日
午前、ジョティリンドロナト・タゴール氏を写生なす。夜は強き雨降る。
d19170901九月一日
午前、ショッテンドロナト氏の肖像を写生す。ジョティリンドロナト氏、同氏の写生本に再び余をして写生なす。余もまた余の本に同氏をして写生なす。夕色よし。満月にして夜色またよし。
d19170902九月二日日曜
午前、子供二人に絵を教える。正午より両タゴール氏と自動車によりて、オシツ君の父君宅に昼食の招待を受けて行く。後ほどほかの家に行きて帰る。四時間を要す。この日少し風邪の気味。この地は雨来るときは急に冷え、夜また冷える。
d19170903九月三日
午前、ショッテンドロナト・タゴール氏を写生、ジョティリンドロナト氏の本になす。午後絵端書を認む。時どき降雨あり。
d19170904九月四日
午前、再度ショッテンドロナト氏の写生をなす。ランチーの学校の絵画教師という者来たり、氏の本に氏の肖像を写生す。夕色絶美、青赤白と様ざまの色彩、まったくわが国にては見られざる感ありき。
d19170905九月五日
絵端書六、七枚を認め、カルカッタの人に送る。
d19170906九月六日
絵端書なぞを認む。久栄のところへ書状出す。

8月30日
〜9月6日
(34/85)
d19170907九月七日
雨風時どき強く来たりて外出もならず。終日室内にありて絵端書や読書によれり。この日は少し寒し。
d19170908九月八日
午前雨音し、時どき午後も降る。夕刻あがり、運動に行く。気持よし。
d19170909九月九日
朝、子供らに絵を教える。少しの雨、時どき降る。夕刻あがる。例のごとく空は雲の美観を呈す。
d19170910九月十日
天気よし。夕刻の色彩は実に驚くほどの美観を呈し、かつて見たるうちの、その最たるものにてありき。見る間に変化の様をあらわし、日すでに入りても、なお様ざまの色と化す。初めて接するこの美観、言語に絶す。
d19170911九月十一日
雲はあれども天気上々、朝まことに気持よし。「国華」にアジャンター行承諾の「I Accept your offer」の電報を発す。この価は金二十ルピー十三花55。午後雷雨あり。この日凹孫兄56よりの書翰あり。
d19170912九月十二日
写生及び絵端書などを認む。ボシュ氏父子より絵端書来る。面白きもの。ムクル君の弟君、シュレンドロナト・タゴール氏の子息と学友の由にて、学校よりの帰途来る。午後雷雨あり、夕刻止む。運動一時間、長き歩行はこれをもって初めとなす。
d19170913九月十三日
日中天気。夕刻ショッテンドロナト・タゴール氏の同伴をなしランチ倶楽部に行く。二、三重に立ちたる人に紹介せらる。同倶楽部は印度人のみ。多くの人びと余を見ることはなはだし。少しきまりが悪いくらいである。もっとも出で立ちは紗の黒紋付、しかもその紋は通常より大。彼ら多くの紳士は日本人を知らぬはなけれど、余のごとき紋付という服装を見るのは初めてならん。あるいは羽織を手にておさえ、誠によろしいものであると言う。車立ちに余の周囲を取り巻き、種々話をしかけられ少々閉口の気味。さりとて半ばは話がわかり、見向きもされぬよりは面白いもの。
素人芝居がある。よきほどに始まる。劇はマホメダン57のものにて、老翁に二人の娘あり。二人の若者その娘をと○○〇(*原稿欠)をなす。互いに許しあう。初め若者二人老翁の家に来たり、翁を侮辱なす。後にその娘を得んとするにあたり翁怒る。娘を得ること困難となる。その間に種々ありて、ついに老翁の許すところとなる、という筋なり。要するに総じて半分は○○〇(*原稿欠)味である。先に甲谷陀(カルカッタ)にてパーシー58の劇を見しことありき。クリシナによるものなりき。同様に○○〇(*原稿欠)味多かりき。余は言語不明といえども、その様子にてほぼ知ることを得る。しんみりとしたところに乏し。遊惰の気分ありと感ず。
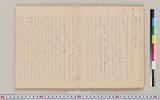
9月7日
〜9月13日
(35/85)
d19170914九月十四日
早朝、いやあまり早くもない六時半に余を起こす者あり。おぼえず眠き眼をこすりあけ戸を開けて見れば二人ありて、ひとりは先の日來たる学校の図画の教員たる画家、なおひとりはムクル君母堂の弟と言う。ただただしばし談ず。時に教員の余の肖像を写すと言う。そのモデルに立ちつつありけるところに、またまたムクル君の伯父君及び青年二人来たれり。この二人は学生にて絵を描く。話しばらくにして帰る。次の日曜、余より訪問することを約す。
この日雨なしといえども付近は雷雨あり。夕色よし。
d19170915九月十五日
天気よしといえども、時どき少しの降雨あり。夕刻外人老婦人二人、タゴール氏奥様の同道し余のところに寄る。余の写生を見んため故に写生を見す。嬉んで見る。後日再び来たりて見んと言う。ひとりは多少描くよし。
d19170916九月十六日日曜
午前中ランチの青年来たり絵を習う。午後夕立雨あり。
d19170917九月十七日
時どき降雨多し。沢村君59より書翰来る。日本へ二、三通、甲谷陀(カルカッタ)の諸氏に端書を出す。
d19170918九月十八日
時どき降雨ことに多し。このごろの日の入りは六時半。
d19170919九月十九日
早朝より降雨。ことに猛雨終日。久栄より書翰、及び寺内氏、大橋氏60、ムクル君、野生司君61より一通来る。甲谷陀(カルカッタ)の諸氏に端書を送る。
d19170920九月二十日
雨なし。運動を充分になすことを得る。吉田氏、茂垣氏、そのほか一通の端書来る。夕刻英婦人二人来る。写生を見せる。
夕色に添えるに三日月をもってす。その色彩の美感を受けること、また大なりし。
d19170921九月二十一日
タゴール氏子息ショビ、女ジヤ児62に絵を呈す。この日運動をよくなすを得る。
d19170922九月二十二日
午後三時よりランチーの町に行き、マケツ(*マーケットか?)市を見る。非常の人出。その人込みの中に入れる生は眼を回すほどの様にして、もの目新しく見る。人びとも生を見ること目新しそうである。多くの人びとが見る、見る、よく見る。多く野菜もの、そのほか種々なるものあり。余は布を四枚とコール婦女の装飾画集を買う。町端れの家は面白いもの多々あり。

9月14日
〜9月23日(途中)
(36/85)
d19170923九月二十三日日曜
午前中、タゴール氏奥様同道で英紳士の家を訪問す。帰途ムクル君伯父の家に至る。かねての約定とて昼食のご馳走にあずかり、かなり美味を得る。英スタイルの画家も来たり、同氏の家に行き多くの画を見る。多くの少年の付きまとうには少々閉口した次第。ヒンズー僧の○○〇(*原稿欠)という高僧に会し写生をなす。夕刻帰宅。夜は音楽師二人来たりてヒンズー歌をうたう。
この日はすこぶる変化のありし日なりき。初め華やかな英紳士の家に行き、しかも婦人のもてなし。次は印度の中以下の家庭に半日を送り、その家の多くの少年や、また変わるがわる外の人びとの余を見に来るの奇観を呈し、終わりに高僧に会し、夜は音楽に時を移す。
d19170924九月二十四日
天気よし。岡氏よりの返事によれば、錫蘭(セイロン)丸は二十七日ごろという。よりて余は二十六日に当所出発と決定す。健康も恢復し、愉快々々。63
d19170925九月二十五日
一ケ月の滞在ほとんど雨。この間に写生を作ること五、六十図にして、風俗面白く、まったくエジプトの古代絵画を見るの感あり。また夕色の絶美なる、感深くせしこと大なりき。
d19170926九月二十六日出発
午後三時半の発車にて出発。停車場までミセス・タゴール、子供二人、軍人一名にて自動車をもって送らる。途中雨多し。下山の頃すでに夕色絶美の様を呈せり。先の日、蘭智(ランチー)において絶美の色を見る。この日再びそれを見るを得た。
雨後の夕景、印度の空、まったく日本にて見ることの出来ぬもの。深く深く感を受得することを得たるは有難きことにこそ。八時少し過ぎにポロリ市にて乗り換え、午前六時半ごろカルカッタ(甲谷陀)に着く。
d19170927九月二十七日甲谷陀(カルカッタ)着
電話をもって錫蘭(セイロン)丸着を聞き合わせる。二十八日着と。午後五時ごろより岡師を訪ね、旅行のことにつきて相談す。夜、タゴール翁及び青年の者あまた論議ありて、十一時過ぎまで続く。夕食この話をもってなし、ほどなく床に就く。
南京虫の小なるもの数多く来たりて余を悩ますこと甚だし。半夜眠ることを得ず。しかして十数匹を得取る。
d19170928九月二十八日
早朝より岡氏を訪ね、バザーにて旅行具を種々買い求む。昼食を岡氏のところにてご馳走になり、夕刻まで談話後同道美術得羅(*ビチットラ?)に帰る。
五時よりタゴール翁作の芝居を催す。ゴゴネンドロナト氏三人の兄弟、及びムクル氏、オシツ氏そのほか二、三の人びとによりてなす。来客は男子のみにて二日前には女子のみの芝居ありし由、小生は見ず。面白かりき。
d19170929九月二十九日
朝、旅行具をとり揃えなどなす。夕刻より運動約三時間、天気よし。天気恢復しつつあり、時には降雨ありといえども夕立的なり。この日の暑さ、まことに暑きことでありし。
d19170930九月三十日日曜
タゴール翁の頼みによりて、能楽堂の図を作る。

9月23日(続き)
〜9月30日
(37/85)
d19171001十月一日
朝、正金銀行に行き千ルピーを引き出す。これはこのたびの大旅行費用としてのもの。日本郵船に行き錫蘭丸の来るを聞き合わす。午後三時と言う。一度帰宅し再び船着き場まで出向く。野生司君来る。氏大いに嬉ぶ。船長の津田君のところで夜まで話し込み、ご馳走になり、諸氏と共に運動に出で、野生司君と共に帰宅。同君をして余の床に余と伏す。
d19171002十月二日
野生司君と同道。船に行き、船長、事務長の四人、馬車にて郵船会社に行き、それより領事館に至る。再び船に行き昼食をご馳走になる。のち野生司君と旅行用具を買う。
夜別れて岡氏のところへ行き、準備を相談、辞し帰る。八時ごろ船に至りしに、はや野生司君は出かけたる後、急ぎ停車場に至りてみれば、岡氏も来たりあり。待つこと久し。野生司君ついに来たらず。よりて帰る。
d19171003十月三日
午前中日本郵船の永井夫婦、子供の三人で来る。タゴール翁及びそのほかの人びとに紹介をなす。夕刻船に至り野生司君の所在を尋ねるに、二日夜に一汽車早く出発せしと。
d19171004十月四日
早くより波浦(ハオラ)停車場64に行く。アネバサント65という印度における革命家の英国老婦人(*イラストあり)、その歳七十七歳という、文章及び演説ともに英語たり、よく印度のために説く。たまたま英官の捕するところとなるも、その獄にあること一ケ年。このごろ放免されてアッラーハーバード66に行く途中で市に寄る。非常の人出にて大歓迎をなす。のちタゴール翁方に来る。余も面会なすを得たり。
夕刻ボシュ君、信君と活動写真を見る。岡君より八日に出発なすを端書にて申し来たる。
d19171005十月五日
終日雨天。午前、岡師を訪ね旅行についての打ち合わせをなす。予定を二日延期す。午後オシツ氏と警察署に行きパスポートを願う。帰途四、五点旅行具を買う。
d19171006十月六日
終日降雨、もっとも多し。朝、林君訪ね来る。日本へ行って来ると。

10月1日
〜10月6日
(38/85)
d19171007十月七日
(*この項の記述はなく、ここからノートは第二冊目の「大正六年十月八日」となる)
d19171008大正六年十月八日出発 岡教遂君、荒井寛方の二人道中
午前十時半の汽車にて出発。朝、岡君のところにて野生司君に会い、同氏は都合ありて帰る。この日は前日の大雨に引き替えて天気よし。涼しきこと十一月ごろの気候。
いたるところ雨後とて出水多く、水の上を行くごとし。夕色美麗。しかして汽車は二等、三等の中間のもの(インター)に乗り、その価(あたい)はなはだ安し。
d19171009十月九日プリー着
午前三時半ごろカルダロー駅にて二時間近く停車。七時にプリーに着す。馬車使い及び多くの土人来たり、うるさきこと話しにならず、実に閉口。これが閉口の第一番。米を買わせて朝食の用意をなす。米の色の黒きこと、この地の人種と同じ。やがて飯ができ雑炊のごとし。空腹の吾がためには結構至極。
ほどなく町に行きジャガナート寺院に至る。門守の入るを許さず。岡君数言争うところとなる。ついに入るを得ずして帰る。
d19171010十月十日
午前八時というにプリーの宿所を出発す。牛車に乗りたる二人は、車上に伏しあるいは起き、風涼しくはなはだ気持よし。途中ちょっと猛雨あり。広き砂原を車はきし(*軋)りて、その遅きことはなはだし。
午後六時、ニヤキヤというところにて河あり。水増して渡るを得ず、車上に宿することとなる。食事も我々二人にて作り食す。しかして牛車の内に伏す。

10月7日
〜10月10日
(39/85)
d19171011十月十一日
午前五時に起き出でて出発の用意をなす。一時間の後、古代式の丸木舟に乗りコナーラクまでは約二里を徒歩にて行く。途中水溜り多くして困難をきわむ。コナーラクにては写真二葉を撮影なし、写生も数葉なす。
すぐに帰途に就く。途中の熱暑を「何の」と勇気をだし、牛車のところへ来たりし時はまったく疲れ、牛車に入りて休む。
岡君は勇気ありて、すぐに飯を作りなどする。しかして宿に着したる時は午前一時ごろなりし。余はこれにてプリー、コナーラクは再度の見物である。
d19171012十月十二日
プリーはジャガナート寺院の今なお盛んなる印度教の本山とて参詣人も多く、そのほかに小寺が二百寺もある。町は古風にてことに画家の家が軒を並べ、壁には面白き画を描き、吾らの喜びを満足させる。
コナーラクはプリーより二十哩(マイル)と言い、はなはだ不便なところにて牛車によりて行く。今を去る一千年前後の古寺院にて、すべて石建築、彫刻をもってこれを飾る。その本尊は大日輪を安置せしもの。彫刻の大部分は交接の図にして、別に音楽堂あり。彫刻はことごとく音楽なり。本堂は馬車の大日輪を引くの形をとりたる意なり。向かって右に大象二つあり、左には軍馬二つあり。
d19171013十月十三日
午前九寺半の汽車にてプリーを出発し、十一時半ごろブボネシュワル67に着く。牛車によりてカンダギリ及びウダヤギリに行く。行程三哩、道もっともよし。
一時(いっとき)余りにして着く。小山にして大石をうがちて造りたる、すなわち窟寺院。アショカ王朝の建造にして、彫刻をほどこせり。これも佳作なり。写生及び写真を撮る。カンダギリ、ウダヤギリとも道を挟みて十数窟ずつあり、のちにジャイナ教の支配するところとなり彫刻を加えり。その彫刻にも見るべきもの多々あり。
帰途ブボネシュワル寺院の隣りに至る。案内者の悪強(わるじ)いにより怪しき家に連れて行かれ、食を強いられる。日は早や暮れ、見るも物凄き土人が黒山となりて無理強いに食をすすむ。岡氏も少し食するにより余もまた少しとり、しかして二ルピーを乞われる。明朝来ると約して、ようやくにして逃がる。道にてまたガリ68の藁、牛を取り替えるとて久しく待たせしむ。吾々は歩む覚悟で馬子を呼ぶ。ついに来たりて停車場に至る。
駅長に会い種々談話の後にバンガローに案内せられ、ここにて明朝四時のマドラス行きを待ち合わす。この駅長は親切の人なり。
d19171014十月十四日
ブボネシュワル駅を午前四時発の列車に乗る。四方の風望よし。進むに連れて海が近くに見え、小山も多く山脈をなせり。古時玄奘三蔵法師はこの道を通りしよし。風俗、家屋など異なれり。人種は非アーリアン種の猛気あり。景色はなはだよし。午後十二時ベーズワタ駅に着きバンガローに宿す。
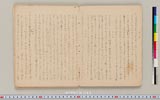
10月11日
〜10月14日
(40/85)
d19171015十月十五日
西に去ること二哩(マイル)半に小岳あり。古時玄奘三蔵法師の訪ねられたる仏教窟寺院あり。大乗仏教を起こしたりし当時、もっとも盛んなる起教派なりき。大小三窟あり、彫刻あり。壁画ありしも今はなし。少しその名残りあり。大なる涅槃像あり。これも古き寺なりき。
ことにこの地の風景、絶美をきわむ。大河横たわり、小岳四方に突き出たり。古時をしのぶに余りある。感深し。寺は〇〇〇(*原稿欠)寺院と号す。日中の暑きこと、我が国の熱暑の時よりも強し。
d19171016十月十六日
午前五時、乗り合い自動車により九哩ほどのところにて下車。半道にして渡船場に至る。言語通ぜず、ようやくヒンズスタル69を解する者ありて渡り、二哩ほど行きてある村に着く。
ここは多くの村人ありて牛乳の供養を受く。目的のアマラバテ70までには七哩あると言う。身体疲れて、はなはだ落胆する。しばらく休みて勇気を出し、苦力(クーリー)ひとりを雇い、炎天のもと道なき畑の中を、西へ西へと進む。
およそ五哩ほど行きしところに小岳あり。この辺りならんと苦力に尋ぬれども、言語不明のためほとんど要領を得ず。村人に尋ねるに、山を廻りてさらに行くなりと。身体はなはだ疲れ、さらに勇を起こして進む。小河を渡りおよそ二哩(マイル)ほど行く。
村あり、アマラバテと言う。我々がアマラバテを目指すのは、古時仏教の盛んなりし頃、大乗仏教の起因を成せりという古所なればなり。今は英政府の発掘するところとなりて、何ものも存せずという。生らはついにその目的地を見いだすことを得ず遺憾至極。
この辺りの家屋また面白し。一つの小なる堂を写生なす。ヒンズー寺院の大なるものもあり。ここより渡船もあるに夕刻とて出でず。ついに舟の上に寝ることとなる。時折り雨なぞ来たり、印度旅行の感、またかくしてこそ味のあるところ。
d19171017十月十七日
早暁に舟人数人来たりて起こす。「この舟は河上の方に行く。十二時ごろに渡舟をなす」と。よりて余らはその時を待つことになり、町に出て米そのほかを買い、河岸にて煮る。余はこの時はなはだ疲れていて、いかんともなすを得ず。前日朝食にパンを少々とミルクを飲みしのみにて、終日歩して舟に至る。その疲れにて非常なる思いありき。飯を食しミルクを飲み、ようやくにして勇気をだす。
しばらく休み、舟に乗りて対岸に着きしは四時ごろ。それより自動車のあるところまで四哩ほど急行し、ようやく二十分ほど前に着きて乗るを得た。

10月15日
〜10月18日(途中)
(41/85)
d19171018十月十八日
朝、町を見物す。靴などを買い、家(*宿)に帰り昼食をなし、午後三時半ごろの汽車にて出発す。この汽車はマドラスメールにあらずして途中までである。十二時下車。停車場の待合いに寝る。金五十ルピーを岡君に渡す。
d19171019十月十九日マドラス
午前六時乗車、同十一時ごろマドラス着。すぐに馬車に乗りてヒンズーのホテルに宿をとり、午後に市中を見物す。女子の風俗カルカッタとは少しく相違し、主に色彩をほどこしたるもの、黄八丈のごときもの多し。男はウリシッシャと同じく、日本の徳川時代の武士のごとく前頭を剃り毛を後ろに結ぶ。眼色たくましくして勇気あり。
この日雨多くして、印度における熱地と聞きしが、いたって冷える。
d19171020十月二十日
雨をおかして博物館に至り、阿摩羅波提仏寺院の石彫を写生なす。石は白大理石及び青大理石を用いてすこぶる見事なるもの。古時盛んなるを思い、うたた感を深うす。そのほかに印度教の石彫多々あり。
d19171021十月二十一日
午前博物館に至り写生をなす。いったん宿に帰りて茶を飲み、再び外出し市中見物をなす。日本人の家を訪ね、茶を馳走になる。帰途天平式靴を買う。価三ルピー。建築は古風にして、すこぶる面白き壁画を装飾せり。家も多くあり。
d19171022十月二十二日
午前中は市中見物。博物館に至り写生をなし、午後七時十五分の発車にて錫蘭(セイロン)島の古倫母(コロンボ)に向かう。停車場にて英官吏の吾々を調べるところとなる。
d19171023十月二十三日
正午マズラに着く。再び英官吏の調べるところあり。午後五時ごろ、いよいよ印度最南端に出でしより一時間、そののち船に乗り換えるのである。医師の健康診断ありて、のちに乗換船に至りまた取り調べを受け、ようやくにして船に乗り、一時間半ののちに汽車に乗り換えて進む。
d19171024十月二十四日古倫母(コロンボ)
午前七時、古倫母に着く。ただちに日本人臼井清造氏71宅を訪ねてそこに宿することを頼み、茶を喫し、臼井氏の案内にてダルマパー氏商店に行き昼食の馳走を受け、土人の案内を同氏宅より受けて博物館に至り、館長に会し写生をなす。彫刻また見るべきものあり。シリギリ寺院72の古壁画の模写あり。余はこれを写生なす。
帰途マリガカンダ、ビッチャーカーシ大学のナネシッシャウ僧正に会し、夕刻宿に帰り湯を使う。余は印度に来て初めて入浴をなす。日本食のご馳走を受け、臼井氏の柔道を見て、のち快談に時を転じ、十二時ごろ床に入る。

10月18日(続き)
〜10月24日
(42/85)
d19171025十月二十五日
午前検疫所に至り、帰途井上(画家)氏を訪ね、いったん宿に戻り、午後博物館に至り写生をなす。夜井上氏来る。
d19171026十月二十六日
午前検疫所に行き、午後より博物館に至り写生をなす。錫蘭(セイロン)古代の旗模様の本を買う。夕刻仏寺院にてナネシッシャウ僧正に会し肖像の写生をなす。内松商店の井上利正氏の招きに夕食を受く。同君の浪花節は堂に入りしもの、大いに快を得る。
d19171027十月二十七日
この日は休息をなし、手紙などを認む。朝より井上君訪ね来る。絵を揮毫なし、臼井氏及び内松氏、南条氏などに呈す。井上君は一日談じ込む。
d19171028十月二十八日日曜 コロンボ出発 カンディ73
午前七時十五分の発車にて出発す。五氏も停車場まで送り来る。途中の風望ことによし。進むにしたがい山の中腹を行く。十一時半カンディに着く。避暑地とて西洋風の町は家屋、道路いたれり尽くせり。すぐに馬車にて仏窟寺に至る。停車場より二丁余りにして寺に達す。
周回一里ぐらいの湖水に面し、四方は山をもって廻らし、樹木繁茂し涼風至り、鳥鳴き花咲き、霊気自ずから来る。真にこれ尊き仏窟を奉安なすべきの地、絶好の霊地。極楽の天地とはかくのごとき所ならんと感ず。天には白雲往来す。天人雲上にありて音楽を奏す。木々は黄赤白の花を置き、人民快楽の思いあり。嗚呼これ真に仏霊地、合掌。
我らは寺に詣で、宿を頼みて休息す。夜は仏堂の霊天のうち、親しく拝すること有難く有難く。五十ルピーを岡氏に渡す。
d19171029十月二十九日
午前、博物館にて写生などをなす。また郵便局に行き、午後はこの地の高僧に会う。夜は満月の拝経に多くの信徒ら来たりてまことに盛んなり。十時ごろより説教あり。余らも十二時ごろまで拝しいる。説教は終夜に渡れり。信徒は手に手に生花をささげ仏前に献ず。

10月25日
〜10月30日(途中)
(43/85)
d19171030十月三十日
午後より近所の寺を参詣せんと、先に一マイルほどのガンガーラー74寺院に行く。道は馬車の通ずるよき道。ほどなく達して写生をなす。木造にして壁を多く用いる。内部は至るところ画をもって彩色す。それより更に一マイルほどの所にデカルドルワ窟寺あり。途中に河ありて景色よく、日本の山川とは少し異なりたるの感あり。
まったく危うき舟に乗る。川向こうに大象に人の乗りて来たるを見て、山辺氏の朝日新聞の旅行記にありしはこれならんと思いしに、ほかにまた大象の小象を連れて来たるに会す。河より半マイルほどで窟寺に達す。仏陀の涅槃像を安置す。岩を彫り抜きし大なる御像なり。およそ三百年前、この地の王の建立するところという。室内の壁は小さき絵をもってなせり。像もその当時のもので面白きものなり。
寺僧は英語をよくし岡氏とよく話す。同僧もカンディに行くとて連れだちて帰る。道ぎわは植物繁茂して気持よし。暑きこともなく旅行にもっともよき時節。

10月30日(続き)
〜10月31日(途中)
(44/85)
d19171031十月三十一日
午前七時発の汽車にて、二十分ほどにして二つ目の停車場に着く。苦力(クーリー)をひとり雇い、約二哩(マイル)ほどにしてガダラーデニア寺院に着く。寺は岩上の小高きところにありて、ことに建築の面白きこと余らをして嬉ばしむ。写生などをなす。院内は釈尊御身長一丈五尺ぐらいの座禅の極彩色。壁はことごとく絵をもってせり。中に金像の釈尊立像二尺五寸ぐらいの上々の作、結構なるものにこそ。展望もっともよし。
それより二哩ほどにしてランカー寺院に達す。岩石の小高き上に、ちょっと日本の城のごとき形に種々なる工夫をこらしたる面白き建築にて、院内はガダラーデニアと同じく釈尊の座像。二丈近き御像の上には天人菩薩の半肉彫に極彩色をほどこし、壁画も院内ことごとく色彩をなしあり。客坊にて昼飯のご馳走にあずかり腹をふくらせり。
なおそれより二哩ほどにしてテラシブッカク寺に至り、茶を受け、衣を色付ける樹木などを見、かつ小花を得る。本堂は五十年前に建築せしものにして、まったく城のごとき形なり。
この所より三哩(マイル)ほどにしてペラデニヤ停車場に至り、五時半の汽車にてカンディ駅に着く。この地は至るところ樹木繁茂して繚乱なり。歩行もっとも安し。一日の回参は九哩。寺はことごとく眺望絶佳のところ。〇〇〇はことに清々たり。(*判読困難)
宿所に帰りて、夕食のあと参拝をなし、鍍金(めっき)金仏の小なる物を持ち来たるを一ルピー半にて買い求む。かくして一日の参拝をもって十月の月を修めたることこそ、有難く有難く。
d19171101十一月一日
三人僧の肖像を絹に認(したた)めて呈す。ある商人の家を訪ね、茶をご馳走になり数珠を頂戴す。午後はちょっと町に出て、なお休息す。
d19171102十一月二日出発、アヌラダプール
午前七時発の汽車にて出発。二時間ほどにして乗り換え駅に達し、ここにて乗り換え。午後一時にアヌラダプール駅に着く。すぐに牛車にて半哩ほどにしてルダコバ(*判読困難)寺院に着く。主僧に会し宿を受けて、そこに滞在いたすことになる。一室を得て、以来休息をなし、夕食の雑炊を二人にてなし、十時ごろ床に入る。
d19171103十一月三日
朝食を作り、九時ごろより案内者を連れて近所の寺院を参拝なす。寺は程ほどのところに高き古塔あり。アバヤギリ塔と言う。もっとも古きものの由。それより三丁ほどにして菩提樹に至る。菩提樹は初め紀元前三世紀の中葉に、この国の帝須王(チツサ王)に請ぜられて、阿育王の子摩哂陀(マヒンダ)が来教して大東日教団を建てたと言う。王妃アヌラは婦人の教団の建立を企望しマヒンダに請うた。彼は「婦人を得度させることは出来ぬ。妹に僧伽密多(サンガミッタ)と言う者あり」と。ついに妹を招来せしめ、そのとき仏陀伽耶の菩提樹を移し植えしという樹なり。それより僧伽密多は錫蘭(セイロン)の婦人に大法の恵みを浴せしという。今の樹は若樹にして何代目かの若芽ならん。
参拝をなし、それより五、六丁にしてクスルムート寺院に至る。岩窟寺にして、マヒンタラ王の住せしという古き寺なり。後ろに大なる湖水あり。周囲は大樹繁茂し、南の七、八哩(マイル)にマヒンタラ山を見て眺望よし。往時盛んなりしを偲ばしむ。寺僧の長老八十歳余という。ユイナートの水を馳走せられ、暫時休息をなし、昼食をすまし、帰途町に出て靴を直し、宿に帰る。

10月31日(続き)
〜11月4日(途中)
(45/85)
d19171104十一月四日マヒンテル山行、アヌラダ75より東八哩
午前八時に牛車を雇い、男をひとり連れて出かく。道路一本の通りのよき道。両側は非常なるジャングルという隙間のない雑木が一帯に繁茂し、八哩(マイル)の里数を三時間にしてマヒンテル山に着く。
山麓の村にて村民に昼食を供養せられ、そこより一丁ほどにして石段に着き七、八丁を登る。二千年前マヒンタ僧正の住せし最も古き仏所なり。古塔は多く山上にあり、マヒンタのスツーパあり。至るところ殿舎の跡や柱石散在し、往時を偲(しの)び教えるに充分の材料あり。山上にて記念の写真を撮る。中央に八十歳以上の老僧、そのほか多くの人びとあり。のち帰途につく。
午後六時宿に着す。山上の眺望非常によし。ただ一面のジャングルの林には驚くのほかなし。この中には野生の象及び虎そのほか、種々なる獣の住すといえり。
d19171105十一月五日祇園寺塔
午前早朝に北二哩近くにある祇園寺塔に詣ず。塔の周囲は敷石をもって廻らし、その付近一帯は樹木繁茂し、所どころに寺院の跡多く、石柱の横たわるありて、塔から南半丁ほどの所には釈尊の座石像丈八尺ぐらいの結構なるあり。また西南にも同様の像あり。
樹林はわが奈良の春日大社樹林によく似たり。もって往時の盛んなるの感、ただ深し。ここより西南二丁にランカー塔あり。丈低く、寺僧の再築を計りつつあり。なお一ケ所の塔に詣ず。午後は休息をなす。
d19171106十一月六日出発、印度に向かう
この日降雨あり。一日休息をなす。少しく洗濯をなす。午後七時に出発いたし、停車場にて五時間ほど待つ。土人は我々一行を見ること非常に目新しきものとして、至るところで人垣をつくる。出発まで人びとの送るの感あり。仏教国のこととて至るところ親切で、はなはだ気持よし。二周目の巡拝、感また深し。ただ仏教の永く続かんことを祈る。合掌、祈念。

11月4日(続き)
〜11月7日(途中)
(46/85)
d19171107十一月七日マドゥライ76着
午前六時半、渡船場着。同九時渡海。汽車に乗り換えて再び印度の屯(たむろ)を見る。進むにしたがい暑さを感ず。印度最南端の暑い国。床に入りて休む。午後一時に起き出でてバナナなどを食し昼食に代える。
午後三時マドゥライに着く。有名なるヒンズー寺院を見る。その造営の盛んなるはいかん。すべて石造りにして彫刻無数、内陣の彫刻もっとも佳作。その精巧なる肉感的なる活躍的なるも、むしろ品格、すなわち最上の気には乏し。ただ盛んなる熱心なる造営には一驚するものなり。おもちゃなどを買い夕刻帰る。途上マホメダンの家にて食事をなす。今はまったく土人式に化したる自分に感心する。
出発は夜の八時半。三等の切符を買い、ポリチポリ駅の到着は夜中の三時。下車して乗り換えまでは間がある。ベンチの上で一休みと毛布にくるまり休む。
d19171108十一月八日
午前七時半、乗り換えて出発。午後三時にイローデー(*足跡図ではエローデ)に着く。三時半ごろ出発。午後十一時過ぎにジャレット駅着。
d19171109十一月九日マイソール州バンガロー77
午前一時過ぎ乗り換えて発車。満員の車内にようやく乗りて、床に入ることもならず。眠き眼をこすりながらトロトロと一眠りなし、午前六時半にバンガロールに着く。至るところ巡査及び刑事の付きまとうところとて、はなはだ迷惑を感ず。
ただちにヒンズーの無料宿舎に行き一室を求む。建築なかなか盛んなるもの、上等のホテルのごとし。しかし余らは下等なる室にて、石畳の上に寝る次第。釜戸もその脇にあるという。それでも昨日今日まではパンのみ食せしうえ、眠りの不足し疲れたる身には上等。野菜そのほかを巡査公の案内にて買い求め、炊事をなし、美味であるとはいいながら食せしときは格別のこと。気候は暑きことなく、日本の秋のごとし。まず一休みと床に入りて休む。
午後は市中を見物し、靴及び小物などを買い求めて宿に帰る。夕食をとり、前日の疲れを治さんと床に入れど、非常に多くの人びとの同宿するため雑踏をなし、そのうえ南京虫の襲撃は、いまだ見ざるほど大多数の突貫を受けて非常の苦しみ、安眠なすを得ず。

11月7日(続き)
〜11月10日(途中)
(47/85)
d19171110十一月十日
午前中、邦人の桜井氏のあるを聞く。彼はマイソールのラヂヤの御弟氏方に住むという。馬車に乗り二マイルほど行き訪ねた。同氏は〇〇〇〇(*判読困難)。日本人青年二人ありて種々談ず。執事来たり、明日午後四時〇◯◯氏◯◯◯(*判読困難)の約をなし、片道センダン樹にて造りし櫛屋ヘ訪ね行き見る。
この辺りは外人町にて綺麗なる広きところ。種々の品はセンダン樹にて造りてあれども非常なる高価なり。櫛を求め土人町に出て帰る。午後眠りをとり(*以下も判読困難)。
d19171111十一月十一日出発
昼食をヒスルマンの縄的(*?)茶屋に入りて食す。その価はなはだ安く、なかなかに食するを得る。
前日の約によりてカントラジヤの家に向かい、途中博物館を見る。ラジヤの建築による数個の石彫あり。そのうち二、三は最も古くアショカ(*原稿は阿摩迦)朝に近き面白きもの。一つは摩耶夫人ならんと思う。一つは戦時その他。これは仏教寺院のものならん。そのほかにも上等の石彫あり。二、三写生をなす。
それよりカントラジヤに面会する。氏の作品は日本への想いきわめて親交なる好男子である。応接の間は日本美を用い、すべて日本で求めしもの多し。茶の馳走になり一時間あまりにして帰る。
帰途、先刻の縄式(*縄的茶屋)に入り夕食をとり、なお朝食の用意をなし、馬車を雇いて停車場に至る。九時発にて車室はインター。バンガローを出発し孟買(ムンバイ)に向かう。(*以下余白)
カントラジヤの家には五十嵐、鈴木という二ボーイあり。この箱中は桜井、小野、小村などの乗客ありしと。
d19171112十一月十二日孟買(ムンバイ)へ向かう
車中ただ二人にてはなはだ気楽なり。この辺りは高地にて、河は少し流れて水田はほとんどなし。荒地多し。気候はわが国の十一月ごろ。海抜二千尺の地という。
d19171113十一月十三日孟買(ムンバイ)着
午前六時ごろプーナ78という駅にて乗り換える。この地は孟買の避暑地にて景色まことによし。進むほどに小山多く、ようやく下りとなりて、ついに孟買に着く。すぐに領事館を訪ねるに、この日より三日間は土人の正月にて、役所及び商会はみな休日となる。
それよりマラバルヒルに日本綿花の楠本氏を訪ねる。時に同氏は旅行中にて、やむを得ず荷物のみ預け置き、領事館の官宅に行く。新領事及び伊藤氏、その他ひとりの日本人ありて談ず。
時を移して夕刻まで居り、それより夕食をマホメダンの家にて食し、ヒンズーのダルマサーラのバンガローに行くも、人にていっぱい、一室もなし。やむを得ず野外の軒下の石敷きの上に寝る。その付近はことごとく雑多の人びと、なかには乞食などもある。これ真に社会の味と思う。種々考え、そのうちに眠ることを得る。

11月10日(続き)
〜11月13日
(48/85)
d19171114十一月十四日
正月第二日とて市中は朝早くより人出多く、皆みな晴れ着を付け、家は飾り物などをなし、市中はなはだ雑踏をなす。終日見物をなし、夕刻日本町に行き、岡氏の知人〇◯(*原稿欠)という女将(おかみ)を訪ねる。同女ありて、ついにその夜はそこに一泊を頼み安眠をなす。
この日夕食は領事館の招待を受け、新領事〇〇(*原稿欠)氏、伊藤氏の四人、及び両人妻君の六人で会食をなし、十時ごろに帰り休む。
d19171115十一月十五日
午前中市中に買い物などをなし、午後四時ごろ楠本氏を訪ね、種々話した末についに世話になることになり、この家に寝る。高所で海に面し、市中を見、遠くを見、まったくなる絶佳の地。
d19171116十一月十六日出発
在宅領事館の人びと及び楠本氏のために絵を絹本に揮毫なし、手紙なども認め、夜になる。
十時半発車にて出発ということになる。楠本氏も種々とり持って、缶詰、雑誌など贈り物もあり、自動車にて停車場に送られ、二等車によってひとまず孟買(ムンバイ)の地を去る。五日間の孟買、種々の労楽を受け、感また深し。

11月14日
〜11月17日(途中)
(49/85)
d19171117十一月十七日ナーシク窟寺院79
午前七時近くにナーシクの停車場に着く。軌道馬車もあれども、余らは馬車によりてナーシク町に至りバンガロー着。停車場より町までは二哩(マイル)ほどもある。バンガローより窟寺院まで三哩近くある道は完全にしてバニアン樹の並木。この辺り〇〇(*原稿欠)作なく見渡すかぎり草原にて、奇なる山岳を廻らし風望ことに気持よし。
ほどなく馬車は止まる。見れば山の中腹に窟の多く見ゆる。ここにもバンガローの小なるもの一つあり。道より半哩ほどにて寺院に至る。風景よし。第一窟より第二十三窟になり、西より東に渡る。第二、第三、第十五、第二十三窟などは破壊せり。中には建造二、三世紀ごろのものもある。阿育(*アショカ)文字、刻文なども柱にあり。彫刻はけっこう古きも新しきもあり、上、不上などあり。写生などをなし、午後一時半ごろバンガローに帰る。
寺には村人の寺院世話係り二、三人及び老婆などがいる。村人は案内をする。我々は五アンナほどをやる。馬車は停車場よりバンガローまで一ルピー。それより寺まで往復二ルピー半。少し安くなるようである。しかしてバンガローに一泊のことになり、飯を作り、食後ベッドの人となり夕刻まで一眠りをとり、起き出でてまたまた食事を作る。
d19171118十一月十八日出発
早朝四時に起き出でて飯を作り、五時過ぎ馬車によりて出発す。六時半の発車というに汽車は一時間半ほど遅れ、マンマット(*マンマッド?)駅にては乗り換えに苦力(クーリー)がなきため荷物の持ち運びならず。ようやくにして苦力ありて岡氏が先に乗り、余は一足遅れての発車。岡氏は出発。取り残されてただひとり、やむを得ず二等特急室に夜の八時半まで待つこととなり、寝つ起きつして夕刻に至る。土人來たりて、余の友人返り来たれりと言う。ほどなく岡氏を伴い来たる。岡氏も二、三駅先きの停車場より帰り來たりしなり。
ダラマダバット(*ダウラタバード?)駅に午後十一時に着く。駅の待合室に寝る。巡査が我々に親切に話をし、明朝出発の馬車男に、往復四ルピーの約束にて取り計らってくれた。寝たけれど南京虫の多くおり眠ることかなわず。把撃をなしたれども取り尽くせず、寝たり覚めたりなどをなす。

11月17日(続き)
〜11月19日(途中)
(50/85)
d19171119十一月十九日イロラ(エローラ)80
朝七時出発。牛車、前日の馬車に比しはなはだ遅く、途中山にかかるころヒンズーの古城跡を過ぐ。天然の山を城として、砦の中に町あり。過ぐれば峠にかかりて眺望ことによし。頂上を少し行くとモスルマン宗の城あり。郭内に町あり。城とともに古く、荒れ果てたるもまた面白き町、古時盛んなるを思わしむ。城郭を出でて二、三丁行くほどにダークバンガロー81あり。わが国の榛名山上に似たるところ、眺望またはなはだよし。一日ひとり一ルピーにて一室を借り受く。
昼食をなし、半哩(マイル)ほど坂道を下ると窟寺院に達す。向って右より第一号窟。第十七号窟までを仏寺窟となし、中央にヒンズー寺院あり。それより左(すべて山の中腹)に二十号窟まである。窟は大小ありて、ことごとく彫刻あり。古きも新しきもある。一号窟は彫刻なし。二号窟は彫刻よし。写生をなす。余の考うるに今を去る一千二、三百年前となす。第三号窟も同じ時代、第四号、第五号窟もまた同じ。第五号、第六号窟は二階造りにて、ことに第六号窟の石彫は左右の御立像、観音像及び勢至菩薩像が丈一尺ぐらいにして上々の作。窟中随一と思考す。写生をなす。その他の室も二階あるもなきもありて、多少新しき彫刻はやや劣る。
第十四号窟は彫刻が一種変りて、多少ヒンズー教の混在のごとく見受けられる。しかれども中央には仏陀の座せしならんと考えられ、左右の御立像のごときは他の様式と異同なし。ただ周囲の彫刻その他と異なりたるうえ、多少年代の若きこと、肉的活動の自由なる、ことにヒンズー的なるは、仏教末期の宗派の然らしむるを、のち印度者の反(かえ)りて取り込みたるものか。これまた写生をなす。十五、十六、十七号窟などはさほどのものでもなし。
中央の印度教の大石寺、これは窟寺院とは少しく異なれり。一面の大石山を殿堂のごとくくり抜きたるもの。その建築、設計、彫刻、絵画(今は落ちて少しばかりあり)、実に驚くのほかなきものありき。時代は彼のコナーラク寺院と時代を同じうせり。今を去る一千年より一千百年ぐらい前か。そのほかジャイナ教82及び印度教の寺窟二十四号窟まである。しかるに夕刻にして、しかも土人の巡査の「虎三匹ほどこの辺りに出没す」とたって止むるによりて中止し、バンガローに帰る。
先にアクバル大帝83の征しにこの地に来られしと言うに、異宗教寺の破壊なきは奇異の感なきにあらず。考うるに大帝はやがて美術を奨励したるほどの名君なれば、この地に来たり、この美術の盛んなるに敬意をはらいたるならん。また部下も大帝の意を常にいただき、多くの武士も破壊の蛮心をほしいままにするを恐れたるならん。しかも先には仏教寺の盛んなる後、印度教、ジャイナ教なども相当の盛時をきわめ、後にまたマホメダンの時代となりて盛んなる跡を示すに至りても、今は皆ことごとく衰えたり。
要するにこの地は眺望には可なり、事をするには適せりといえども、田畑なき荒地、何物もあらず。人民の住するには困難を告ぐ。ことごとく末時に至るは天然の然らしむるところなり。今日風俗もまた下りて、女子の衣服の色、また不快を覚えるほどに下落す。人情、風俗の、よりて自然の然らしむるところ。
ダークバンガローは今までになき気持のよきところ、まったく疲れを忘れしむ。カレーの夕食もことのほかなる珍味を感じ、「狼は面白きもの」と小唄なぞ出ずるほどである。

11月19日(続き)
〜11月19日(途中)
(51/85)
d19171120十一月二十日出発
朝茶を飲みいるところ、三井物産孟買(ムンバイ)出張員の吉本氏来たりて、「きのう松山中佐在デリー武官を案内し来たれり」と。よりて宿へ岡氏と訪問し少し談ず。余らは十時に出発、中佐等は参拝というので長くも談ずることかなわず。辞して帰り、昼食をとり、やがて出発。
午後二時に停車場に着く。同三時三分の汽車にて出発。午後五時五十七分にマンマッド駅に着く。ここで明朝三時まで待つということである。余らは前日乗り換えのとき苦力(クーリー)のなきため乗り遅れしにこ(懲)り、ことに夜中なれば発車付近にあるをよしとして、ついに荷物小屋の軒下に、しかも土間に伏すことになる。時あたかも雷雨の後にて、雨来たりて止まず夜を明かす。

11月19日(続き)
〜11月21日(途中)
(52/85)
d19171121十一月二十一日
時刻来たりて室内に入るに、支那人多く横臥して確たる席なし。無理に窓より入り込む。二、三の停車場に下車の人ありて初めて横臥するを得て、いつの間にか眠ることを得る。
ほどなく夜は明け汽車は進むほどに、この辺りの土地は原野にして耕地少なく、村民は痩せ、終日さらに農地を見ず。見渡すかぎり原野にして右方に遠く山脈横たわり、左方には小さき岡見ゆ。今や秋色来たりて草木色づき、秋風来たりて内地を旅行するの感も出ず。
午後九時二十八分サッツナー(*サトナ?)駅に下車。食堂の一室を駅長の許しを得て使用し、安眠をとる。
d19171122十一月二十二日
駅前の商家でこの町の財産家の厚意により、この家に宿泊することとなり終日休息をなす。夕刻町を見て歩き、少しのものを買い求め、更紗切れなどを買う。この商家の主人はMr. B. Lalbeher。

11月21日(続き)
〜11月23日(途中)
(53/85)
d19171123十一月二十三日
早朝より、この家の子息及び同氏の友人及びほかに老人の案内者ありて、一荷という馬車に乗りて東南九哩(*マイル)にあるバルフートの仏教寺院に行く。これも古きアショカ朝の建築にして、石彫なども結構をきわめ、英政府の自国及びカルカッタ(甲谷陀)の博物館に陳列してあり。この地は仏陀の古き御足跡にして毒龍窟の物語の山あり。山麓に塔ありたるも今は小なりて、ただ跡のみ。山の東西に当時は王城ありて、王の仏に帰依して仏の像を作りしは同王をもって初めとすと。この国の名は古時コーサンビと言い、山脈をもって廻らし、サツナー(*足跡図はサトナ)河あり。田畑ありて王城をなす。
この地、余は初めて仏跡に足を入るるの感また深く、朝より六、七人にて同所に向かい、ガリは二哩(マイル)ほど手前にて下車。バタノワラ村に例の彫刻一つありて写生をなす。これもよきもの。程なく山麓に達し、古塔の跡、石彫は持ち去りし跡といえども、この地こその感はなはだ深きものあり。破片二、三を得る。これより山上二哩ほどの所は道なく、ジャングルの中を案内者ともども八名で登る。その困難はまた言語に絶す。樹を切り断崖を登り、しかして頂上に達す。草は横に伏して自ら道あり。これ虎の伏すところ、気味はなはだ悪し。進むほどに岩下に虎の糞多々あり、獣骨あり、まったく虎の巣窟をここに初めて見る。その窟多々あり。
このごとくして頂上を探求するは、アショカ朝の刻文のあると言う話によりてなり。しかるに今は大岩破損して跡形なし。ただ殿堂のありし跡ありて柱石多くあり。展望ことによし。山麓に二村ありて、また古石彫二つありと。日暮れのため見るを得ず。
しかして余らは下山をすべくジャングルの中を進む。時に午後三時過ぎ、空腹はなはだしけれど、時を移さば一大事と勇を鼓して進む。案内の若者はよく進む。その困苦名状すべからず。夕暮れ、ようやくにして下山をなし、井戸の端に行き霊水を飲みしときは蘇生の感ありき。同行の二人(宿の子息及び友人)、ことにその友人というははなはだ疲れ、ようやくにしてバタノワラ村に着き食をなし、ガリにて帰り着きし時は九時半という。すぐに床に入り眠ること早かりき。
d19171124十一月二十四日
一日休息をなす。午前中町を見歩き、夕刻また町に出ず。
d19171125十一月二十五日出発
午前九時同駅より荷車に乗り、家息二人及び警察の人や友人という連中にて同行八人。隣村に古き仏寺院ありとて案内せられ、およそ七哩(マイル)ほどにして下車。この地は石盤を盛んに製造なす。ここより約二哩半ほどにしてバルジナ村に着く。破壊されたる石造寺院の跡は無数に彫刻物の横たわり、その作もっとも可作(*佳作?)にして、およそ今を去る一千年前のものと思考す。彼のコナーラク彫刻とほとんど同式のもの。
ただちに帰り汽車に乗りてサツナー(*サトナ?)の宿所に着く。ひと休息をなし、夕刻、町及び公園を息君の案内にて歩き回る。公園には一千年前の石彫仏陀の御像あり。土中に下向きとなしてあり、岡氏これを建て戻す。上々の作、縦四尺ぐらい。町は五十年前に出来たる由にて新しき町となす。しかれども古風の町。池は二つあり、寺もジャイナ教及びヒンズー教と多々あり。周囲は広く行楽の地なり。
この日ラジヤの王妃この世を去りたまう日とて、町は三日間休業の由。この日は午後九時半の汽車にて出発す。出立に際し、この家の親切なるを深く感謝す。汽車はインター(*この後、判読不明)

11月23日(続き)
〜11月25日
(54/85)
d19171126十一月二十六日(*アッラーハーバード?)
午前一時半着。駅内の隅に夜を明かす。朝、馬車を雇い、印度教の宿屋に着く。十時ごろより一荷という馬車(面白きもの)に乗り、ガンジス河に至る。ここは煩河(*?)とジャムナ河(*ヤムナ河)との落ち合う所にて霊地となし、多くの行者及び信徒の水浴行をなす所。古時玄奘法師もこの地を大地主(*大施主?)の所と言い、今に至るまで盛んなり。少しのところ舟に乗り、落ち合う水のところまで行きて見る。
帰途市内のバザーに寄りて少しばかりの物を買う。三時ごろ帰宿、休息をなす。
d19171127十一月二十七日出発
早朝再度バザーに行き、品物などを買い求む。しかして午前十一時四十五分の発車、パンジャブ甲谷陀(カルカッタ)メールに乗り(二等室は二十四ルピー〇アンナ)甲谷陀市に向かう。発車後間もなく次の駅に至る。Nale(*ネール)というこの駅の六、七丁の所に仏彫刻の佳作が二、三樹下にあるのを見た。おそらくはこの近辺に古寺のありしか。
午後九時にパトナ駅にて岡氏下車。同駅より四哩(マイル)ほどの地にアショカ王城の跡、今は英国のガバーメントにて発掘中の由。前の停車場にて岡氏の窓より飛び込むのを見た。一時間ほど進むとガンジス河の淵に出ず。月下に仏跡の地を拝し、三ケ月後に必ず参拝をいたすべく祈念、合掌す。

11月26日
〜11月28日(途中)
(55/85)
d19171128十一月二十八日甲谷陀(カルカッタ)着
午前十時ハウラ停車場に着き、馬車によりて帰宅す。
午後チットプール84にてジャイナ教の祭りを見る。道中大象の造車、様々の出し物、家々の小児、子供に盛装をさせ、馬車あるいは自動車の数かぎりなく引き続き、最後にジイナゴート85を引く騎馬数頭あり。その装飾、金銀の唐鞍(からくら)にもっとも近きは妙なりき。古代印度より支那に渡りて少しく変化せしが、唐朝の頃わが国に来たりしものならん。夜は音楽の会ありて多くの人びと来る。タゴール翁も音楽をなす。そのほかに男女及び楽師もありて面白かりき。
旅行出発以来一ケ月二十日間を要し、全印度の三分の二は行きしならん。費用二百十三ルピー十二アンナという。これも安価なりしは岡氏のおかげ。食する物も食せず、飲むべき物も飲まずという場合多くありき。困難だけに後にては宝となす。この旅行にて印度に来たる甲斐ありき。大いに得るところありと信ず。要するにこの難行苦行も、御仏の吾に味を味わわせんがためと信ず。まったく天地の味に触れるなり。有難し有難し。
これにて第一回の旅行を修む。しかして第二回アジャンター模写より始めんとす。

11月28日(続き)
〜11月28日
(56/85)
d19171129十一月二十九日
午前中より少し気持ち悪し。床に伏す。熱気あり。前日湯をつかい、すぐに祭を見るべく外出。日照り帽子を持たぬが原因にて風邪気味ならん。帰宅後にて誠によろし。道中にての病気は閉口なり。
d19171130十一月三十日
少しく快方。この分にては翌日は快癒せることならんと思う。
d19171201十二月一日
熱引いて気持よし。しかしながらいまだ全快とはならぬ。少しく頭重し。しかれども起き出でて、商人の来たりて談ず。
前日端書を野生司君のところに出だせしに、夕刻電話にて明朝来ると言うによりて心待ちに待つ。午後一時ごろ野生司君来る。ほどなくボシュ君、シレン君なども来る。大いに談じ、野生司君をアジャンター模写の仲間に入れるよう話をつけた。オボニンドロナト・タゴール氏もダージリンより帰り来たり会談す。コロンボで買いし細工物をロテン(*ロティンドロナト氏?)氏に呈せしに、靴(*イラストあり)を余に贈らる。
d19171202十二月二日
早朝より気持よし。全快なす。午後よりボシュ君来たりて夕食を馳走すると言う。行きて馳走になる。

11月29日
〜12月2日
(57/85)
d19171203十二月三日
午後より郵船会社に行き、屏風運送費の立替金二十二ルピー十五アンナを前田君に払う。三井物産に行き笠松氏に面会し、孟買(ムンバイ)三井に紹介状の依頼をなす。田嶋氏にも会す。夕食を同氏宅に馳走になることを約し、帰途ホワイトイー及びバザーなどにて小物を買い求め、万歳商会にも寄り、しかして田嶋氏のところに至る。
新しく妻君来たりて同氏得意の色あり。同妻君は松下君の学校にて、松下君の名刺を持参す。快談数刻、帰宅す。電報ありて、沢村君の一行は孟買着。余も明日は孟買に向かうべく決す。
d19171204十二月四日
午後領事館に至り、新領事酒辺氏に会す。それより野生司君を訪ね、夕食の馳走になり、乾氏宅に一泊す。
d19171205十二月五日出発
アジャンター行は模写のためで三ケ月間の予定。野生司君を同道し帰宅。ただちに出発の準備をなし、午後一時二十分の孟買メイルに乗じて出発す。野生司君も停車場まで送らる。
d19171206十二月六日
何事もなし。途中ジャコという獣を見る。また野鹿をも見、ラクダなども見る。車中はいたって気楽でありき。みな西洋人、夫婦者も乗り合わす。
d19171207十二月七日
午前九時過ぎ孟買(ムンバイ)ビクトリア停車場に着く。すぐに三井物産に行き、沢村君、浅井君86に会す。午後沢村君と買物に町に出て、種々準備品を求む。帰途、酒あり肴ある家に休む。

12月3日
〜12月8日(途中)
(58/85)
d19171208十二月八日
再び買物に出ず。まず大ランプその他を求め、正金銀行に行き五十嵐氏に会す。日本綿花にも行き楠本氏にも面会す。明日エレファンタに行くとて余も行くことになる。領事館に夕食の招待を受け、農商務省の◯◯(*原稿欠)氏にも会す。
d19171209十二月九日日曜 エレファンタ87
午前八時半に日本綿花の連中と小汽船にてエレファンタに向かう。約一時間にして着く。石段を二丁ほど上り窟に達す。正面三面の大いなる、もっとも良き石彫。シバ三尊の像と言う。半身体のものもあり、そのほか大なる彫刻多々あり。紀元後八世紀ごろのものと言う。多く破壊のありて、はなはだ遺憾なり。写生などをなす。
中央に大いなる堂、左右に天上切り抜きたる一堂ずつあり。この付近景色よし。猿なども見る午後二時に帰る。
d19171210十二月十日
午前より日本郵船、商船(*三井?)、日本綿花、三井の社に行き各支店長に会し、午後は大ランプそのほかの買物をなす。
d19171211十二月十一日アジャンター
正午、昼食を森岡氏の馳走にて海岸の洋食店にて食す。帰途、古道具屋にてパーシーの絵画を五十ルピーにて買う。午後九時四十分の発車にてジャルガオン88に向かう。
d19171212十二月十二日
午前五時二十分、ジャルガオンに着く。三井物産出張員の西村小八郎君の出迎えを受け、万事世話になる。三井のバンガローに行く。
この日は荷物を牛車五車、ボーイ及びコックを一車にて出発せしめ、吾々は明日出発なすこととなる。

12月8日(続き)
〜12月13日(途中)
(59/85)
d19171213十二月十三日
午前七時、三井の北村氏の案内にてトンガ89二車に乗りて出発す。途中は高原のこととて稲作を見ず、民はやせ衰う。道はよき道にてモーターなども往復なすを得る。道側は〇〇(*原稿欠)樹にて並木をなし気持よし。鹿及び〇〇(*原稿欠)を見る。
二つの河を過ぎ二つの村を見る。この辺りぺストのある地とて、村人は多く野外に避難し居る。吾々は午後四時近くにダークバンガローに到着。この夜はウイスキーを抜き労をいやす。
d19171214十二月十四日
午前八時半ダークバンガローを出発、窟寺院に向かう。一哩(マイル)ほどは凸凹の原野にて、北西より南東に山脈の横たわり、山麓のハイダラバッド90の役員テントに依りてある。これより山渓に入り風望ことによし。五哩(マイル)にして窟寺院に着く。
寺院は断崖の丸く廻らせし中腹に並ぶ。向かって右より二十六窟あり、いにしえは二十九窟という。おそらく三窟は崩れたるならん。実に勝景の霊地にして、下流は水清く、上流に滝あり。初めて窟内に入り第十窟のスツーパに拝し壁画に接したる時は、知らず感涙を覚え、感深し。
一巡拝をなし、荷物運搬の世話もなし、同行の北村君に非常なる尽力を得る。同君は正午より帰り、吾々は四時に帰る。アジャンター窟寺院の初日の感は深くして、仏教盛勢時の今を去る一千有余年前の建立、今もその時を見るの感をまた感ず。
d19171215十二月十五日
午前八時より出発、模写の準備をなす。
d19171216十二月十六日
午前八時出発、窟寺院に向かう。 第一号窟の降魔(ごうま)の図を写すべく準備をなす。終日窟内にいる。窟寺院の役員二人に夕食を供す。

12月13日(続き)
〜12月17日(途中)
(60/85)
d19171217十二月十七日降魔の図を写し始む
午前八時バンガローを出て窟寺院に至り、模写を始む。夕刻より前日の役員にテント内にて夕食のご馳走になる。帰途三人の送り人あり、ひとりは鉄砲を手にす。猛獣の用意になす。
d19171218十二月十八日
午前八時近くに家を出で、窟寺院内に模写をなす。その困難また言語に絶す。
d19171219十二月十九日
疲れを休めんため、この日休息をなす。
d19171220十二月二十日
早朝より窟寺院に行く。線書きをなす。虎の足跡を見る。
d19171221十二月二十一日
前日に同じ。
d19171222十二月二十二日
前日に同じ。大野君及び鴨下君91、常三郎、野生司君のところへ妻君より來る。野生司君、二十五日出発すと電報あり。
d19171223十二月二十三日
早朝より窟寺院に至り、線書出来(しゅったい)す。
d19171224十二月二十四日
例によりて例のごとし。着色を始む。
d19171225十二月二十五日
窟寺院(*原稿は「窟」。以下同)に行く。
d19171226十二月二十六日
休息なし、手紙などを認(したた)む。

12月17日(続き)
〜12月27日(途中)
(61/85)
d19171227十二月二十七日
窟寺院に行く。パーシーの老画家、アジャンター窟寺院の壁画を英ガバーメントの依頼にて、十二年間寺院内生活をなし模写をなしたる人、その家の人びと来たりて会す。名をPestonpe92と言い孟買(ムンバイ)に住す。
d19171228十二月二十八日
窟寺院に行く。
d19171229十二月二十九日
窟寺院に行く。
d19171230十二月三十日
夕刻、桐谷洗鱗君93、武上氏来る。大いに呑み、大いに食す。
d19171231十二月三十一日
窟寺院に行く。
d19180101大正七(一九一八)年一月元旦
雑炊を食し、酒を呑み、元旦の祝いをなす。桐谷君一行も加わり、五人の人びとにて終日遊ぶ。
d19180102一月二日
休息をなす。桐谷君一行は馬車の到着なきため、ジャルガオンに向かう。夕刻、馬車ボーイ来る。桐谷君には会えず。沢村君と白緑青土を見出す。喜々然たる二人は重きほど持ち帰る。
d19180103一月三日
仕事始めを一日早めて早朝出発。模写に着手。夕刻帰宅。
d19180104一月四日
窟寺院に行く。夕食を下役人に馳走なす。
d19180105一月五日
窟寺院に行く。桐谷君、再び帰り来る。
d19180106一月六日
窟寺院に行く。
d19180107一月七日
窟寺院に行く。降魔(ごうま)の図、中央をほとんど修む。
d19180108一月八日
窟寺院に行く。降魔の図第二に着手なす。
d19180109一月九日
窟寺院に行く。道途二千年前の道について考えをもつ。桐谷君のボーイ不正(*?)をなす。

12月27日(続き)
〜大正7(1918)年1月9日
(62/85)
d19180110一月十日
窟寺院に行く。
d19180111一月十一日
窟寺院に行く。アーマド氏94及び外役人帰り来る。
d19180112一月十二日
窟寺院に行く。
d19180113一月十三日
洞窟に行く(*窟寺院=洞窟?「窟」は窟寺院、「洞窟」は洞窟と表記)。
d19180114一月十四日
洞窟に行く。
d19180115一月十五日
洞窟付近の村人非常に多く来たりて洞窟前の河辺に集まり、老幼男女一日の楽しみとなす。すべて印度教人にして色また黒し。河辺には多くの商人出でて、豆の焼きし物を多く売る。わが国の歳越しのごとし。この日は日の出、日の入り等分の日とて、翌日より日の長くなる境い目という。かかるゆえの祭りである。
d19180116一月十六日(*日付の記述はないが前日の最後の一文を同日の日記とする。)
降魔(ごうま)の図、中央二面の模写出来(しゅったい)す。
d19180117一月十七日
疲労を休めるため休息す。沢村君は役人らと新発見の洞窟を見るために出掛く。夕刻パーシー人夫婦来たりて一室を開け貸し与う。桐谷君は大いに不屈(*不満?)。程なく野生司君来る。大いに談ず。
d19180118一月十八日
洞窟に行き野生司君を案内す。かつ野生司君より種々条件を出さる。余はなはだ困惑す。しかれども話し合いの結果、平安的になさしむ。
夕刻帰宅。前日のパーシー人夫婦、前約にたがい室内に居り、吾々に対して一言の礼儀もなさず。無礼を責む。英字をもって手紙をよこす。当方もまた日本文字の手紙を出す。
d19180119一月十九日
朝、武上君及び桐谷君、再度論戦す。のち窟寺院に行く。夕刻沢村君帰り来る。この日降魔の図の最右端を始む。
d19180120一月二十日
洞窟に行く。野生司君は十七洞窟の表壁画を始む。

1月10日
〜1月21日(途中)
(63/85)
d19180121一月二十一日
洞窟に行く。桐谷、野生司、朝井の三君と共に洞窟山上に登り見る。時に猿多く住み、なかには大猿あり。色薄白く尾長く、顔の色黒し。朝井君と共にまたまた山上に登り展望をなす。時に谷間を見下ろすに、亜仁多(アジャンター)河の上流ありて小村落あり。レナポールという。写生をなす。下りて村に行き写生などをなす。
帰途洞窟上の岩に立ち滝を望み見るに、神秘的にして、鷲多く岩間に住む。岩は白く雪を置きしに似たり。これみな鷲の糞なりき。半日の歩み、また得るところ大なりき。滝壺の感深し。画材となる。
午後は模写をなし家に帰る。ロバー及びそのほか面白き花の写生をなす。
d19180122一月二十二日
洞窟に行く。この日雲多く来たりて、夕刻降雨少なし。
d19180123一月二十三日
洞窟に行く。降魔(ごうま)の右端を書き修む。今日もまた雲多し。
d19180124一月二十四日
降魔の左端に着手。
d19180125一月二十五日
洞窟に行く。朝より虫歯が痛み、午後帰宅。
d19180126一月二十六日
休息なす。痛みなお回復せず、夜分安眠せず。
d19180127一月二十七日
なお休息なす。
d19180128一月二十八日
諸君も休息す。
d19180129一月二十九日
洞窟に行く。中学程度の学生二十余人と教員二人、当バンガローに来たりて宿泊す。

1月21日(続き)
〜1月30日(途中)
(64/85)
d19180130一月三十日
洞窟に行く。帰途、山中の樹影より大声を発して飛び出せし者、「ああ、荒井さん」と言う。これムクル君にてありき。彼はいかにも嬉しさのきわみにてありき。この山中に案内者なくただひとり、しかも夕刻、たどりたどり路傍に伏し居たり。しかるに余らの一行の来たるに会す。彼の嬉びさもあらん。しかして同君は余の室に居ることになす。
この夜またかの学生及び教員の一行も宿泊なす。たまたま吾らと彼らと月下に座をとり歌合せをなす。初め土人のボーイ君歌う。次に桐谷君尺八を吹く。次に学生、またまた桐谷君という次第にて、替わるがわるに歌う。しかして余もまた歌うところとなる。大いに面白きかぎり。
d19180131一月三十一日
洞窟に行く。第一洞より新道をつくる道ができ、余ら帰途初めて通り初めをなす。
d19180201二月一日
洞窟に行く。
d19180202二月二日
洞窟に行く。ハイダラバッドの役人多数来たり、「バンガローを貸せ」と。応じず。
d19180203二月三日
洞窟に行く。帰途、道にて孔雀三羽いるを見る。感じて孔雀明王の図を作るべく考案を起こす。
d19180204二月四日
洞窟に行く。沢村君及びムクル君ら、アランガバート95よりエローラに向かう。節分の日とて夕食に雑煮を作り桐谷君を招待なす。この日使いの男に四アンナを給す。
d19180205二月五日
洞窟に行く。降魔の図ぜんぶ出来(しゅったい)なす。印度人画家の那低仙(*?)氏来る。
d19180206二月六日
洞窟に行く。菩薩像(正面向かって左側)及び向かって右側の仏の図三葉を写す。
d19180207二月七日
休息なす。
d19180208二月八日
洞窟に行く。正面左側の菩薩像を写す。バンガローには印度の役人多数来たり、テントを多く造り迷惑はなはだし。
d19180209二月九日
洞窟に行く。

1月30日(続き)
〜2月10日(途中)
(65/85)
d19180210二月十日
アジャンター村に行く。南三哩(マイル)の地にあり。ダークバンガローより一哩行きて岡となり、廻り道の岡の上に大門ありて風望よし。岡の上は見わたすかぎり平地なり。実に大陸たるを覚ゆ。行くほどに珍草、珍木あり。ほどなく村に達す。入口に大門あり、前にバニアンの大樹あり、池もある。写生をなす。門内の家屋また面白く、二、三時間を写生にとる。
しかしてバザーに行き、女衣地を二、三反買い求め、帰途牛車に乗りて帰る。しかるに道悪しくして、中途にて下車なし歩みて帰る。
d19180211二月十一日
洞窟に行く。
d19180212二月十二日
洞窟に行く。線書(*線描?)を修む。
d19180213二月十三日
洞窟に行く。
d19180214二月十四日
洞窟に行く。この日おもしろき花を二種見る。
d19180215二月十五日
洞窟に行く。夜、果実及び印度食をハイダラバッドの役人より贈らる。この役人は五、六日滞在の由。多くの人びとを供ない、テントを十数個張りラヒツを造る。税務所官吏長に会す。
d19180216二月十六日
洞窟に行く。アシテニヤ、インジュ帰り来る。
d19180217二月十七日日曜
洞窟に行く。税務所官吏一行、窟寺院に来る。「ご迷惑、ご迷惑」と言いて余の写しいたる所に入り来たり、握手をなして帰る。沢村君も帰り來たる。
d19180218二月十八日
洞窟に行く。
d19180219二月十九日
洞窟に行く。
d19180220二月二十日
洞窟に行く。孔雀の羽をアーマト氏より贈らる。

2月10日(続き)
〜2月21日
(66/85)
d19180221二月二十一日
洞窟に行く。諸役人はこの朝帰り去る。
d19180222二月二十二日
洞窟に行く。菩薩の画出来なす。この日、心不快を感ず。午後帰宅なし伏す。少々の熱気あり。要するに肩をこ(凝)らせしならん。
d19180223二月二十三日
休息なす。なお熱気あり終日伏す。夜分少し爽快。ニザンデン氏96一行転ずる。
d19180224二月二十四日
大いに快気。なお一日の休息をとる。桐谷、武上君帰り去る。
d19180225二月二十五日
洞窟に行く。左側を始む。
d19180226二月二十六日
洞窟に行く。
d19180227二月二十七日
洞窟に行く。この日筆を修む。
d19180228二月二十八日
洞窟に行く。第一洞窟及び第二洞窟の図を写す。
d19180301三月一日
洞窟に行く。第十、第十六、第十七洞窟の写しをなす。

2月21日(続き)
〜3月2日(途中)
(67/85)
d19180302三月二日
洞窟に行く。第十、第十七洞窟の写しをなす。アジャンターの研究、ここにまったく終わりに就く。夕刻、その別れを洞窟に向かいてなす。その感また深く、古代この美をなせる美術家に生き別れの感ありて、涙を出だすを禁ずるあたわず。嗚呼(ああ)百日の業や、今日をもってなるかなと。
古代西暦紀元前一二世紀ごろより六、七世紀に渡るの長き日数において、この大事業をなす。これ真に仏徳のしからしむところ、その力や大なり。その芸術は長く世界に渡りてその徳を残す。その現わすところ、また現世界に自由に出現す。絵画の色彩は複雑なるものなきも、よくその自由なる世界に入れり。一洞窟において四人あるいは五人の大家のなせるその画のなるや、右手を切断すと。しかしてのち再び絵をなさずと。古代印度の美術家の真情、その信仰の強さ、その精神のしからしむる。今日この大美術として長く世に輝きたるはたまたまのことにあらず。我ら縁念ありて百日の間この美に接するを得るは、これまた仏徳によるもの。有難し有難し。
わが国法隆寺の壁画とその類を引くということは、多く世の人の唱うるところ。時代においてもアジャンター第一洞窟ごろと同じうするも、その間おのずから別様なるは深く感ずるところ。ただ法隆寺においてもその印度の直風なる、また筆者のわが国人ならざるを信ず。
余はこの日誌を書する時においても、アジャンター絵画のわが頭脳中にはっきりと現われ出ずるを、いかに感を深くせしか。二千年前の美術家とよく話をなす余もまた幸いあるひとりなりき。まったく仏徳に感謝するものなり。合掌。
d19180303三月三日
午前中荷造りをなし、午後三時半に牛車二台に乗り、アーマト君も同時にマンカット(*足跡図はマンマッド)まで送るという。そのほか牛車六台に荷そのほか〇〇にて夕刻となりバザーあり。下車をなし一巡なす。小川ありて多くの女児の洗濯をなす。その光景またよし。ネリにおいてダークバンガローに入り休息をなし、夕食をとる。時に十二時。
d19180304三月四日
午前二時出発。車に伏し眠る。七時にジャルガオン着。同時刻発のに乗車なし、午後四時孟買(ムンバイ)着。三井物産に入る。
d19180305三月五日
市中にて買物などをなす。夜、芝居を見る。
d19180306三月六日
日本人倶楽部において模写を陳列なし、在留日本人のために展覧す。各会社の重役連と昼食を共にする。
d19180307三月七日
写真の種板(たねいた)、そのほか買物をなす。
d19180308三月八日孟買出発
午後十一時孟買出発。初めインター室に乗るため九時発に間に合うべく停車場に至る。時に時間遅れて得られず、はなはだ困難をきわむ。朝井君に別れる。
d19180309三月九日
午前Bohopal駅97に着き再び乗り換え。駅長に肖像の写生を呈す。ために親切をもって小なる一室を進められる。その室に同乗者ありしを他に転ぜしむ。

3月2日(続き)
〜3月10日(途中)
(68/85)
d19180310三月十日
午前五時ビルシャ駅に着き、一時間の後に乗り換えて次駅サーンチー(*足跡図はシャンチー)に乗り戻る。同停車場に荷物を頼み、五、六丁の地にあるサーンチー塔の岡の下にあるダークバンガローに入り食事をとり、塔に至る。
四面広く山脈を廻らし風望絶佳のところ。この塔二千年前のものにて最古跡。美なる石彫いまなお存す。バルフート式に少しのところアマラバティの彫刻を入れし感ありて、その結構は言語に絶す。写真六葉を撮り写生をもなす。午後三時いちどバンガローに帰りて食事。その後一時間を第二の塔の玉垣の丸模様を写生なす。
急ぎ停車場に至り三十分の後に列車来る。サーンチーの感深く深く、なお一日をこの地にあらざるを遺憾とす。ビルシャ駅に下車。明日の七時まで待つこととなり、待合室に入り写真の現像をなす。六枚とも上々の撮影とて、二君に優るの第一となす。
d19180311三月十一日アグラ着98(*後にデリー着)
バリラの町には堅塁ありて、全印度におけるもっとも有名なる城なり。午前六時出発。インター室に乗り夕刻アグラに着く。八時半Delhi(デリー)着。駅にて夕食をとる。二時間の後、他車にて出発す。
この日、野に生きる真鶴を見る。駱駝の群れ(*原稿は「軍」)と鹿の群れとを見る。
d19180312三月十二日ラホール着
午前十時ラホール駅着。十二時発車にてPeshawar(ペシャワール)99に向かう。進むに連れて人種、風俗、建築など自ずから変わるもまた面白し。
午後十一時過ぎ、ラーワルピンディー市100に着く。途中大雪山の連山北に横たわり、ジイラム河101の夕色はなはだ絶佳をきわむ。風土は日本に同じ。いたるところ駱駝の群れ(*原稿は「軍」)を見る。車中終日写生及び彩色(*原稿は「色彩」)をなす。ラーワルピンディーにては停車場に一泊をとり、椅子の上に眠る。
d19180313三月十三日ラーワルピンディー発、ペシャワール着
午前七時に起き出だし市中の見物をなす。北に近山あり。停車場より六、七丁馬車に乗りて見物に行く。バザーに出でて買物をなす。銅壺及び金器や籠などを求む。すぐに停車場に帰り食事をなし、十時半発車にてペシャワールに向かう。途中連山を右に見、田畑青く、これみな麦にして、あたかもわが国の春色にして、桃の花は麦の中に色どれり。
人種はアラビヤ人も多く、まったく中印度とは感を異にせり。途中山狭まりて渓流あり。バラ河という。流れの岸の岩上に古き人家多く、遠くに雪山を見る。印度松は無数にありて、その間を駱駝が歩み、あるいは牛馬、驢馬に乗る人、水牛を追う者、支那の山水画中にあるの感ありき。夕刻六時半ごろにペシャワールに着き、ただちにダークバンガローに至り宿をとる。ちょっとバザーを見歩く。

3月10日(続き)
〜3月14日(途中)
(69/85)
d19180314三月十四日
早朝、ガンダーラ朝の古塔発掘の地に馬車を走らす。町の中を東に二哩(マイル)ほど進むに、畑の中には発掘の跡とて何ものもなし。ただ石垣の存するのみ。その最東端の跡には彫刻少し存す。カニシカ王の造りたるものと言う。
帰途町内のバザーを見る。この国の織物にして毛布のごとき模様の色の面白きを二枚、二十二ルピーを出して買い求む。午後博物館に至り見る。すべてガンダーラ彫刻のみ。写真及び写生をなすことを得ず。ために五、六枚の写真を買うことを頼み、宿に帰りて食事を作り、九時の発車にてタクシーラに向かう。
d19180315三月十五日タクシーラ古塔
午前五時半サライカラ駅に下車。ラーワルピンディーの二た駅手前。同駅に夜明けを待ち、苦力(クーリー)を連れ、東四、五丁にして博物館あり。英人マーシャル(Marshall)の発掘せしガンダーラ彫刻の古塔、東七、八丁にして今なお発掘を続けつつあり、その古きを十四、五年(初めカンニンガモ氏の発見)。塔の跡及び寺院の跡、今はその土台を存するのみ。すべて大小の石を左のごとく積み(*イラストあり)、その上を漆喰にて塗り仏陀その他を造りたるもの。それより北一丁にして町の跡あり、もっとも古きもの。それより北西七、八丁にして塔あり、町の跡あり、寺院その他あり。
北東五、六丁に塔あり。なお東十丁余りにしてジョホリアンの古塔跡に至り、それを見る。山間に漆喰の彫刻大像あり。それも写真二葉撮影なす。なお十丁ほど進む。岡上に塔及び寺院の跡あり。スツーパ多し。この形もっとも変われり、写真に撮る。その廻りに例の彫刻無数にあり作品よし。すべての段(*?)みな親切をきわむ。風望もよき所。
帰途博物館に至り発掘の彫刻を見る。傑作多し。右の彫刻はギリシャ式を発揮し、ほとんど同様のものありき。五、六葉の写真を頼む。夕刻六時の発車にてラホールに向かう。刑事、巡査の多く来たりて調ぶるには閉口、閉口。
d19180316三月十六日ラホール
早朝着。荷物を停車場に預け、馬車を頼み博物館に至り見る。先に絵画の一室あり。一巡なし、すぐに彫刻室に至る。二室ありて、ほとんどガンダーラ彫刻をもってす。この式のものにては優れたるもの多し。
オボニンドロナト・タゴール氏の弟子グプタ氏に会す。氏は隣りの美術学校に絵画の教員をなしあり。博物館一巡ののち同氏の宅を訪ね、そののち町を一巡なし、バザーなどに行き、夕刻汽車に乗りてデリーに向かう。

3月14日(続き)
〜3月16日
(70/85)
d19180317三月十七日デリー
朝、車中より孔雀の野に降りるを見る。日常近郊に来れば愛すべし。広々としたるは実に気持よし。午前十時半ごろデリー着。五ルピーというホテルに泊まる。
午後、市中にてマホメダンの寺そのほかを見物し、商品を見て二、三品買い求め、ターキーバッスに入浴をなす。デリーの名物を買わんとせば十四ルピーを要すという。我らは人形を買いて宿に帰り、写真の現像をなし安眠をとる。
d19180318三月十八日
朝デリホートを見る。その企図大ならずと言えども、帝王の諸人一見のところは、大理石に模様をなせしは実に結構をきわめ、帝王、女皇の各浴室は見るべきものあり。博物館もその隣りにあり、少しばかりの彫刻、絵画あり。
のち市中に出てバザーを見て買物をなし、いったん宿に帰り、午後九時の発車にてマットラ(*足跡図はマトウラ)に向かう。
d19180319三月十九日マットラ102、アグラ
午前九時ごろ着く。ただちに博物館に至り、写真及び写生をなす。中印度の彫刻なく、サーンチー式のもの多く、なかに結構なるもの四、五点あり。釈尊立像はことにその最たるものなり。いまだこの博物館も整理がつかず、留守居の翁ひとりあるのみにて、写真及び写生を得しは幸いなりき。
しかして市中を見歩く。町は古風にしてジャムナ河に沿い、感動にて我が意を得たり。絵画五、六葉、金物、生物その他を買い求む。今日まで歩きし市町のうちにては、その憂いの感を〇〇(*?)ならしめしものの一つにてありき(*この前後も判読困難)。
夜の七時ごろの汽車にてアグラに向かう。夕刻停車場には悪しきガイド多々ありて実に閉口なす。馬車に乗りてダークバンガローに至れば、今は人を入れず。しかして悪ガイドどもは二人までありて我らの馬車に乗り、ほかにレイルイのダークバンガローありと言う。ひとりのガイドに案内させてほどなく着く。
家の中に至るに間もなく英人二人来たりて、無礼の言をもって我らを追い出すという事件あり。これみな悪しきガイドの知りつつ、我らを導きたるなりき。しかれども夜中、いかんともなすことを得ず。再びガイドによりてホテルに行き、三ルピーという安価にて宿ることとなり、写真の現像をなし三時ごろ伏す。
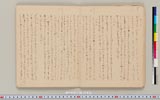
3月17日
〜3月20日(途中)
(71/85)
d19180320三月二十日
昨日約定せしガイド早朝に来たり、馬車によりて第一番にタジマハル103を見る。かねて写真及び話によりて知りたれども、その想像のごとく実に結構をきわめ、白き白き大理石の形は、まったく高き高き感あらしむ。初めて数門の中より見たるときは、思わず「アッ」と声を出す。影の中より明るきを見る、これ真にその意を得たるものなり。
内部の結構さはまた格別のものありて、廻廊をめぐりて後ろに至ればジャムナ河真下を流れ、風光また可なり。すぐに去るにしのびず写真四葉を撮りて、時間のなきため早速帰途につき、途中宮殿のキップを得べく役所に至り、いったん宿に帰り昼食をなし、午後フホート、すなわち宮殿を見る。
城廊デリーとはまったく相違し、企図また大、建造また多く、ジャムナ河よりタジマハルを見るに、その結構なる大理石の建築、皇后の居間、ヒンズーの別皇の室多く、浴所、シャージャハンの囚われたる病室そのほか、実に善美をきわむ。今はこの城内は英兵の守るところとなりて兵舎多し。
二時間余り見物に要し、帰途バザーを見て夕食の後、ホート停車場より九時の発車にてラクノ(*足跡図はラクノー)に向かう。宿はひとり三ルピーは実に安価にてありき。一等ガイドも五ルピーと言うを二ルピーにて約定なす。悪しきガイドと言えども吾々慣れたる旅行者にかかりては、その悪意を用うるあたわざるべし。この夜雨多し。
d19180321三月二十一日ラクノ
午前九時ごろ着く。この停車場の苦力(クーリー)はなはだ悪しく、すべて至るところの苦力はみな悪しかれども、ことに悪しかりき。しかれども我らは強く、その上を越せり。
馬車にて博物館に至り見る。中印度彫刻多し。なかに塑像の上々たるものあり。写真及び写生をなすことを得ず。役人に計りしに許さず。初め写生をなしおりしに、番人来たりて布切れをもって仏体を覆うなどなど、きわめて不親切にてありき。写真五葉を買いて、帰途市中を見物なす。
この町は新しき町とて、町ははなはだ面白からず。ただラジャの婚礼とて、その行列を見る。兵卒、騎馬兵、旗持ち、音楽、駱駝の兵、象に乗りたるラジャ及び花嫁など多くの行列、はなはだ面白かりき。写真を撮影なす。
帰途仏教寺院に至り、若僧及び仏教信徒に会し夕食を勧められ、ついに夕食をなし、九時発の発車にて出立をなすべく停車場に急ぎしに、至りてみればはや発車をなし進むを得ず。停車場の待合室にて眠る。

3月20日(続き)
〜3月22日(途中)
(72/85)
d19180322三月二十二日
午前八時発にて出発。次駅にて乗り換え、祇園精舎に向かうべく切符をバルンプール(*バルランプール)停車場までのを買う。午後四時バルンプールに着く。途中、鶴二羽の野に降りいたるを見る。すぐに馬車(一荷と言う)に乗り、およそ一哩(マイル)にして町に出でビルマ人の家を訪ね、この家に宿泊することとなる。この家にはただビルマの青年と僧侶の二人。二階を領しきわめて気持よし。僧侶はサンスクリットの研究に渡印せられたるとなん。この夜は写真現像をなし、遅く床に寝る。
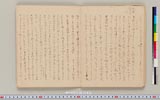
3月22日(続き)
〜3月23日(途中)
(73/85)
d19180323三月二十三日祇園精舎104
早朝ビルマ僧及び青年の案内にて祇園精舎に向かう。町より道は一直線にして、しかも十間幅の大道路。しかれども道は少々悪しくして馬車の進行は遅し。途中マンゴー樹多く、樹木青々として快感を覚ゆ。鶴及び象を見る。
町より西行十哩ほどにして古塔跡あり。下に沼二つあり、マンゴーの大樹茂れり。塔上より西北にサヘート、すなわち祇園精舎マヘート。この舎は英国城跡を近くに見る。写真を撮る。なお西行一哩にしてサヘートに着く。下にビルマ僧のダルマパーラあり。ここで昼食をなし、写真を撮り、さらにサヘートに詣ず。南門と思しき所を入り、左端に寺の跡のごとき敷石二、三ケ所あり。さらに北方二、三十歩の所にも同様の跡、井戸二つあり。さらに北方半丁の所に塔の跡及び菩提樹あり。いにしえこの樹下にて如来の説法を給いし所となん。ここに二、三の大菩提樹あり。これ阿那無陀ピッパラ樹と言い伝う。生ら十年の願い達し、ここに真実の御仏跡に合掌をなす。昔時この所、この土の上にい給いしをの感こもごも至り、去り難きを感ず。
なお進むにしたがい寺跡多くあり。如来の「常に衆生来たれ」と言う「健ものの緒」と言うもあり(*?)。詳しくはビルマ僧の話なれども、言語の自分に通ぜぬも、ややその中を知る。寺跡の分別はなはだ盛んならず。これ如来の没する所なりしならん。この面積およそ二丁四方ぐらいなりき。
さらに北一哩(マイル)ほどにして舎英城跡に至る。城廊広く北に流れを廻らし、遠く大雪山を見る。風光また美。古城跡という二ケ所あり。一つをパマリテと呼ぶ。一つを〇〇〇(*原稿欠)と言う。寛方思うに古時はこの廊内に町ありしならんと。そのほかはきわめて平坦にして五穀実り、気候またよし。古時もっとも盛んなりしを思えり。この古跡いまは荒廃してジャングルとなれり。記念の撮影をなし、夕刻帰途につく。巡査三人と苦力(クーリー)に重い荷物を持たせしはおかしかりき。またよく働くのである。
道にて牛乳を得て道路にて煮沸して飲み、月下を並木の影に歩み、十一時ごろ帰宿。写真の現像をなし床に就きしは三時ごろなりき。
d19180324三月二十四日
午前九時に起きて食事の後、町に出てバザーを見る。ラジャの庭内を見物なし、午後三時の発車にてタシオドリヤ(*次項はタシルデオリヤ)停車場に向かう。ゴランプール(*ゴラクプール?)にて乗り換え。
d19180325三月二十五日
午前十一時、タシルデオリヤ(*前項はタシオドリヤ)駅に着く。すぐにダークバンガローに入る。食後町に出て古銭及び切手などを買い求め、八時過ぎ駱駝の車にて月下を行く(往復十ルピーの約定)。久しくして眠りに就き、時どき眼を覚ます。夜風はなはだ寒し。

3月23日(続き)
〜3月26日(途中)
(74/85)
d19180326三月二十六日拘戸那掲羅105、盗を走らす
寒し。夜明けカシヤの町に着く。牛乳を求め路傍に煮る。しかして朝食の用意まったく済みて、二哩(*マイル)の地を一時間を要しクシナガラに着く。緬旬(*ビルマ)寺に入り、僧侶は老僧の高僧と若僧の二人。親切をもって吾々を迎う。昼食の馳走を受く。参拝、御仏像の写真撮影をなす。
本堂内の大涅槃像は阿菟楼駄羅漢106と(*原稿は「の」)伝えられ結構なる御作。その丈(*たけ)二丈ぐらい、英人の手にて発掘せられたるものにして、背後には阿育王建造の古い煉瓦塔あり。堂前及び側らに伽藍の御壇発開しあり。南方一丁余りの所にピッパラ、マンゴー両樹の下に降魔(ごうま)形の仏像あり。その作きわめて精巧なり。写真撮影及び写生をなす。
堂より東十丁ほどの地に如来の荼毘(だび)所あり。一つは丘の上に老樹(バニアン菩提樹)茂り、古煉瓦散在せり。嗚呼、如来涅槃の地、感こもごも至るなりきり。「吾いま如来の地に参ずるを」と。去るにしのびず。
夕刻五時帰途につく。月はなはだ明るく、すぐにしてマンゴー樹の並木のよき道を駱駝車の上にて眠る。熟睡の時「サブ、サブ」107と呼ぶ。その声大にしてただ事ならず。起き出でてみれば黒奴あり。身に一衣をも着けず駱駝の頭を後方に引く。ガリワラ車の男は二人ありといえども如何ともなすなく、ただ騒ぐのみ。これを見たる寛方は大声でこれを叱咤す。沢村君もまた同じく大声をいたす。ここにおいて彼の強盗はすぐにその手を離して走り去る。月影に見ればなお彼方にひとりの盗人ありき。実に痛快をきわめり。大声の叱咤、盗人を走らす。再び眠りに就き、夜明け方タシオドリヤの町に着く。
d19180327三月二十七日
午前九時四十七分発車にてベナレスに向かう。進むにしたがい暑気を増す。土地平坦にして五穀実り、実に宝の国なり。野生司君にはバトユー駅にて別れる。同君はすぐにパツナ(*パトナ?)より王舎城に向かう。夕刻七時ごろベナレスのカントンメントに着く。停車場にて食後、ホテル・ド・パリスに入りて宿す。停車場より六、七丁、写真の現像をなす。
d19180328三月二十八日
朝八時発車にて次駅の鹿野苑、現地名サーラナート(*足跡図はサルナート)に向かう。如来最初の説法の地、弥勒受化の所たり。停車場より良き道四、五丁の所の左方に古塔あり。この辺りを上人迎仏の所と言う。さらに四、五丁にして鹿野苑に詣ず。高塔は古く、現今その修繕をなす。西面、北面多数の発掘をなせり。向かいて右手に閣雄那寺あり。塔後に錫蘭(セイロン)のダルマパーラ仏徒休憩所あり。塔前すなわち西方に緬詢(ビルマ)寺の休み所あり。吾々はこの寺に昼食を受く。寺僧三人あり、少時談ず。
後に塔の側らの博物館を見る。みな発掘の石彫にて実に結構をきわむ。中央室正面に如来説法の御像あり。実にグプタ朝の彫刻の第一なるものなり。そのほか多数の仏の立像あり。皆みな上々の作なりき。写生及び撮影をなす。古塔は周囲を彫石をもってなし、上部は軟煉瓦をもってなす。当時の全盛を想起するものなり。
この日博物館にて小川尚義台湾視学官、小河原義照朝鮮総督視学官二氏に会す。

3月26日(続き)
〜3月29日(途中)
(75/85)
d19180329三月二十九日
午前八時、案内者を雇い馬車に乗りて市中の見物に出かく。初めグプタ朝の柱石を見、マハラジャの家を見、ガンジス河に至り舟に乗りて水浴の様を見る。まことにベナレスは「水のベナレス」と言うこと、誰が眼にも同様。多くの寺院、大なる建築物、多くの水浴者。死人を河岸に焼き、その際で水浴をなすなど、あるいはその水を飲むなど、信仰とは言いながら驚くのほかなきことにこそ。各寺院をも見る。ネパールのカリ寺院を見る。支那式の建築を意味す。彫刻は男女交合の図あり。
いちど宿に帰り、昼食の後ふたたび出かけて各寺院に至る。モンキー寺院、大理石の寺、手の寺、金の寺、そのほか商店などを見て夕刻帰宿す。八時半の発車にてモライサライ(*ムガルサライ?)に行き停車場に宿す。この待合所に昨夜小川氏が宿すと番の男が言う。
d19180330三月三十日
午前四時半発車にてパツナ(*パトナ?)に向かう。十時同駅着。馬車を雇いてスプナー氏を訪ねて会するを得、かつ昼食を馳走になる。一日を同家に暮らし、夕刻同氏の案内にて東二哩(マイル)ほどの地に発掘の跡を見るべく、同氏の友人も同乗にて馬車二台を走らす。夕色の光景また見るべきものありき。
ほどなく着く。発掘は非常に深く紀元前三世紀と言う。釋尊の在世のころなるべし。もっとも古き寺院の跡、木造建築とて朱屋根型にその骨木あり。ペルシャの影響を受けしと言う。なお跡ありとてスプナー氏大得意のものありき。さらに二丁余ほどにて王城の趾に至る。これまた同氏の発掘するところたり。
ただちに停車場に帰り、八時半の発車にて出発、ブッテヤプール駅に下車。待合室に宿す。

3月29日(続き)
〜3月31日(途中)
(76/85)
d19180331三月三十一日那蘭陀
午前九時出発。汽車は小にして同道に通れり。町及び村の中を行く。那蘭陀プール停車場下車時に野生司君あり。同車は王舎城に行くという。野生司君は王舎城を見物して那蘭陀に来たりしもの。余らはただちに那蘭陀に向かう。停車場より西一哩(マイル)半の所すべてスプナー氏の発掘。同氏のテントの中に入り昼食などをなし、発掘品を撮影し、発掘地を見る。
午後七時ごろトンガによりて王舎城に向かい、いつしか眠りにつく。「サブ、サブ」と言う声に起き出でてみれば、はやダークバンガローに着せり。時や月下にて四方の風望絶佳を覚ゆ。眼前五山の横たわるなりき。我が大和辺りにあるの感ありき。現像をなし、ほとんど眠りをとらず夜は明けり。
d19180401四月一日
早朝三、四丁行きて温泉あり入浴。はなはだ気持よし。いったん宿に帰り出発の用意をなし、スプナー氏の好意による案内者及び苦力(クーリー)二人を連れ、リョジセン、サイラギリに向かう。旧王舎城を過ぎ、ジャングルの中を二哩ほど進む。周囲五山を廻らし王城のあるべき所なり。ほどなくサイラギリに達す。
時にこの日特に暑気強し。勇を起こし登山をなし、困難を排して頂上に達し、岡師の建てたる石塔を拝せしときは、涼風来たりて暑気を忘る。撮影をなし、下山をなし、バンガローに帰りしときは身心はなはだ疲れたり。夕刻雷雨あり。この日の暑さはそれがためなりき。ことにこの朝入浴をもなせしは良からざりき。

3月31日(続き)
〜4月2日(途中)
(77/85)
d19180402四月二日
小雨あり、小時にして雨止む。この王舎城108はビハル州にありて、その地勢、吾が大和の室生に近き地に髣髴たり。五面は山をもって囲み、ビプラ、ラツナ、ウダヤ、ソーナ、バイバーラの五山をもってす(*五山のイラストあり。名称は少し異なる)。
ヴイブラ(*前出はビプラ)、バイバラ(*バイバーラ)の両山相通り、その間二丁余りにして天然の関門をなせり。バイバラ(*バイバーラ)山下に温泉ありてヒンズーの寺内になれり。この城内は地平坦にして王城のあるべき所。我が大和大原の大なるにも似たり。
この日旧城跡に行き、竹林精舎辺りとも思しき所に詣ず。バイバラ(*原稿バイバル)山下に窟あり、一彫刻を安置す。岡師及び野生司君の落書きあり。余らも書き付く。家宅地の風光は釋尊永住のしからしむ、ことに霊鷲山サイラギリ山上より見たる光景はまた格別のものなり。嗚呼、釋尊半生をこの地に在りませりと。
午後三時発車にて出発す。ヒンドゥー教の石彫破片を売る者持ち来たり、一ルピーにて買い求む。バルランプール停車場にてスプナー氏の下役のおのおの引き上ぐるに会す。同車をグデヤプール駅にて乗り換え、二時間を要しパトナジャングションに一夜を明かす。

4月2日(続き)
〜4月3日(途中)
(78/85)
d19180403四月三日仏陀伽耶109
午前十時半、(ブッダ)ガヤ駅110下車。すぐに馬車にて八哩(マイル)というを馳せて仏陀伽耶に着く。この時間二時間余り、途中右手に小山あり。美麗にして町はその下にあり。樹木また多く、東にニレイゼン河(*ニランジャナ河)111、すなわちニランジランと土語に言うを樹下に見、河向こうには前正覚山を見る。西南の地は曠野渺茫たるがきわめてその霊地たるを思わしめ、吾ら初めて見るの快、天地にこれ真に如来成道の聖天地。不肖、仏跡参拝の大願をこの大聖地仏陀伽耶をもってその修むるところとなる。有難し有難し。
仏塔西にビルマ人の建つる参拝者宿泊所の立派なるあり。そこに入りて休憩なす。昼食を受けしのち参拝をなし来たりて象にて進む。三時を約し東ニランゼラン(*前出はニランジラン)を過ぎて小村を過ぐ。左手に小高き土岡あり。これシャジャタ(*スジャータ?)女の家の跡と言い伝う。それより東一、二丁にして大自在天祠の傍ら、合眠(ガーチ)樹下となすを乳糜(にゅうび)供養の地となすと。東南一丁にして〇〇〇(*ニランジャナ河?)と言う河に出で前正覚山を見る。風望ことによし。吾が象上にて撮影なす。南一丁に堂あり、龍神石彫を安置せり。夕刻帰る。感深し、感また深し仏陀伽耶の地。
(*イラストあり)
d19180404四月四日
午前十時半出発。仏陀伽耶のバザーに出て金の壺を求め、午後二時発にて出発、帰途に向かう。この辺りすべて山脈続き。
d19180405四月五日
午前八時ハウラ着。沢村君と別れ、タゴール翁方に帰る。昼食の後三井に行き笠松氏に面会す。時に沢村君もあり洋食堂に案内せられ、日本郵船に行き大谷氏に面会。夕食の馳走になり桐谷、野生司君の二人もすでにあり十一時に帰る。久しぶりの日本食、多く食し多く呑む。
d19180406四月六日
午前中、岡、武樋氏の二人来る。午後沢村君の来るを約せしため待つこと久し。ついに来たらず。津田、小林、野生司の三君来る。タゴール翁に紹介をなし、付近のラジヤ家を見物に行く。油絵はなはだ多し。のち野生司君と沢村君を三井社宅に伺い、夕食にすき焼きを馳走になり十一時ごろ帰る。
d19180407四月七日
午後八時半発車にて、沢村君孟買(ムンバイ)に去る。停車場に送る。

4月3日(続き)
〜4月7日
(79/85)
d19180408四月八日
午後千田氏を訪ね夕食を馳走になり、同車にて錫蘭(セイロン)丸に桐谷、野生司君を送る。帰途千田氏の宅に寄り一時過ぎまで話し、ついに宿す。如来誕生の日、降誕の下図112を始む。
d19180409四月九日
チョレンゲに千田氏同乗。別れて買物をなし、のち岡師を訪ねる。昼食の馳走を受け夕刻まで談ず。時に武樋君も来る。
d19180410四月十日
在宅。
d19180411四月十一日
在宅。
d19180412四月十二日
万歳商会に至り、写真焼き付けを依頼のため猪子氏に頼む。
d19180413四月十三日
在宅。岡師来る。前原氏も来たり、ともに談ず。前原氏は午前中に帰る。岡師に昼食を馳走なさしむ。兌(*?)で食す。夕刻まで談ず。
d19180414四月十四日ベンゴールの一月元旦 日曜
約定により午前中岡師を訪ね、万歳商会の猪子氏宅に昼食の馳走を受く。肉のすき焼きうどんにて、はなはだ美味を感ず。帰途岡師と古道具屋を見る。鍍金仏(めっきぶつ)一体を買い求め、なおバザーに行きカバンを見る。この日吉田夫婦及び木村氏も見えたり。
d19180415四月十五日
午後七時、前原氏の宿所グレードエーストンホテルを訪ね、夕食の馳走を受く。印度(インド)花もありき。
d19180416四月十六日
揮毫。
d19180417四月十七日
揮毫。
d19180418四月十八日
揮毫。
d19180419四月十九日
揮毫。
d19180420四月二十日
揮毫。
d19180421四月二十一日日曜
揮毫。
d19180422四月二十二日
揮毫。
d19180423四月二十三日
揮毫。
d19180424四月二十四日
揮毫。
d19180425四月二十五日
揮毫。
d19180426四月二十六日
揮毫。
d19180427四月二十七日
揮毫。千田氏宅に行き、この夜宿す。
d19180428四月二十八日日曜
揮毫。岡師家替えいたす。余も行き半日を送る。茂垣氏も同宿になる。
d19180429四月二十九日
揮毫。
d19180430四月三十日
揮毫。前原氏訪ね来る。余留守。夜、ホテルに訪ね行く。
d19180501五月一日
乾夫婦着もありき。帰途、自動車にて乾夫婦のために送らる。

4月8日
〜5月1日
(80/85)
d19180502五月二日
夕刻、ゴゴネンドロナト氏と同道にて千田氏宅に行き、夕食の馳走になる(*はずの)手紙の行き違いのため少し不都合にてありしは、千田氏余らの行くことを知らざりき。ために外約にて出で行く。しかれどもこの日曜を約し、再び夕食を受くることになりき。
d19180503五月三日
揮毫。千田氏妻君来る。ゴゴネンドロナト氏に筆及び墨と紙を呈す。
d19180504五月四日
揮毫。この日オボニンドロナト・タゴール氏より菩提樹を贈らる。またゴゴネンドロナト氏より籠及びベンゴール布縫いのもの一葉及びボタン43、婦人の耳飾りを贈らる。またシャモネンドラ氏より真鍮(しんちゅう)の壺を贈らる。ボシュ君より筆、紙を買い求めて送ることを依頼せらる。金四十ルピーを預かる。
夕刻オボニンドロナト・タゴール氏来たり、「君はグレートアーチストである」と屏風を見て言われる。「初め、ほとんど画を見せずありしが」と言う。非常に称賛してありき。
d19180505五月五日日曜
揮毫。ムクル君旅行より帰り来たりて会す。夕刻よりゴゴネンドロナト氏と、千田氏宅に夕食の馳走になりに出かく。
d19180506五月六日
揮毫出来(しゅったい)す。ミセス・タゴールに切れ地及びおもちゃ竹籠を贈らる。この日多くの人びと来たり見る。皆みな称す。オボニンドロナト氏は「君は初めさらに絵を見せぬに、帰るころ善良の絵を見せてくれてよき画家である」と言う。
午後領事館に行き旅行券の裏書を願い、吉田君に雪山の巻の下画を呈す。それより警察に行き旅券を願い、また正金銀行に行き預金を引き下げる。多くは大阪にて下がることになり手形を得る。ただちに岡師及び茂垣氏に夕食の馳走を受く。食する者は猪子氏及び他ひとりありて、はなはだ愉快なりき。

5月2日
〜5月7日(途中)
(81/85)
d19180507五月七日
写真などを撮り、午後万歳商会に行く。猪子君に案内を頼み宝石を買い帰宅。すぐにボシュ君の宅にて夕食を馳走になり、絵画二葉を贈る。うち一枚はボシュ君の絵。
またまた千田氏の夕食に同氏宅に行く。山王丸船長及び大谷氏113その他の人びとと屏風出来披露のための会食をなす。千田氏も大いに嬉び面目をなせり。この夜は船長と千田氏宅に同宿す。
d19180508五月八日
早朝帰宅。タゴール翁の誕生日とて、古代式の夕食をなすため装飾をなす。翁は小生のために絹地に文字を書きて贈らる114。誕生の日早朝に筆を執りたるは真に記念と、また家宝となるべきかな。夜は七、八十人の人びと来たり会食をなす。
d19180509五月九日
岡君来る。二人にて外出し買物をなす。午後千田氏より使いありて荷物の運搬をなす。夜八時、千田氏宅に引き移る。
d19180510五月十日
朝、博物館の事務員の家に行き、博物館の画の部屋を見る。夕刻館を出て、ムクル君に会し花などを見る。夜、岡師及び吉田、茂垣、武樋、そのほか三井の人びと来たり屏風を見る。皆みな褒むる。
d19180511五月十一日船に乗り込む
自動車によりて植物園に至り、午後西船長と千田氏宅に行き、後の荷物を持ちて船に行き検疫を受け、再び千田氏宅に行く。笠松氏そのほか三井の人びとありて屏風を見る。千田氏得意なりき。
夕食の後、十時ごろ船に行く。千田氏夫婦、秋山、岡、茂垣、武樋、箕作、〇〇〇(*原稿欠)、田島(嶋)氏代理、ムクル君など、送別のため船まで来る。大谷氏より更紗三、箕作氏より茶数個及びチベット女の胸下げ、吉田氏より更紗一、ムクル氏より花及び籠、那蘭陀(ナーランダ)土中土印一、その他などを贈らる。千田氏よりジャワ古面一箱を贈らる。
船は一時(*次項では七時)出航す。植物園近傍にて宿す。

5月7日(続き)
〜5月12日(途中)
(82/85)
d19180512五月十二日出航
七時(*前項は一時)過ぎ出航。時どき雨降る。午後四時半停船す。
〈印度の所感〉
渡航以来、ここに一有半歳を送る。その間苦楽こもごも至り、再びするなき宝を得たる、これ信なる仏の導き給う有難かりけることなりき。山は世界に類いなき大雪山、ガンジス河、ジャムナ河の清流、わが国の感あるペシャワール近傍、いまなお盛んなる仏教国たる錫蘭(セイロン)島、花咲き鳥飛ぶアジャンター寺洞窟、五穀実る古仏跡の地、まず一通りの国々を、替わる民びと、あるいは流行り病の地を旅する余らも上中下、渡る世間の人びとも無情有情も様ざまの、深く深く我が胸にきざみしことは大いなる賜物となん。
今の印度の人びとは、ただただ己と言うのみかな。口と実との添わぬことは上も下も同じ様。弱なる国のある事にて憐れむよりは外なかり。四生(*ししょう。原稿は「四性」)と有実いまに引き、情に疎くなりしなり。これ世の常と、皆とは異国の下に住む民びとは僻(ひが)む心となるべきかな。仏の国の民びとと余らも同情いたすなり。衰えし国の哀れさは、国に製作(*政策?)、また美術なし。ただ天然の食を得る眠りの長き印度の国、醒むる朝日はいつならん。
d19180513五月十三日
午後、河口を煽(あお)るモンスーンの初めとて浪やや高く、大うねりありて気持はなはだ悪し。
d19180514五月十四日
時どき降雨あり。風は南より吹く。船は前横ともに動く。気持悪し。
d19180515五月十五日
前日同様。
d19180516五月十六日
前日に同じ。
d19180517五月十七日
風浪高く、デッキに浪を打ち上ぐ。食事をとれず伏すこと終日。
d19180518五月十八日
風浪ややおさまる。しかれども、ために熱を発し、午後には身体痛み、はなはだ疲れる。熱は三十九度四分という高きをなす。氷などを頭にのせ眠りをとれず。

5月12日(続き)
〜5月18日
(83/85)
d19180519五月十九日
熱まったく引く。初めてキナイン(*キニーネ)を飲む。食事少しとる。
d19180520五月二十日
新嘉坡(シンガポール)を過ぎる。夕刻、その空の色、海の色、島の色、絶美をきわむ。斯様の景色またほかに多く見ず、熱国の夕べ特別の色をなす。デッキ上にありて見うるかぎりに親しむ。シンガポールの美、深く深く忘ることを得ず。
d19180521五月二十一日
病まったく快癒す。また浪おだやかにして、油を流せしごとく気持よし。
d19180522五月二十二日
前日同様。
d19180523五月二十三日
前日同様。仏領のサイゴン(西貢)付近の国見ゆ。尺五絹本に揮毫す。
d19180524五月二十四日
浪少しある。尺三絹本に揮毫す。
d19180525五月二十五日
追手の風ありて浪また少々あり。船進む。尺五絹本に揮毫す。
d19180526五月二十六日日曜
午後、香港沖に達す。
d19180527五月二十七日
午後五時ごろ和田丸を追い抜く。満月海上を照らし美感をきわむ。
d19180528五月二十八日
気候いよいよ深し。風ありてうねりあり、気持悪し。
d19180529五月二十九日
同。
d19180530五月三十日
箱を造り荷物を造る。うねりなく天気よし。気持はなはだ快。
d19180531五月三十一日
風浪高く、四面ガスかかりて見えず。時どき島を見る。午後一時、唐津港に着く。四面山をもって包み景色よし。
久しぶりにて見る日本、その嬉しきことかぎりなし。検疫、税関の者来たり何なく済む。三井物産の井上一氏も来たり会す。四時ごろ上陸、山佳という旅館に宿す。

5月19日
〜5月31日
(84/85)
d19180601六月一日
人力車によりて本唐津町見物に出かく。町内に近松寺あり。門左衛門の墓あり。時に井上氏ありて会す。当町の有志宮島徳太郎氏、生のために名所の案内をなす。帰途宮島氏の邸宅に行き暫時休息す。景色また絶佳。同氏及び井上氏により町にてもっとも上級の料理店に案内せられ、昼食の馳走を受く。芸子二人来たり二、三時間を要す。帰途井上氏の会社に行き、ほどなく宿に帰る。
舞鶴の公園より虹の松原を見る。その風光天下の絶景にして、天橋立によく似たるありて、日本三景のうちに入りても劣らぬものと感ず。当地は三韓征伐でその出船の地。佐依姫(*松浦佐用姫のこと)の古跡名を残し、城跡そのほか古跡に富む。久しく外国の荒漠たる地にありてこの絶秀に接す。いっそうの感を深くせしならん。虹の松原を再び見るときに海岸に美なる花を見る。これその名を水浪寿草という。
d19180602六月二日
朝七時半の発車にて、機関長及び古川の社員と三人連れにて帰京の途につく。四駅目に相知(アイチ)という駅より約十丁にしてウドノ(鵜殿)の岩屋あり。岩石に仏彫刻の多くあり、前年小川博土の発表する所たり。降雨のため遺憾ながら見ずに過ぐ。
二度乗り換えをなし二日市町に下車。太宰府神社に参詣をなし、次の発車にて門司に着く。坂田氏を訪ぬべく予定を変更し、七時の急行車にて大阪に向かう。機関長及び古川の社員二人も列車に同乗す。
d19180603六月三日
午前八時、梅田駅に着く。ただちに西照庵に宿す。妻のところに電報を出す。すぐに返電あり、「今晩行く」とあり。

6月1日
〜6月3日
(85/85)